放射線の基礎知識 「放射線とは何か」に始まる、放射線に関する用語解説集 不安に陥らないために、今こそ「放射線」の基本の「き」から学ぼう
物理学的半減期・生物学的半減期
| 核種 | 半減期 | |
| 酸素15 | 15O | 2分 |
|---|---|---|
| ナトリウム24 | 24Na | 15.0時間 |
| ラドン222 | 222Rn | 3.8日 |
| ヨウ素131 | 131I | 8.0日 |
| コバルト60 | 60Co | 5.3年 |
| ストロンチウム90 | 90Sr | 28.8年 |
| セシウム137 | 137Cs | 30.0年 |
| ラジウム226 | 226Ra | 1,600年 |
| 炭素14 | 14C | 5,730年 |
| プルトニウム239 | 239Pu | 2.4万年 |
| カリウム40 | 40K | 12.8億年 |
| ウラン238 | 238U | 44.7億年 |
放射能の強さは時間とともに弱まります。原子が放射線を出しながら安定した別の原子に変わっていくため、原子の数が減るからです。原子の数が半分になるまでの時間を半減期と呼んでいます。しかし、半減期を迎えたからといって、放射能がなくなったわけではありません。
表6は、代表的な核種(原子核の種類)の半減期を表しています。あっという間になくなるものから、宇宙の歴史とほぼ同じ長寿命まで幅が広いですね。前述の検査用ラジオアイソトープには、非常に短い核種が使われています。この図の半減期を物理学的半減期といいます。
図7は、半減期を迎えるごとに、急速に放射性元素の数が減っていく現象をグラフ化したものです。
福島原発事故で放出されたヨウ素131の半減期は8日間ですが、その原子を1000個とすれば、8日後に500個、16日後にその半分、80日後には原子数も放射線の量もゼロになります。やはり外部に放出されたセシウム137は、半減期���30年と長く、千分の一に減るまでに300年を要し、それ以降も放射能を持ち続けるのです。
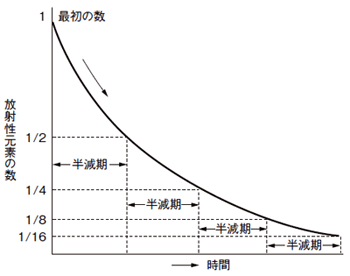
一方、生物学的半減期というのは、体内に取り込まれた放射性物質が排泄や代謝の影響で半分に減少する現象です。これを物理学的半減期と同列に扱うことはできません。
ヨウ素131の物理学的半減期は8日ですが、チェルノブイリ原発事故後の追跡調査の結果、乳幼児の甲状腺に溜まりやすく、140日後に半減した医学的事実が明らかになりました。一方で、セシウム137の生物学的半減期は110日と短くなっています。体外に排出されやすいようなのです。
生物学的半減期については、たとえば骨や臓器など体内のどの部分に蓄積し、排出されにくいのかといった問題など不明な点が多く、一刻も早い解明が待たれています。
自然放射線と人工放射線
宇宙が約46億年前に誕生した瞬間から放射線は存在しています。地球上でも、宇宙から降ってくる放射線の中で、大地や食物からの放射線も取り込みながら人々は暮らしてきました。このような自然放射線を1年間に受ける線量の世界平均は2.4ミリシーベルトになります。
海抜が高いほど宇宙線の量も多く、高い高度を飛ぶ大型ジェット旅客機の乗客やクルーも案外高い線量を浴びています。土壌や岩石中に含まれる放射性物質と、地表に降り注ぐ宇宙線が溶け合って植物に取り込まれ、食物連鎖を通して日常の食品に放射性物質が含まれます。カリウム40は代表的なもので、自然界では野菜や肉類、海藻などに含まれています。
人工放射線は、文字通り人間が作り出した放射性物質から出る放射線です。図8を見てください。医療に欠かせないCTなど放射線診断装置や放射線がん治療、原子力施設内での被曝事故、古くは核実験による放射性降下物(フォールアウト)などがあります。原発事故以外に、原発周辺にごくわずかな放射性物質が出ることがあります。それを最小限に抑えるため、線量目標値が設定されています。
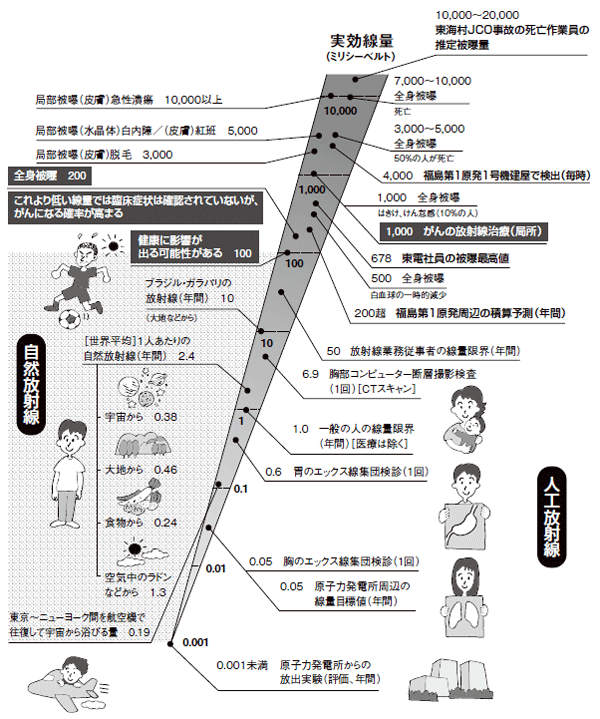
人工放射線は、医療用であっても極力浴びないようにすべきです。意外に被曝線量が高いCT検査は、必要がない限り受けないことです。
自然放射線の場合もその通りなのですが、以前から、低い線量の放射線には身体のさまざまな活動を活発化させるホルミシス効果がある、と主張する研究者も多いようです。一種のホルモン刺激説ですが、賛否両論があり、結論は出ていません。
原爆と原発の違い── 被爆と被曝
| 広島原爆 | 長崎原爆 | |
| 投下日時 | 1945年8月6日 午前8時15分 | 1945年8月9日 午前11時2分 |
| 原爆の種類 | 砲身型ウラン原爆 U約60kg使用 核分裂したのは約0.7kg | 爆縮型プルトニウム原爆 Pu約8kg使用 核分裂したのは約1kg |
| ニックネーム | リトル・ボーイ | ファット・マン |
| 重量 | 約4トン | 約4.5トン |
| 威力 | 約16キロトン | 約21キロトン |
| 爆発高度 | 約600m | 約500m |
| 人口 | 約42万人 | 約27万人 |
| 1945年末までの死者 | 14±1万人 | 7±1万人 |
| 1950年10月までの死者 | 約20万人 | 約14万人 |
ウラン235に中性子を当てると核分裂が起こり、エネルギーが生じます。核分裂が次々に起こる連鎖反応を利用し、莫大なエネルギーを得るのが原子力発電です。
しかし、1940年代前半に人類が手にした核分裂連鎖反応は、原子爆弾という不幸な形で最初に実現してしまったのです。広島、長崎に投下された原爆は、表9のように種類が違いますが、威力はほぼ同じで、それぞれ10数万人以上の命を奪いました。
1954年、旧ソ連で実用規模として世界最初の原発(5000キロワット)が運転を開始し、日本でも65年に東海村で稼動しました。核エネルギーは核兵器(軍事利用)と商業発電(平和利用)の2面性を持ち、今日に至っています。
原発などで放射線を浴びたり、自然放射線を受けたりすると、放射線を「被曝」したと書きます。
これに対し、原爆の被害や、ビキニ環礁での水爆実験による第五福竜丸被災事件の場合は「被爆」と記します。前者は放射線に曝されるという意味、後者は爆撃に遭ったという意味です。原爆も原発も核分裂反応という同じ原理に基づいた、表と裏の関係ともいえます。
原発で出る放射性廃棄物
現在、国内には電力会社など11社が計54基の原子炉(原発)を所有しています。「核のゴミ」と称される放射性廃棄物が当然ながら多量に出てきます。炉内で燃焼(核分裂)させた燃料棒(使用済み燃料)をはじめ、浄化用フィルター、ろ過装置、放射線防護服・手袋類、除染した後の放射性廃液などです。
使用済み燃料には高い放射能レベルの核分裂生成物が含まれます。青森県六ヶ所村の再処理工場でウランから生じたプルトニウムと一緒に分離・抽出する計画ですが、まだ稼動しておらず、原子炉建屋内の燃料プールなどに保管されたままです。
放射能レベルが低い廃棄物は原発敷地内に、セメントなどで固めたドラム缶にして保管されています。すでに60万本以上になっていますが、受け入れ先の低レベル放射性廃棄物処理センター(六ヶ所村)がまだ稼動しておらず、溜まる一方です。原発建設が始まった当初から、「トイレなきマンション」と呼ばれていた事情は今も変わりないのです。
放射線でなぜがんになるのか ──発がんリスク
細胞内にあるデオキシリボ核酸の略称であるDNAは、「生命の設計図」ともいわれるほど重要な遺伝情報の担い手です。遺伝情報を記録して、次の世代の細胞に伝えるからです。
放射線を浴びてDNAに損傷が起こると、新しい細胞が作られなくなったり、異常な細胞ができたりします。この異常な細胞が元の細胞とは異なった性質を持つと、大半が死んでしまいますが、生き残る細胞もあります。それががん細胞になっていくと考えられています。
図8で示したように、被曝線量が100ミリシーベルト以上になると、がんになる可能性があるといわれています。世界の放射線防護の専門家でつくる国際放射線防護委員会(ICRP)は、放射線被曝により、がんで死亡する危険(リスク)が、1000ミリシーベルトで5パーセント高まると公表しています。200ミリなら1パーセント、100人に1人が発がんする計算です。一般的には200ミリ以上でがんリスクが高まるとされています。
図8で7000ミリのケースは、急性症状が出る早発性障害と呼ばれるものですが、晩発性障害として現れるがんの場合は、20年以上の潜伏期間があります。ただ、放射線以外に喫煙、大量飲酒、食べ物などライフスタイルの影響も絡み合って、がん細胞の増殖が加速される可能性も高いといわれています。
ちなみに、がんの放射線治療では通常、局所に1000ミリシーベルトを照射しますが、皮膚表面や周辺の正常組織にも多少当たります。しかし、そこががん化することはありません。


