放射線人体への影響 事故発生時から現在、そして今後の放射線の影響を正しく知る 原発事故による放射線の影響 不必要に怖がらず、必要な対策を
-放射線被曝を防ぐために- 現在は土壌の放射性物質が問題
| ヨウ素 I-131 | セシウム Cs-134 | セシウム Cs-137 | ストロン チウム Sr-89 | ストロン チウム Sr-90 | |
| 出す放射線 の種類 | ベータ ガンマ | ベータ ガンマ | ベータ ガンマ | ベータ (ガンマ) | ベータ |
| 物理的に放射能が 半分になる期間 | 8日 | 2年 | 30年 | 50年 | 29年 |
| 身体中の放射能が 半分になる期間 | 約7日 | 約80日 | 約100日 | 約50日 | 約20年 |
| 蓄積する 器官・組織 | 甲状腺 | 全身 | 全身 | 骨 | 骨 |
原発事故が起こってから現在に至るまで、状況は刻々と変化している。3月中旬から下旬までは、事故が起きた原発から大量の放射性物質が大気中にまき散らされ、それが風で広域に運ばれた。そして、雨が降ったことにより大気中に浮いていた放射性物質が地上に落ちた。
現在は大気中には放射性物質はほとんどないが、地面に落ちた放射性物質が問題である。また、現在環境中に残っている放射性物質は、放射能が半分となる期間(半減期)が長いセシウムという放射性物質がほとんどである。
今回の原発事故で生活域に放出された放射性物質のうち人体への影響が大きいものは、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137だが、環境中での半減期は、ヨウ素131が8日であるのに対し、セシウム134は2年、セシウム137は30年である。だが、体内に放射性物質が入った場合、尿や汗などによって排出されるため、体内での生物学的な半減期は短くなり、ヨウ素131は約7日、セシウム134は約80日、セシウム137は約100日となる。今後は、半減期の長いセシウムへの対策が課題である。
外部被曝と内部被曝を避ける
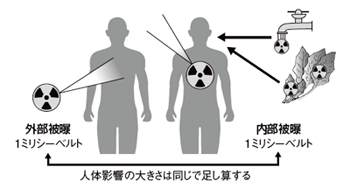
放射線被曝の経路には、大気中や土壌に存在する放射性物質から出される放射線を浴びる外部被曝と、放射性物質を含んだ水や食物などを摂取することで体内に放射性物質が取り込まれる内部被曝がある。人体への放射線の影響は、外部被曝と内部被曝の両方から考えることになる。それぞれの被曝を避けるための対策を知っておきたい。
外部被曝に対する対策は、①離れる、②遮る、③時間を短く、が3原則である。
「放射性物質から出る放射線が届く距離は数10メートルですから、まず離れることが非常に重要です。また、放射線はブロック塀などで遮ることができますので、屋外より屋内のほうが放射線量を浴びる量が低くなります。そして、高濃度に汚染された場所を知り、放射線量が高い場所には長時間留まらないようにしたほうがよいでしょう」と米原さんは説明する。
一方、内部被曝への対策は、規制値を超える食物を食べないこと、風の強い日は土壌に溜まっているセシウムが巻き上がる可能性があるのでマスクをして吸い込まないようにすること、土が付着したらすぐに洗うことである。そして、新たに放射性物質が放出されていないか、情報を入手することも重要である。
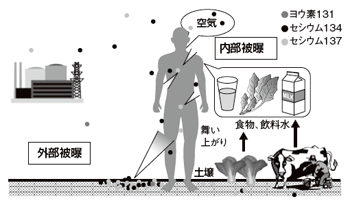
市場に出ている野菜などは国や自治体により暫定基準値を超えるものが流通しないよう管理されているが、自家栽培や野生の山菜、キノコなどは汚染状況が不明であるため、食べるのは避けたほうがよい。牛肉は一部規制値を超えたものが流通したが、チェック体制をしっかりとする必要がある。ただし、基準値は、その濃度のものを1年間食べ続けてもある基準の線量を超えないように十分に余裕をもって決められているので、一時的に基準値を超えたものを食べた場合でもその基準の線量を超えるようなことはない。また、野菜は水洗い、あく抜きをして煮汁は飲まないこと、酢漬け、酢洗浄を行うこと、土が付着している根は切り落とすことで、食品に含まれるセシウムの量を減らすことができる。
日常生活でも自然放射線を浴びている
実は私たちは、今回の原発事故が起こる前から、宇宙線やラドンなどからの自然放射線を浴びている。1人あたりの自然放射線の年間被曝量は、世界平均で2.4ミリシーベルト、日本平均はそれよりも低く1.5ミリシーベルトである。インドのケララ州は自然放射線量が10ミリシーベルトと高く、その地域の住民は、現在東京で測定される放射線量よりも高いレベルの自然放射線を浴び続けていることになるが、がんの発生率が高いという報告はない。
また、生きていくために摂取しなければならない元素の1つにカリウムがあるが、食品に含まれるカリウムのごく一部(0.012パーセント)は放射性で、私たちは放射性カリウムをさまざまな食品から取り入れている。たとえば1キロあたりに換算すると、干ししいたけに700ベクレル、魚に100ベクレル、ほうれん草に200ベクレルの放射性カリウムが含まれている。
「今回の原発事故で、まったく新たな物質が体内に入ってきたと考えると恐怖感は大きくなりますが、今までも私たちは放射性物質の中で暮らしており、普段から食べている食物にも放射性物質は含まれていることを知れば、安心できると思います」
過剰な不安を持つことで、かえってストレスが高まることが懸念されると米原さんは話す。
正しい情報を入手し、注意すべきところは注意する
放射線の影響に関わる情報はテレビ、雑誌、インターネットなどから大量に得ることができる。その一方で、デマや偏った情報も飛び交っており、正しい情報を適切に選択することが求められる。米原さんは「現状に則した正確な情報提供と信頼関係の構築が必要です。一方的な情報発信だけではなく、住民にじっくり時間をかけて説明することが大事です」と語る。
信頼性の高い情報は、放射線医学総合研究所をはじめ、公的機関から入手することができる。
誤った情報、偏った情報に惑わされず、信頼性の高い情報に基づいて、正しい判断、対策を行っていきたい。


