型にはめた支援ではなく、人と人とのつながりを重視した支援を 未曾有の大災害から考える人間の本質的な生き方とは
長期の避難で地域文化が失われる

たとえば私が暮らしている三春町には、浜通りの富岡町に暮らしていた人たちが300人避難しており、富岡町の臨時役場も設けられています。また福島県郡山市のビッグパレットという施設、さらにはそれ以外の地域でも、多くの富岡町民が避難生活を余儀なくされています。
つまり富岡町という同じルーツを持つ人たちがいくつもの異なる地域に分散して暮らし、それがいつまで続くかわからない状況が続いているのです。となると、富岡という町で育まれてきた文化や歴史はどうなってしまうのでしょうか。
なかには避難地に溶け込んで自立すればいいという人もいます。しかし、事はそう単純ではありません。
それは、仕事という事柄1つをとりあげてみてもよくわかります。この不況下で仕事を見つけること自体が大変でしょう。しかしそれだけではありません。富岡町をはじめとする浜通りには、先祖代々、漁業を生業として生活を営んできた人たちも決して少なくありません。その人たちが簡単に自らを育んでくれた漁業を捨てることができるのでしょうか。仮に他の仕事につくことができたとしても、その仕事に適応することは、並大抵のことではないでしょう。
さらに町の機能の維持という面でも困難が生じています。今回の震災では、多くの消息不明者が出ています。そのなかには瓦礫に埋もれた死者も多いことでしょう。しかし、それとは別に放射能による難を逃れるために、いち早く自発的に他の地域に避難した人たちも決して少なくないのです。そうした人たちとのつながりをどう維持していくのか。実際どこにいるのかわかりませんから、富岡町では義援金の分配にも難渋しているほどなのです。
原発の損傷による放射性物質汚染には、こうした郷里をどう捉えるかという人の生き方に直結したきわめて本質的な問題が潜んでいるのです。そのことを考えずに、復興対策に取り組むのは早計といわざるを得ないでしょう。
生活をゼロから構築し直すということ
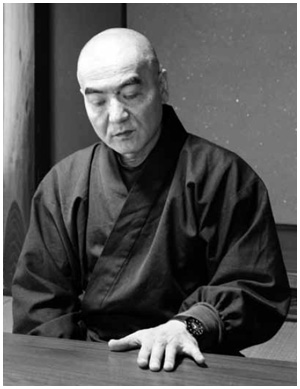
こうしてみると被災者の支援対策は、まだ端緒についたばかりであることがわかるでしょう。しかし、震災発生から現在に至るまでのプロセスを通じて、被災者はもちろん、彼らを支援する私たちも、これからの生活、生き方を考えるうえで、とても大切なことを学んでいるのも事実です。
避難生活とは生活をゼロから構築し直していく作業でもあります。まずは衣食住を確保することから始まって、次第に文化的な欲求を満たしたいと考えるようになる。三春町の書店でも、この3月は前年の1.5倍も本が売れたそうです。これは被災者の人たちの欲求が衣食住から文化的な側面に向かい始めてきた結果といっていいでしょう。
そうしてゼロから自らの生活を構築し直すなかで、被災者の人たちは、本当に自分に必要なものは何かということを改めて理解しているのではないでしょうか。たとえば日がなパソコンに向かっていた人が、避難生活を送るようになって、毎日家族や大勢の人と話している自分の変化に驚いているような例もあるのです。
東日本大震災を通じて、何を学び取るか
同じことは、彼らを支援する私たちにもあてはめることができます。被災者を支援している人たちは、彼らにとって何が必要かということを考え続けているはずです。それは自分ではそうと意識しないでも、避難生活を疑似体験していることを意味しているのではないでしょうか。それを自らの生活の見直しにつなげていけばいい。
そして、そうしたプロセスを通して、自らの生活のなかで、本当に必要なものと、そうでないものを自然に区分する習慣を身につけることもできるでしょう。かくいう私自身も、ふと気がつくと被災者への支援を続けるなかで、今やるべき仕事とそうでない仕事を仕分けする自分を発見しています。野菜や果物も、旬以外のものは要らないと思うようになりました。余計な電気を使ってそんなことしてほしくない。
これは言葉を変えれば、生活の本質を見抜く目を持つようになったことを意味しているのではないでしょうか。翻ってみると、私たちはどれだけ生活のなかで無駄なぜい肉を増やし続けてきたことか。
今回の災厄を機に、被災地にいる人も、読者のがん患者さんも、私たち1人ひとりが生活の本質を見きわめて、自分にとって意味のある暮らしとは何かを考えてみてほしいと思います。災いから学ぶことで、今回は被害を免れた私たちも、人生をより意義深いものにすることができるのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 風聞・間違ったイメージに惑わされず、正しい知識に基づいた判断を期待 国立がん研究センター緊急会見「原発事故による健康被害、現時点でほぼ問題なし」
- 災害時にがん患者がパニックに陥らないための7箇条
- 大震災で学んだ、弱者の視点に立った新たなまちづくりを 末期がんを乗り越えたその力を今度はまちの復興へ
- ストーマ装具を失った患者たちの不安の声にどう対処したか 被災地のオストメイトたちの危機はこうして解消された!
- がん患者さんはもっと声をあげて! 不安に満ちた被災地のがん患者さんたちの声
- 型にはめた支援ではなく、人と人とのつながりを重視した支援を 未曾有の大災害から考える人間の本質的な生き方とは
- 巨大地震発生!そのときがん患者は、看護師は、医師は
- 原発事故を乗り越え、自然の声を聞け


