- ホーム >
- 連載 >
- 赤星たみこの「がんの授業」
【第十八時限目】臨床試験 臨床試験と人体実験はどう違う? 治験って何?
受けたい試験が受けられない
臨床試験を受ける最大のメリットは「最先端医療が無償で受けられること」、これに尽きます。とくに、これまでの治療法や薬剤で思うような効果が出なかった患者さんにとっては、新薬を試せる絶好の機会。私の姉は何回か乳がんの再発を繰り返しているのですが、「効果がある薬なら、多少のリスクは冒してでも試してもらいたい」というのが、妹としての率直な気持ちです。
しかし、臨床試験中にどのような副作用が出てくるかは予測しきれません。また、今の日本では患者が臨床試験を受けたいと希望しても、思うように受けられる状況にないという点もデメリットの1つでしょう。現在、厚労省の基準(新GCPに対応できる医療機関)は、国立がん研究センターなどのがん専門病院や主要な大学病院など、ごく一部に限られています。また抗がん剤の場合、「いつどこで、どんな臨床試験を行うか」といった情報も公開されていません。
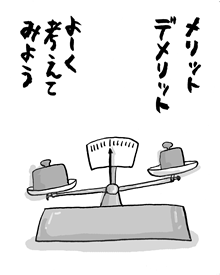
そんなわけで、たまたま臨床試験が行われる病院に行った患者さんが、主治医に誘われて参加するケースがほとんど。万人に機会が開かれているとはとても言えないのです。
しかも、首尾よく臨床試験に参加できたからといって、必ずしも新薬による治療が受けられるとはかぎらない。なぜならフェーズ3の比較試験は「ランダマイズド・トライアル」(無作為に振り分けて行う試験)の形式で行われるからです。比較試験では、患者は新薬(新治療法)を投与されるグループと、既存の薬(治療法)を投与されるグループに分けられます。そのどちらを割り当てられるかは、まさにクジ運次第!自分は新薬の投与を受けたいと希望しているのに、既存の薬を割り当てられてしまう可能性だってあるわけです。「新薬の可能性に賭けたい」という思いが必ずしも満たされるわけではない。このことはよく知っておく必要があります。
臨床試験と人体実験の違い
臨床試験に参加するということは、患者であると同時に「ボランティア」であることを意味します。他の患者さんになり代わって薬の効果と安全性を自分の体でテストし、医学の発展に貢献する――そうした使命を帯びた医療ボランティアでもあるわけです。
実際、ボランティア精神が浸透したアメリカでは、多くの患者さんが自発的に参加して、大々的に臨床試験が行われています(もっとも国の保険制度が整備されていないアメリカでは、高い医療費を払うか臨床試験にでも参加しないかぎり、効果的ながん治療を受けられないという切実な事情もあるのですが……)。
一方で日本の現状をみると、臨床試験のイロハからして、さっぱり患者さんに知られていないのが実情です。
「なんだかんだ言っても、臨床試験って人体実験じゃないの?」
と、口に出さずとも思っている人は多いはず。
たしかに人体を使ってテストするという点では、臨床試験は人体実験と似ています。しかし! この2つには大きなちがいがあるのです。それは「臨床試験は被験者の意志を尊重し、安全確保に最大限の配慮を払う」が人体実験はそうではない、という点です。
これはどういうことかという���、臨床試験と人体実験の違いは、そこにあるのは、人を人として大切に認めながら治療をするか否か、ということではないでしょうか。

人体実験は、その人の意思を無視し、効果があるかどうかを確かめるためだけに危険な治療を行うこと、だと私は思います。
余談ですが、有吉佐和子さんの小説で『華岡青洲の妻』という作品があります。江戸時代に紀伊に実在した外科医・華岡青洲が、麻酔薬を開発して外科技術を飛躍的に進歩させようと考える。そして近所から野良猫を拾ってきては、動物実験を繰り返すわけです。ところが研究も佳境にさしかかり、人間の体で試してみないことにはにっちもさっちもいかなくなる。すると青洲の妻と母は自分の身を人体実験のために差し出し、妻の失明とひきかえに麻酔薬は完成する、という物語です。
もちろん青洲も妻や母を実験台にするのですから、安全を考えなかったはずはない。でも残念なことに、当時はまだ、今のような科学的な臨床試験の方法がなかったのですね。「人体実験」が「臨床試験」になるまでには、華岡家をはじめとする多くの犠牲があった。その中で科学的なデータと経験が蓄積され、人権と安全に配慮した現代の臨床試験のシステムが確立されたのです。なかでも大きなターニングポイントとなったのが、97年に厚労省が打ち出したGCPの新基準です。これを機に臨床試験の監視体制が厳しくなり、徹底したインフォームド・コンセントが求められるようになりました。
患者の側もそろそろ、臨床試験に対する意識を変えるときが来ているのかもしれません。医師にインフォームド・コンセントを求め、メリットとデメリットをきちんと理解したうえで、臨床試験に参加するかどうかを決める。試験が始まって副作用が出たら、我慢せずに医師にどんどんアピールする。そのこと自体が貴重なデータとなり、必ずや新薬や新しい治療法の確立につながっていくはずです。
新薬や新しい治療法は、患者のボランティア精神なしには確立しません。その意識と誇りを強く持ち、毅然たる態度で臨床試験にのぞむ。そんな患者が増えていくことが、これからの日本の医療を前進させると私は思っています。
同じカテゴリーの最新記事
- 【第三十六時限目】再発への心得 ハンディを持ちながらも、生き生きと生きていくという生き方
- 【第三十五時限目】骨転移 骨折や寝たきりにならないために、骨転移についてもっと知ろう
- 【第三十四時限目】がんの温熱療法 温熱療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十三時限目】がんとセックス 人知れず悩まず、セックスについて真摯に語り合うことが大事
- 【第三十二時限目】免疫療法 免疫細胞療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十一時限目】がんと不妊 がんの治療と妊娠・出産の問題を考える
- 【第三十時限目】がんと迷信 間違いだらけのがん常識。正しい知識と認識を持つことが大切
- 【第二十九時限目】分子標的薬 分子生物学的な理論に基づいて開発された分子標的薬のABC
- 【第二十八時限目】血管新生阻害剤 がんを兵糧攻めにする新薬「血管新生阻害剤」の光と影


