- ホーム >
- 連載 >
- 赤星たみこの「がんの授業」
【第三十四時限目】がんの温熱療法 温熱療法って本当にがんに効果があるの?
“日陰の存在”となった温熱療法
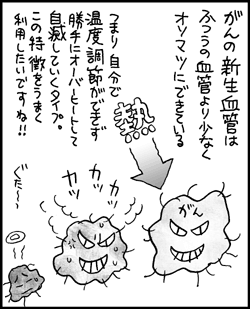
この原理の発見は、古代ギリシアにまでさかのぼります。顔に肉腫ができた人が、一種の感染症である丹毒にかかって高熱を出した後、肉腫がすっかり消えてしまった。こうしたことから、「(がんの一種である)肉腫と発熱には何らかの関係があるらしい」ということは古代から知られていたわけです。
この原理を応用するがん治療法の研究が始まったのは、1970年代半ば頃。がんの3大療法といえば手術・化学療法・放射線治療ですが、温熱療法が開発されると、免疫療法と並ぶ第4、第5の治療法として大きくクローズアップされます。しかし、なかなか思うような成果が上がらないうちに、80年代後半から化学療法や放射線治療が長足の進歩を遂げ、温熱療法はたちまち“日陰の存在”となってしまいます。そんないきさつもあって、一時はホープ視された温熱療法も、今では限られた医療機関で細々と続けられているのが現状です。
しかし一方では、温熱療法の研究開発は目立たないながらも着実に進歩を遂げているのです。
温熱療法には大きく分けて「局所加温法」と「全身加温法」の2つがあります。局所加温法とは文字通り、体外から患部に向けて電磁波などを照射し、局所的に加温する方法です。また食道がんや子宮がん、直腸がんなどのケースでは、口や腟、肛門などから電極針などを入れて加温する方法などもあります。
温熱療法では、とくに体内の深部にあるがんの加温法が難しいとされてきました。超音波や波長の短い電磁波を使っても、体内の脂肪や骨などに熱を吸収されてしまうため、深いところにある患部を温めるのがむずかしかったのです。しかし最近は、日本で開発された高周波(電磁波)を使った『サーモトロン-RF8』という加温装置の技術開発・改良によって、治療技術の水準も着実に進歩しているようです。
余談ですが、がん治療の先進国アメリカでは、温熱療法の研究が日本ほど進んではいないんだそうです。その理由は、「アメリカ人は太っている人が多いから」(!)「皮下脂肪が厚いと熱が体の深部まで伝わらない。だから今の温熱療法では無理」というわけで、一種のあきらめムードがあるというのですね。それを考えると、日本人の体格の小柄さは、あながちマイナスポイントとばかりもいえない。先日ドイツで開催されたサッカーW杯では、日本人選手は体格的に不利だと言われていましたが、温熱療法に関するかぎり、話は別! その意味でも(?)日本は温熱療法の研究開発をリードする存在になれるのでは、と期待してしまいます。
この辺で、もう1つの温熱療法である全身加温法についてもふれておきましょう。現在、一部の医療機関では、全身加温法への取り組みが行われています。全身加温法としては、遠赤外線で体の表面の血液を温め、血液を循環させることで体全体を温める方法などがあります。この場合、患者の苦痛を取り除くため、全身麻酔で行われるのがふつうですが、この方法はがんに効果があるかどうかはまだ不明です。
化学療法や放射線治療との併用で
では実際、温熱療法にはどれほどの効果が期待できるのでしょうか。残念ながら今の技術では、温熱療法だけでがんを死滅させるのはむずかしいのが実情です。そこで、現在は温熱療法をメインの治療法として位置づけるのではなく、化学療法や放射線治療と併用する方法がとられています。温熱療法と化学療法や放射線治療を併用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
温熱療法の最大のメリットとは、加温によってがんを弱らせることで、放射線や抗がん剤の治療効果を高めることができるという点です。それだけでなく、温熱療法には患部を加温することで免疫力をアップさせたり、放射線治療の副作用やがんの痛みを和らげたりする効果もあります。つまり、体の免疫力を上げたり、がんの治療にともなう苦痛を和らげて患者さんのQOLを向上させるというように、“東洋医学的”な効果があることがわかってきたのです。
もちろん、デメリットもないわけではありません。その1つが、過度の加温によるヤケドや痛みです。なんといっても体の内部に高周波や極超短波を当てるわけですから、照射する量や時間をうまく設定しなければ、体温の異常上昇などの問題が生じかねない。医師の側にも熟練した技術が必要であることは、いうまでもありません。
最近では、加温を効果的に行うための新しい温熱療法の研究も進められています。

その1つが、電磁波によって発熱する極微粒子を、がん細胞の表面にある抗原にくっつけることで、がん細胞だけを集中的かつ効果的にやっつける方法です。この方法なら、加温によって患部の周りの組織を傷つけることなく、がん細胞だけをねらい撃ちすることができます。これも分子標的薬と同様、分子生物学の成果を応用したもの。現在の温熱療法が大きく進化を遂げる日も、そう遠くはないかもしれません。
とはいうものの、医療現場では、温熱療法を“民間療法”、“似非(えせ)療法”とみる空気があるのも事実です。しかし、温熱療法は、万能とは言えずとも組み合わせによって効果が高まることはあるでしょうし、まだまだ解明されていない潜在可能性があるように思えてなりません。病状と相談しながら、辛いものを食べて体を内側から温めるもよし、温泉につかって外から温めるもよし。とくに温泉などはリラクゼーション効果も期待できますし、緩和ケアの1つでもあるわけですから、これと化学療法を組み合わせてもいいのではないでしょうか。
自分なりの“温熱療法”で免疫力をアップさせ、暑い夏を乗り切りたいものです。
同じカテゴリーの最新記事
- 【第三十六時限目】再発への心得 ハンディを持ちながらも、生き生きと生きていくという生き方
- 【第三十五時限目】骨転移 骨折や寝たきりにならないために、骨転移についてもっと知ろう
- 【第三十四時限目】がんの温熱療法 温熱療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十三時限目】がんとセックス 人知れず悩まず、セックスについて真摯に語り合うことが大事
- 【第三十二時限目】免疫療法 免疫細胞療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十一時限目】がんと不妊 がんの治療と妊娠・出産の問題を考える
- 【第三十時限目】がんと迷信 間違いだらけのがん常識。正しい知識と認識を持つことが大切
- 【第二十九時限目】分子標的薬 分子生物学的な理論に基づいて開発された分子標的薬のABC
- 【第二十八時限目】血管新生阻害剤 がんを兵糧攻めにする新薬「血管新生阻害剤」の光と影


