- ホーム >
- 連載 >
- 赤星たみこの「がんの授業」
【第三十五時限目】骨転移 骨折や寝たきりにならないために、骨転移についてもっと知ろう
骨粗鬆症と骨転移の相違
がんという病気は「やたらと執念深い」という困った性質がありますが、中でも骨転移は本当に執念深く、術後数年経って安心しているところへ出現することがあります。
前立腺がんや肺がん、甲状腺がんなどのケースでは、骨転移は術後2、3年以内に起こることが多いのですが、乳がんの場合は、術後10年以上たってからでも骨転移を起こすことがあるのです。
ある50代の乳がん患者A子さんは、乳がんの手術をして12年が過ぎた頃、立っていられないほどの腰痛に襲われました。
「太っているから腰に負担がかかったのかしら」と思い、近所の接骨院に通い始めたのですが、痛みは和らぐばかりか悪化する一方。
そこで「更年期による骨粗鬆症かもしれない」と思い、整形外科を受診したところ、MRI検査で骨転移が発覚。「主治医の先生も『手術して10年以上たったからもう大丈夫』と太鼓判を押してくれたのに」と、A子さんは大きなショックを受けたそうです。
一般に、骨転移と骨粗鬆症の症状はよく似ています。
骨粗鬆症は更年期で閉経を迎え、骨量が減ることによって起こります。骨がもろくなって圧迫骨折などを起こすと激痛を感じますが、この痛みは3週間ほどで治まるのがふつうです。ところが骨転移の場合は、痛みは治まるどころかどんどん悪化していきます。骨転移と骨粗鬆症の違いはX線検査ではわかりにくいことも多いので、「怪しいな」と思ったら、MRIや骨シンチグラフィ(以下、骨シンチ)の検査を受けることをお薦めします。
ちなみに骨シンチとは、骨新生のさかんな場所に集まるアイソトープ(放射性同位元素)を含んだ検査薬を注入し、ガンマカメラで撮影する検査法です。検査薬を注入すると、骨の代謝が盛んなところに薬が集まって、その様子が画像に映し出されます。いわば“PETの骨版”ですね
この骨シンチには、「全身の骨転移を一度に調べることができる」というメリットがある反面、「溶骨型の骨転移は骨新生が不活発なのでわかりにくい」というデメリットもあります。したがって、見落としを防ぐには、骨シンチとCTやMRIを組み合わせて検査を行う必要があります。
注目浴びる放射線治療
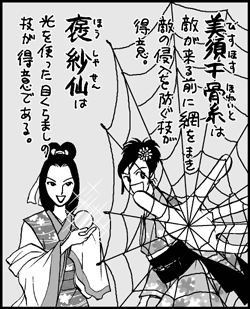
では、骨転移の治療法としてはどのような方法があるのでしょうか。骨転移の治療の最大の目的は、がんをできるだけコントロールしながら、症状を取り除いてQOL(生活の質)の向上を図ること。その主な方法としては、抗がん剤治療やホルモン療法、放射線治療、ビスフォスフォネート製剤による治療などがあります。なかでも近年注目されているのが放射線治療です。なぜなら、放射線治療には骨転移の進行を食い止めるだけでなく、痛みを和らげる効果があるからです。患部に放射線を照射した患者さんの8~9割が「痛みが軽くなった」と感じ、5割の人が「ほとんど痛みを感じなくなる」といわれています。
骨転移の進行を抑制するビスフォスフォネート
さらに、最近になってビスフォスフォネート製剤のゾメタ(一般名ゾレドロン酸)が乳がんの骨転移の治療薬として承認されたことも、患者さ���にとって大きな福音となりました。
しかし、抗がん剤や放射線治療と違って、ビスフォスフォネート製剤が直接がんを殺すわけではありません。
ビスフォスフォネート製剤は骨の表面にくっついて、骨を溶かす破骨細胞の邪魔をし、自滅へ追い込みます。がんを殺すわけではありませんが、骨転移の進行を抑えることができるのです。「進行を抑えるだけ」とはいえ、放射線治療と同様、これによって痛みや骨折なども抑えられ、患者さんにとって大変いい効果が上がっています。
次に、骨転移が起こるとなぜ骨が破壊されるのかを考えてみましょう。
がん細胞が骨に転移すると、タンパクを分泌します。このタンパクが破骨細胞を活性化させます。よって、破骨細胞がせっせと骨を溶かし始めるという二段構えで骨が破壊されていくのです。
また破骨細胞のほうも、がんの増殖をうながす物質を放出し、もともとのがんをどんどん勢いづかせていきます。つまり、がん細胞と破骨細胞は互いに結託して悪事を働く“悪の同盟”を結んでいるのです。
「破骨細胞よお、オレが先に行ってシマを荒らしておくから、そこへ来い」「ガッテンだ、がん細胞の兄貴! 後からオレが行って金品を巻き上げて、それを兄貴に送りますぜ」「おう、頼むぜ」という具合ですね。この悪の循環はどこかで断ち切らなきゃいけない! その役目を担うのが、破骨細胞をやっつけるビスフォスフォネート製剤なのです。

その1つであるゾメタ4ミリグラムを溶骨性骨転移の患者さんに3~4週間ごとに投与すると、骨折や高カルシウム血症、脊髄圧迫骨折などが有意に減り、その発生する時期を遅らせるといわれています。この製剤の登場によって、日本の骨転移の治療は大きく前進したといえるでしょう。
治療効果を確実に上げるためには、予防に力を入れることも重要ですが、残念ながら、ゾメタを使った予防的治療に対する保険適用はまだ認められていいのが現実です。
しかし――明るい見通しもないわけではない。現に、今年6月に開催された米国臨床腫瘍学会(ASCO)では、乳がん治療における骨のケアの重要性が大きく採り上げられています。ボーンヘルス(骨の健康)への意識が高まるにつれて、今後は骨転移と闘う方法もますます充実してくるでしょう。
骨折して寝たきりになるよりも、早目に発見して早目に治療! 自分の体と対話しながらQOLを高める努力を続けることが、何より大事だと思うのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 【第三十六時限目】再発への心得 ハンディを持ちながらも、生き生きと生きていくという生き方
- 【第三十五時限目】骨転移 骨折や寝たきりにならないために、骨転移についてもっと知ろう
- 【第三十四時限目】がんの温熱療法 温熱療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十三時限目】がんとセックス 人知れず悩まず、セックスについて真摯に語り合うことが大事
- 【第三十二時限目】免疫療法 免疫細胞療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十一時限目】がんと不妊 がんの治療と妊娠・出産の問題を考える
- 【第三十時限目】がんと迷信 間違いだらけのがん常識。正しい知識と認識を持つことが大切
- 【第二十九時限目】分子標的薬 分子生物学的な理論に基づいて開発された分子標的薬のABC
- 【第二十八時限目】血管新生阻害剤 がんを兵糧攻めにする新薬「血管新生阻害剤」の光と影


