- ホーム >
- 連載 >
- 赤星たみこの「がんの授業」
【第三十七時限目】医師の選び方 患者さん本人の生き方・考え方を尊重してくれる医師を探せ!!
労をいとわず、何人かの医師と積極的に話をする
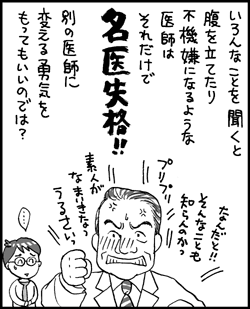
編集部 そうですねえ……その辺は、ちょっと判断がしにくいですけれども。多くのメディアから流される情報には間違った情報も多いので、それらを鵜呑みにせず、自分で判断する眼力をつける必要があるでしょうね。
赤星 これは私の考えですが、名医に出会うためには、労をいとわず何人かの医師と話をするべきだと思うんです。今はセカンドオピニオンという考え方が普及しているから、主治医以外の先生にも積極的に意見を求めたほうがいい。とはいうものの、地方だと「選択肢が少ない」ということもあるでしょうから、その場合は同じ病院の中で、あえて別の先生に診てもらうのも手だと思うんです。いつもと違う曜日に出かければ、別の先生に診てもらえる可能性もありますからね。いずれにしても「複数の先生に診てもらう」というのは最低限必要だと思います。いろいろな先生の話を聞いた結果、納得して最初の先生に戻るということもあるでしょうし。
編集部 大事なポイントですね。
赤星 それから、「患者に対する思いやりがある医師かどうか」も大事だと思うんです。口は悪いけど手術はものすごくうまい、という人も中にはいるかもしれない。でも、直感的に「この先生はイヤだな」と思ったら変わるべきでしょうね。
編集部 医師との「相性」もありますからね。がんというのは「切れば終わり」ではなく、術後のおつきあいも長い。医師との間に信頼関係があれば、患者さんのほうでも生きる力が沸いて回復も早くなる、ということもあると思うんです。
赤星 「腕のよさ」だけに注目して医師を選ぶことが、必ずしもいい結果をもたらすとはかぎらない。
編集部 がんと他の病気との大きな違いは、「生き方と関わってくる病気」だということです。一律に「この治療法がいいんだ」と患者さんに押しつけるのではなく、患者さん本人の生き方や考え方を尊重してくれる医師でないと難しい――そんな側面があるように思います。
赤星 ある大学病院で毎年検診を受けてきた友人に、今年初めて乳がんが見つかったんです。その主治医の先生がとにかく乳房温存に否定的で、「全摘がいい」の一辺倒なんです。友人はすっかり「全摘じゃないとダメなんだ」と思い込んで、結局全摘手術を受けてしまったんですね。あれは医師が患者の生き方、考え方をコントロールした典型的な例だと思う。とはいっても、患者の生き方や考え方に耳を傾けてくれるような先生は忙しいでしょうし……難しいところですね。
編集部 それは忙しいとか忙しくないとかいうこととは無関係だと思います。多忙を極めていても、1人ひとりの患者の気持ちに寄り添って、きちんと対処してくれる先生もいるわけですから。「4つの選択肢の中から選べ」と患者さんに投げつけるのではなく、患者さんの生き方につながるベストの治療法を、医師と患者さんが一緒になって考えていく――そうなっていかないと、本当にいい治療というのはできないと思うのです。
赤星 とはいうものの、日本では「がんの専門家が少ない」現状が大きなネックになっている。だからこそ、外科や放射線科、内科など複数の専門の医師がチームを作って治療に当たるべきだと思います。
また患者の側でも声を上げて、「そういう治療をしてくれないと困る」と訴えていく必要がありますよね。
すべての病院がチーム医療を導入するべきです
編集部 アメリカではチーム医療が発達していて、「自分の不得手は他の専門家に任せる」という意識が行き渡っています。中でも理想的なチーム医療を実践しているのが、テキサス大学の『MDアンダーソンがんセンター』。ここでは外科医・放射線治療医・腫瘍内科医がチームを組み、カンファレンスでベストの治療法を議論しながら患者さんに提示し、患者さんの希望に合った治療を選んでもらうやり方をとっています。専門家チームと患者さんが一緒に考えながら治療法を決定する、というシステムが確立しているわけですね。最近は日本でも、聖路加国際病院や埼玉医大などのように、チーム医療を積極的に採り入れる医療機関が出てきています。
赤星 がん患者さんにとってベストの治療を医療者側がコーディネートする。その意味では、すべての病院がチーム医療を導入するべきですよね。
編集部 ただ、それを実現するにはネックがある。日本の医学界はタテ割りの医局制度や講座制度に支配され、横の連携がまったくないわけです。たとえば東大病院の外科と内科は犬猿の仲だし、同じ病院でも第1外科と第2外科ではまったく違った治療をする、ということがあるわけですよ。
みんなの力で社会の制度を変え、医療改革は果たそう
赤星 そこは厳しく弾劾しないといけませんね。1人の名医を探すのは、浜の真砂から1粒の砂金を探すようなものだけれど、病院全体が変わってくれれば、砂浜ごと金に変わるわけですから。クチコミやインターネットを最大限活用しながら、医療改革に向けて患者自身も声を上げていかないと。
編集部 病院の取り組み方も、院長や理事長の考え方1つでずいぶん変わるんです。この前までダメだった病院が、トップが変わったのをきっかけに改革が行われ、大勢の患者さんが集まるようになったという例もある。その意味では、患者の側が病院に働きかけて改革を後押しするということも、これからは非常に重要になってくると思います。
赤星 そのためにも、患者さん1人ひとりが声を上げてくれると助かるんですが……。結局、社会の制度を変えるために一番有効なのは「署名」なんですって。「これだけの有権者が署名している」という事実を政治家に突きつけることが、一番効果的なんだそうです。その前段階として、ぜひ患者の皆さんはマスコミに投書して欲しい。今はどこの新聞社やテレビ局でも、メールやファクス、手紙で「番組へのご意見」を受け付けていますから。
編集部 数年前にジェムザールという新薬が登場したときのことです。それまですい臓がんの治療は難しかったのですが、ジェムザールを使うことで、何年も生き延びられる方が出るようになった。ところが日本ではなかなか承認されないので患者会が署名活動を展開し、結果として早期承認につながった。世論の力が政治を変えるのに大きな力を発揮したわけです。
赤星 「署名ってどのぐらい効果があるんだろう」と前から疑問だったんですが、本当に世の中を変えるほどの力があるんですね。チーム医療や医療改革を進めるために、我々はこれからもマスコミ業界でサポートしていくつもりです。患者さんや家族の方々も、まずはマスコミへの投書から始めていただきたい。皆で力を合わせて、日本のがん医療を変えていこうじゃありませんか。
編集部 大勢の力を結集すれば、少しずつでも着実に日本の医療を変えていける。そう信じて努力していきたいと思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 【第三十六時限目】再発への心得 ハンディを持ちながらも、生き生きと生きていくという生き方
- 【第三十五時限目】骨転移 骨折や寝たきりにならないために、骨転移についてもっと知ろう
- 【第三十四時限目】がんの温熱療法 温熱療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十三時限目】がんとセックス 人知れず悩まず、セックスについて真摯に語り合うことが大事
- 【第三十二時限目】免疫療法 免疫細胞療法って本当にがんに効果があるの?
- 【第三十一時限目】がんと不妊 がんの治療と妊娠・出産の問題を考える
- 【第三十時限目】がんと迷信 間違いだらけのがん常識。正しい知識と認識を持つことが大切
- 【第二十九時限目】分子標的薬 分子生物学的な理論に基づいて開発された分子標的薬のABC
- 【第二十八時限目】血管新生阻害剤 がんを兵糧攻めにする新薬「血管新生阻害剤」の光と影


