- ホーム >
- 連載 >
- 吉田寿哉のリレーフォーライフ対談
治療困難な「難治性白血病」の子どもたちが3割以上もいる 行政には医療制度のしっかりした骨格を、血肉の部分は「みんな」で育てる
「私はラッキーなほど人には恵まれています」
水谷 「日本白血病研究基金」の正式発足が平成4年ですから今年で14年ですか。ようやく軌道に乗ってきたという段階ですね。もっとも私の場合は、多くの素晴らしい人たちとの出会いに恵まれたことにつきると思います。
吉田 そのあたりを具体的に話していただけますか。
水谷 まず基金づくりを模索している段階で、ご子息を白血病で亡くし、その息子さんの名前で同じような基金をつくりたいと考えているご夫婦に出会うことができました。その方たちと協力し合うことで、基金がスタートしています。またその方たちが「白血病研究基金を育てる会」(飯田真作会長)を立ち上げ、側面から強力に応援しています。基金の事務局は銀行にやってもらっていますが、これはとても優れたシステムで、寄付も集めてくれます。
吉田 銀行が寄付を募ってくれるんですか。知りませんでした。初耳です。
水谷 遺言信託というのがありましてね。資産家の中には、遺産の一部を社会的な事業を行っている団体に寄付したいという人がいるんです。銀行がそうした篤志家に推薦できる団体のリストを提示して、遺産を残してもらう対象を選択してもらうんです。私たちの基金でいえば、2億円もの遺産を寄付してくれた方がありました。これは基金の基盤づくりという点で大きく役立たせてもらっています。
吉田 なるほど……。人との出会いという点でいえば、世界的指揮者の小沢征爾さんやバイオリニストの五嶋みどりさんが、先生がご勤務なさっている東京医科歯科大学病院でコンサートを開かれているし、前回、この対談にご登場いただいた音楽プロデューサーの大橋さんも基金のためにコンサートを催したりCDを制作していますね。
水谷 そうですね。小沢さんの場合は「がんのこどもを守る会」から話があってコンサートが実現しました。小沢さんのコンサートでは、小沢さんがまだ学生だった頃に結成された合唱団を引き連れてこられましてね。あの歌声は素晴らしかった……。大橋さんは五嶋さんのコンサートがきっかけで、最初、院内コンサートをやってもらったところ、意気投合して基金の話をしてみると、そちらでも協力したいといってくださって……。
現在では、基金の活動を広報する「白血病研究基金を育てる会」の音楽部門を担当してくださっているんです。五嶋みどりさんにもたいへんなご協力をいただいています。基金のためのコンサートも開いていただいたり……。こうして考えると、私は本当に人に恵まれていますね。とてもラッキーだったと思います。
課題山積みで沈没寸前の小児医療
吉田 話題を変えて、小児医療についてお聞きしたいのですが……。最近、話題になっている『元気にな~れ、こどもたち』という本では、現在の日本の小児医療がタイタニック号になぞらえられています。もはや沈没寸前ということですね。
水谷 まさにそのとおりです。最近では小児科医が慢性的に不足しており、どこの病院でも小児科は医師、看護師とも過酷な状態が続いています。とくに夜間の緊急診療を受け付けている病院では、若い医師たちがほとんど休みもとれずに仕事を続けている状態です。膨大な仕事量がストレスになってのしかかり、うつ病に陥る医師も少なくないんです。そんななかで小児科医の高齢化もどんどん進行しています。これではとてもいい医療は望めません。
吉田 とくに最近は少子化の影響で、親は子どもを大切に大切に育てようとする。そのため、些細なことでも、病院を訪ねて診察を受けたがる。それで先生方の仕事が増えてしまっていることもあるんでしょうね。
それに親の中には、この時間帯のほうが患者が少なく、早く診療を受けられるからと、わざわざ夜間に病院を訪ねる方もいます。その点では、私も含めて、子どもを持つ親たちも反省しなければなりませんね。ただ昔なら、祖父や祖母が適切なアドバイスをしてくれていたのが、現在では、家庭に子育ての経験を持つ者がいないこともあるんです。そのため、子どもの様子がおかしくなると、どうしていいかわからず、やみくもに病院を訪ねてしまうのですね。
水谷 たしかにそれはあるでしょうね。両親にすれば不安を感じるのは自然な人情でしょうからね。
吉田 しかし、それにしても先生のおっしゃる状況は深刻ですね。どうしてそんなに小児科医が少なくなってしまったのでしょう。小児科医を志望する若い医師も決して少なくはないと思うのですが……。
やはり診療報酬制度を見直さざるを得ない……
水谷 つまるところ、病院にも市場原理が持ち込まれ始めたことが最大の原因でしょうね。国を挙げての医療費削減で、公的病院ですら診療科ごとにシビアに経営効率が問われ始めていますからね。経営という見地から考えると、小児科ほど効率の悪い診療科はありません。患者が子どもたちですから、注射1本打つにも時間や手間が大人の倍以上かかる。そうした経営効率の悪さから、人員配置も後回しということになりがちで、医師や看護師には過酷な仕事が求められることになるんです。休みもとれず、仕事に明け暮れている小児科医の姿を見ると、若い人たちはやはり、小児科を選択することに二の足を踏んでしまうんでしょうね。
友人の大学の話ですが、学生に聞くと毎年20人くらいは小児科を希望するんだそうです。それが1年間の研修で各科目を回っているうちに半分になり、その後、じっさいに小児科で研修を受けている間に、さらに希望者が減少します。最終的に小児科を希望してくれるのは2、3人もいればいいところだと嘆いています。それに最近では、いったんは小児科を選択しても、仕事の過酷さから別の科目に移動する人も目立っています。
吉田 そうなると、残された人たちの状況はさらに厳しくなってしまいますね。そうした人たちは使命感を支えに何とか持ちこたえているのかもしれませんね。でも、それにも限界がありますからね。何かいい方策はないものでしょうか。
水谷 やはり診療報酬制度を見直さざるを得ないでしょうね。現行の制度では、小児科医の仕事の多くは病院収入に反映されていませんからね。それに現在は子どもの医療費は原則として無料です。
それはそれでいいのですが、いったんは窓口で診療費を支払うようにすべきだという意見もありますね。支払わない制度では医療にお金がかかるという実感がわかない。支払うとなると受診の仕方も変わってくる、というのです。少ない国民医療費や限られたマンパワーなどの医療資源の賢い利用という面で一理ありますね。
吉田 以前、アメリカの医師と話していて、アメリカの病院では、たとえば看護師のなかにもナース・オンコロジストというがん治療のスペシャリストがいる。そして、自分が留守をするときには、その人に治療を任せることができると聞いたことがあります。日本でもそうしたチーム医療制度を整備すれば、医師の負担は軽減されるのではないですか。
水谷 たしかにそのとおりですね。これは小児科に限りませんが、日本の病院では医師、看護師がすべての仕事を引き受けざるを得ない状況で、それが医師や看護師の消耗にもつながっています。院内の仕事には直接、医療には関連しないものも多いし、そのなかには他の分野の専門家に任せたほうがいいものも少なくありません。そうした点でもこれからは医療の周辺を補う専門的なパラメディカルスタッフの導入を積極的に考えるべきでしょうね。
自分たちの医療は自分たちで育てる
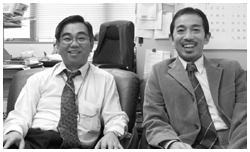
吉田 白血病に関して、また私自身の経験を話させていただくと、入院中には死を意識して不安でたまらない時期がありました。大人の私でこうなのだから、子どもたちの苦しさには想像を絶するものがあるのではないでしょうか。にもかかわらず医師や看護師はいつも忙しく働いていて、不安や悩みを打ち明けられないでいるようにも思います。そんな子どもたちの心をときほぐすスタッフも必要なように思いますが……。
水谷 おっしゃるとおりですね。欧米ではそのために病院内での子どもの生活全般を子どもの立場でサポートするチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)が働いています。
しかし、日本ではなかなかこうした専門スタッフの必要性が認識してもらえない。CLSが全国でやっと10人になった程度でしょうか。資格制度そのものも存在しないので、その道を志す人はアメリカで勉強して資格を取得しなければならないのが実情です。
吉田 その点でも、日本の医療は立ち遅れているといわざるを得ないのでしょうね。最近になって小児科医療の充実、強化が政策面でもとりあげられるようになっていますが、行政を頼りにしていては、なかなか埒が明かないのではないでしょうか。
水谷 そのとおりですね。その意味で、一般の人たちに医療について、もっと考えていただきたいと願っているんです。行政には医療制度の骨格部分をしっかりつくってもらう。血肉にあたる部分は一般の人たちが自分たちで育てていこうという意識を持っていただければ、医療のあり方は大きく変わってくると思うんです。制度だけではどうしても不十分なところが出てきます。そこは税金だけに頼るのでなく一般の人たちが資金を集めて、理想とする医療を自分たちで育てていこうということです。私は医師や看護師の育成にも同じことがあてはまると思っています。私自身がそうであったように、“民”の力で医療従事者に再教育の機会を与えることが大切です。それが結果的には、患者さんにとっても大きなプラスになるのです。
吉田 そうなると医師の意識も変わってくるでしょうね。
水谷 そのとおりです。私自身、イギリスの白血病研究基金に育ててもらったことは、生涯、忘れることはないでしょう。民間の資金によって育ててもらうことで、医師は自然に患者さんに視線を向けるようになるでしょう。それが医師と患者さんの良好な関係にもつながっていくに違いありません。
吉田 医師をはじめとする医療従事者と一般の人たちが、ともに手を携えることで、新たな医療が実現するということですね。そのことを考えると、先生が立ち上げられた「日本白血病研究基金」はとても大きな意味を持ったモニュメントということもできそうですね。
水谷 そうなることを願っています。そのために、民間の基金に資金を集めやすくする税制面での工夫も絶対に必要ですね。これからも多くの人たちと協力し合って、このような基金を発展させていきたいですね。
(構成/常蔭純一)
同じカテゴリーの最新記事
- がん医療の弱点を補完するアンチ・エイジング医療 病気を治す医療から健康を守る医療へ
- 医療の第一歩は患者さんから話を聞くことから始まる
- 治療困難な「難治性白血病」の子どもたちが3割以上もいる 行政には医療制度のしっかりした骨格を、血肉の部分は「みんな」で育てる
- 本邦初のチャリティレーベルに10人のプロミュージシャンが参集 音楽、アートを通して白血病患者支援の輪を拡げたい
- 何よりも治療のタイミングが大切。治療成績向上の秘訣はそこにある 血液がん治療に新たな可能性を開く臍帯血移植
- がん患者、家族1800人を対象にした大規模調査から問題点をアピール 患者の声を医療政策に反映させようと立ち上がった
- 人の痛みや苦しみを体感した彼女が、自ら生み出した“LIVE FOR LIFE” 同じ境遇の人たちに勇気と希望のエールを。美奈子はそれをライフワークに選んだ
- ポイントは、ナース。ナースが意思決定に加われば医療の質も、患者満足度も上がる がん医療全体の質を上げるために、骨身を惜しまず取り組む
- 「なぜベストな治療にまっすぐたどり着けないのか」という疑問から出発した医療改革の道 日本の医療を良くするには、アメリカの医療の良い面を取り入れるのが早道


