- ホーム >
- 連載 >
- 吉田寿哉のリレーフォーライフ対談
何よりも治療のタイミングが大切。治療成績向上の秘訣はそこにある 血液がん治療に新たな可能性を開く臍帯血移植
HLA、DNAの差異は治療成績に関係しない
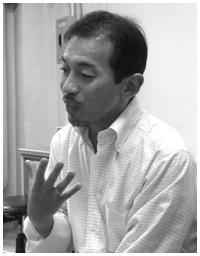
吉田 なるほど。それだけ臍帯血移植を有力な治療法として捉えておられるわけですね。臍帯血とは、胎児のへその緒(臍帯)の血液で、この中に豊富に含まれる造血幹細胞を移植に利用する方法です。しかし、この移植方法にもいろんなネックがあるのでしょう。今、話に出ていたHLAの適合ということもありますし、また、血中の細胞数という問題もありますね。
井関 まずHLAということからいうと、現実的には臍帯血でHLAが完全に適合するケースはほとんどないといっていいでしょう。吉田さんの場合もそうでしたが、20万人以上が登録している骨髄バンクでも、HLAがうまく合致するドナーはなかなか見つかりません。臍帯血バンクの登録者は最近になって急増しているとはいえ、現段階では2万本を上回っている程度です。おいそれとはピッタリのドナーは見つからない。
そこで私たちは次善の策として血清型でHLAが6分の5あるいは6分の4合致しているドナーが見つかれば、移植を実施しています。じっさいにはHLAには血清型だけでなくDNAタイプなど、さらに多くの差異があります。しかし、そうした差異は今のところ、治療成績には関係していません。細胞数の多寡も同じですね。
吉田 そうなんですか。細胞数が多いほどいいというのが移植医療の常識だと思っていたのですが……。
井関 細胞数が多いほどいいといわれていたのは、昔は小児が移植の対象になることが多かったからですね。
子どもの場合、体重あたりの移植細胞数の差がとても大きくなるので……。それが現在では細胞数が少ない大人に移植の対象が広がっていて、小児に比べて移植細胞数の差は格段に小さいのです。それに加えて、日本の場合はバンクによる臍帯血の品質の差がきわめて小さいことも、細胞数をそれほど重視する必要がないひとつの要因にあげられますね。
吉田 と、おっしゃいますと……。
HLAの完全合致や細胞数にこだわる必要はない
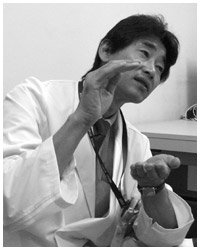
井関 以前はともかく、今は各臍帯血バンク間で細胞処理方法や細胞数などの検査方法の統一がかなり進んでいます。そのなかで、大人でも多くの場合、体重あたり2から3×10の7乗、体重の軽い人で、せいぜい4×10の7乗までの臍帯血が見つかります。細胞数は多いにこしたことはありませんが、この範囲内では、移植細胞数の差は、まず問題ないということです。
じっさい私たちのこれまでの経験でいっても、HLAの差異や細胞数の多寡は、生着率、急性GVHD(移植片対宿主病)の発症率、短期間での死亡数や再発率、さらに長期生存率にはまったく関係していないことがわかっています。それより小児白血病の場合などはHLAがフルマッチしているケースが移植後の再発率がもっとも高いというデータもあるほどです。
とはいえ、これも振り返ってみるとそうだったということで、なぜそうなるのか確たる根拠があるわけではありません。
吉田 なるほど。臍帯血移植に関してはHLA数にこだわる必要はないわけですね。目から鱗がとれる思いです。
世界のトップ水準を行く日本の移植医療
吉田 話が変わりますが、2年前、私が井関さんから治療を受けたときに聞いた話では、日本の臍帯血移植医療の水準は世界でもトップレベルにあるということでした。この状況は今も変わっていませんか。
井関 そうですね。今もトップレベルにあると考えていいでしょう。スペインからも、比較的良い成績が報告されています。
吉田 なるほど。治療成績はどうなのでしょう。治療を受けるときに日本で臍帯血移植を受けた患者さんの5年生存率のグラフを見せていただいて、正直にいって愕然としたことを覚えていますが……。こうした数値は向上していると考えていいのでしょうか。
井関 ジワジワとですが確実に向上していると思います。ただ現時点での5年生存率となるとどうでしょうか。今から5年前というと2001年ですからね。当時はそれこそギリギリの状況にある患者さんがこの治療を受けていた。当然、生存率でもそういい数字は残らない。 しかし、最近になって、状態のいい人が移植治療を受けるようになっていますからね。これからは生存率もどんどんよくなっていくと思います。私自身2、3年後にどんな数字が出てくるか、楽しみにしているんです。
吉田 医科研の成績はどんなものか、教えていただけますか。
井関 移植の成績が良いと予想される、いわゆる標準リスクでの移植では、長期生存率は9割程度で、これはHLAが一致した血縁者ドナーからの成績と同様ですが、リスクの高い移植では、主に再発のために成績は低下します。
移植で大切なのは治療のタイミング
吉田 技術的にはどうなのでしょう。たとえば欧米と比べて日本の移植技術はどこが違っているのでしょうか。
井関 もちろん免役抑制やGVHDの予防など日本の移植医療では欧米とは異なる面が少なくありません。しかし、それらがどの程度治療成績に反映しているのかは率直にいってわかりません。じっさいこれは臍帯血移植に限りませんが、骨髄移植に関していえば、それほどすごい技術があるわけではないんですね。外科手術のように手先の器用さが問われるものでもありませんしね。私はそれよりも移植治療で大切なのはタイミングだと思っているんです。
吉田 タイミングとは、どういうことをいうのでしょうか。
井関 わかりやすくいうと患者さんの体調がもっとも好ましいときに移植を実施するということです。当たり前のことのように思われるかもしれませんが、これが現実にはなかなか難しい……。
吉田 具体的にいうと……。
井関 これは臍帯血移植に限りませんが、一般に移植治療は白血病の再発後に行われますね。そのときの状況を考えてみてください。病気が再発して、移植しか有効な治療は残されていない。しかし多くの場合は骨髄バンクでもなかなかその患者さんにふさわしいドナーはなかなか見つかりません。
そこでギリギリの段階まで抗がん剤などで症状を抑えることになる。その結果、臓器の機能低下など患者さんの体調はどんどん悪化していくことになる。場合によっては水面下ですでに新たな再発が起こっているケースもある。そんな状態で移植をしてもなかなかいい結果は出ないでしょう。もちろん患者さんにとっても治療がよりつらくなる。私から見れば、移植に踏み切るタイミングが遅すぎるんですね。
吉田 そうですね。私自身の経験でも、率直にいって移植治療は楽なものではありませんでしたからね。
同じカテゴリーの最新記事
- がん医療の弱点を補完するアンチ・エイジング医療 病気を治す医療から健康を守る医療へ
- 医療の第一歩は患者さんから話を聞くことから始まる
- 治療困難な「難治性白血病」の子どもたちが3割以上もいる 行政には医療制度のしっかりした骨格を、血肉の部分は「みんな」で育てる
- 本邦初のチャリティレーベルに10人のプロミュージシャンが参集 音楽、アートを通して白血病患者支援の輪を拡げたい
- 何よりも治療のタイミングが大切。治療成績向上の秘訣はそこにある 血液がん治療に新たな可能性を開く臍帯血移植
- がん患者、家族1800人を対象にした大規模調査から問題点をアピール 患者の声を医療政策に反映させようと立ち上がった
- 人の痛みや苦しみを体感した彼女が、自ら生み出した“LIVE FOR LIFE” 同じ境遇の人たちに勇気と希望のエールを。美奈子はそれをライフワークに選んだ
- ポイントは、ナース。ナースが意思決定に加われば医療の質も、患者満足度も上がる がん医療全体の質を上げるために、骨身を惜しまず取り組む
- 「なぜベストな治療にまっすぐたどり着けないのか」という疑問から出発した医療改革の道 日本の医療を良くするには、アメリカの医療の良い面を取り入れるのが早道


