- ホーム >
- 連載 >
- 吉田寿哉のリレーフォーライフ対談
がん患者、家族1800人を対象にした大規模調査から問題点をアピール 患者の声を医療政策に反映させようと立ち上がった
がん患者の7割ががん対策に不満
医療に反映されているとお考えですか]
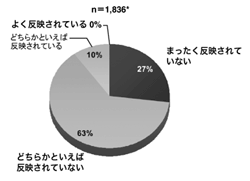
[(問)総合的にみて、
日本のがん医療の水準に満足していますか]
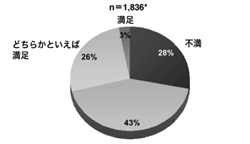
[(問)がん医療に関する情報を
統合して提供する機関は必要ですか]
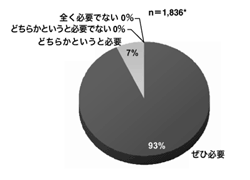
吉田 最近になって、たとえばがん対策基本法が成立するなど、がん医療をめぐる政策は基本的にはいい方向に向かっていると思います。そのなかでジェームスさんがとても重要な役割を果たしておられますね。
2005年に、ジェームスさんが東京大学助教授として発表されたがん患者、家族1800人を対象にしたアンケート調査の結果でも患者が現在のがん医療政策に強い不満を持っていることが判明しています。
がん患者の7割が現状のがん対策に不満を持っており、8割ががん政策に患者の声が反映していないと考え、さらに10割ががん医療情報機関が必要だと回答するなど、患者の要望と現実の落差がくっきりと浮かび上がっています。キチッとしたデータをもとに社会に訴えるジェームスさんならではの手法だと感心しました。
近藤 あのアンケートを通じてデータで示されたことは、患者さんにとっては、ずっと以前からの常識だったことです。しかし、それが霞ヶ関や永田町の人たちの常識かというと、そうではない。彼らに関心を持ってもらうには、患者の声を具体的に数量化する必要があるのです。
現在では日本人の3分の1ががんで亡くなっており、有権者の大半が、この問題に強い関心を持っている。あえて率直の言い方をさせて頂くと、政治家にとっては、がん対策は選挙での集票に直結する問題であるわけです。��のことを広く理解してもらい、問題の所在を明確にするために、あのアンケートには重要な意味がありました。
私自身にとっても、患者会などでストックされていた患者さんたちの声を集約することで、社会を動かすことができたことは、新鮮な驚きでした。
吉田 がん体験者の1人として私自身もとても嬉しく思いました。ひとつ付け加えると、東京大学というブランドをうまく活用されているという印象も持ちました。
近藤 そういって頂けると、大学としてはありがたいですね。私は以前から日本の大学は権威の中に閉じこもりすぎていると考えていましたから……。
大学には本来、大きく3つの機能があります。第1が研究、第2が教育、そして第3の機能として社会とのかかわりがあげられる。大学というのは、社会はどうあるべきか、という青臭い事柄についてまじめに取り組める数少ない機関です。ところが、そうした研究で成果が残せても、それが学内でとどまり続けている。これはもったいない話です。じっさい海外の大学には市民活動の拠点としての機能も持っているところが少なくありません。
これからはそうした大学の機能も存分に発揮していきたいですね。とくに医療のように政治と深く結びつき、一般の人たちには実態が分かりにくい分野では、大学の果たすべき役割はとくに重要でしょうね。
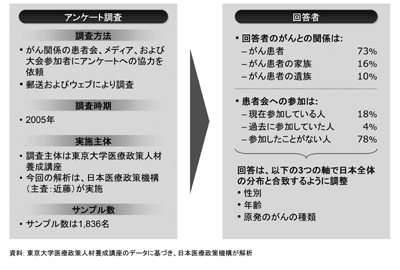
医療を変えるには医師が声を上げることも必要
どのように思われますか。]
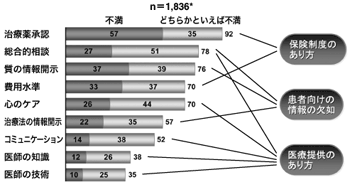
[(問)これまでの診療経験から総合的にみて、患者・家族にとって
どのような情報が必要だ(不足している)と思いますか]
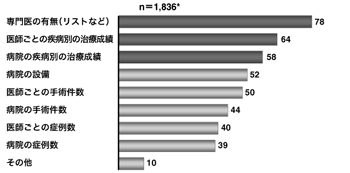
[(問)がん患者の声を政策に反映させるために、がん患者がより
積極的に行うべきことは何だとお考えですか]
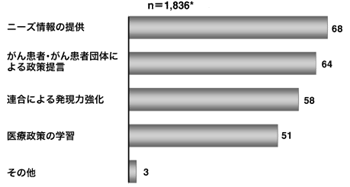
吉田 なるほど。ちょっと話は横道にそれますが、今、おっしゃった大学の役割で第2にあげられていた教育ということも、社会とのかかわりという点ではとても重要なように思います。人材育成についてはどのように取り組んでおられるのですか。
近藤 人材育成については2つの側面から取り組んでいます。まずひとつは、東京大学医療政策人材育成講座の設置です。これは社会人を対象にしたもので、患者支援者、医療提供者、医療ジャーナリスト、そして医療政策者という異なるジャンルの人たちに、「医療を動かす」というテーマで政策提言に取り組んでもらっています。医療提供者に対しては患者支援者、医療政策者に対しては医療ジャーナリストと、対立軸にある人がチェック機能を果たしているので、現実的でバランスのとれた政策提言が生まれてきています。
講座の参加者は約60名。 平均年齢は40歳くらいで、たとえば医療ジャーナリストの場合は大新聞で医療コラムを担当しているといったぐあいに、各分野とも第一線で活躍している人たちです。講座が5年間続けば300名の卒業生が誕生し、力強いコミュニティが形成されるでしょう。それは医療を変えていくうえでのひとつの力となり得ると思っています。
もうひとつは、医学生を対象にした取り組みです。医学生は5年次から病院などでの医療実習がカリキュラムに組み込まれますが、2年前からそこに医療政策立案というプログラムを盛り組みました。医療を変えていくには医師、とくに全体の6、7割を占める勤務医が声を上げることも大切ですからね。
現行の医学部の講座には、実践的な医療政策に関する講座は皆無というべき状況です。たとえば医師の収入源となる診療報酬についても、誰がどのように決定しているのか、まったく教えられていない。日本の勤務医は過酷な条件で、驚くほどの仕事をこなし続けています。制度の不備を個人的な努力でカバーしているわけです。
しかし、だからこそもっと積極的に声を上げる必要があるんです。そのことが社会にも認識され始めているのでしょう。この医学生向けのプログラムには、現在では、東京大学だけでなく、慶応大学、東京医科歯科大学、千葉大学などの医学生も参加しています。
吉田 私も1人の元患者として勤務医が置かれている状況の過酷さは十分に理解しています。しかし、それが患者との乖離にもつながっているようにも思えます。ジェームスさんのアンケート調査でも、がん患者が問題とする事柄に治療薬の承認問題に続いて、相互の相談や心のケアの欠如が指摘されています。これは医師が忙しすぎて、本当は患者とじっくり話し合いたいのに、その余裕をもてないでいる状況を物語っているように思えます。
矛盾している診療報酬設定
近藤 最近になって医療費を決定する中医協という委員会に、患者でもある連合代表の勝村久司さんが参加されている。その勝村さんが標榜されているのが、医療費の設定への患者の価値の反映ということです。
医療費の設定に患者の視点がまったく加味されていない、患者が価値を感じる医療には高い価格を設定し、そうでない医療は低い価格でいいじゃないかというのが勝村さんの持論です。じっさい、そのとおりで患者が求めている心のケアや社会的な問題も含めたアドバイスには、まったく価格がつけられていない。
逆に患者からすればわけのわからない指導や検査には膨大な診療点数が付与されている。その結果、患者がそうしたわけのわからないところをグルグルと回されていることが少なくない。
医師の中にはこうした状況を何とかしたいと考えている人も少なくないと思います。しかし、いかんせん忙しすぎて余裕がない。また、患者の望むことをやっていると儲からないことが多い。結局は制度を変えるしかないんですが、医師はストイックというのでしょうか、政治に参加するよりは自己犠牲を選ぶ傾向が強いんですね。
現実を考えると日本のように診療報酬が一本化されていて、それが政治決定される状況では、医療を変えるには政治に参加せざるを得ないんですが……。
もちろん同じことは患者さんにもあてはまります。医師だけでなく患者さん自身も、自分たちの意思を的確に社会に伝えていかねばなりません。
そこでアンケートの話に戻るんですが、これからはさらに内容を掘り下げて、患者さん自身がどんな医療にどの程度の価値を感じているかということも、はっきり抽出して、社会に訴えていく必要があるでしょうね。
同じカテゴリーの最新記事
- がん医療の弱点を補完するアンチ・エイジング医療 病気を治す医療から健康を守る医療へ
- 医療の第一歩は患者さんから話を聞くことから始まる
- 治療困難な「難治性白血病」の子どもたちが3割以上もいる 行政には医療制度のしっかりした骨格を、血肉の部分は「みんな」で育てる
- 本邦初のチャリティレーベルに10人のプロミュージシャンが参集 音楽、アートを通して白血病患者支援の輪を拡げたい
- 何よりも治療のタイミングが大切。治療成績向上の秘訣はそこにある 血液がん治療に新たな可能性を開く臍帯血移植
- がん患者、家族1800人を対象にした大規模調査から問題点をアピール 患者の声を医療政策に反映させようと立ち上がった
- 人の痛みや苦しみを体感した彼女が、自ら生み出した“LIVE FOR LIFE” 同じ境遇の人たちに勇気と希望のエールを。美奈子はそれをライフワークに選んだ
- ポイントは、ナース。ナースが意思決定に加われば医療の質も、患者満足度も上がる がん医療全体の質を上げるために、骨身を惜しまず取り組む
- 「なぜベストな治療にまっすぐたどり着けないのか」という疑問から出発した医療改革の道 日本の医療を良くするには、アメリカの医療の良い面を取り入れるのが早道


