- ホーム >
- 連載 >
- 田原節子のもっと聞きたい
シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・渡辺 亨さん 知れば知るほど奥の深い抗がん剤、もっともっと知りたい
抗がん剤はどうやってがんをやっつける?

渡辺 細胞には、分裂の周期があります(図2)。G1期でお休みをしていて、S期でDNAの合成を行います。G2期でまたお休みをして、M期で二つに分かれていく。この繰り返しです。がん細胞も正常細胞も同じですが、がん細胞の特徴は、無秩序、無限の増殖です。口の粘膜や毛根、腸粘膜の細胞などの正常細胞の分裂は、秩序だっていますが分裂そのものは速い。
抗がん剤は、細胞がS期で、周りからいろんな栄養素を取り込んでいるときには、その餌を遮断してしまえばいい。M期は、分裂途中で細胞が不安定です。M期に、二つに分かれていくDNAをひっぱる紡錘糸という糸ができますが、タキソールやタキソテールは、この紡錘糸ができなくする薬です。アドリアマイシンは、DNAが二つにわかれて、それぞれが片割れとなるDNAを作るときに、わかれさせないようにホッチキスのように止めてしまう作用の薬です。DNAの材料にウラシルというものがあるのですが、5-FUは、S期に、ウラシルの偽物になって、そこから先の合成を邪魔します。
田原 私は、アドリアマイシンはぜんぜん効かなくて、タキソールはよく効きました。それは、細胞の分裂の最後の段階で効く抗がん剤のほうが私には効く、と言えるんですか。
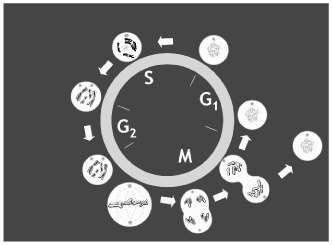
細胞はG1期で休み、S期でDNAの合成をし、G2期でまた休み、
M期で2つに分裂。このサイクルを繰り返して増殖する
渡辺 薬が効かないのには、いろいろな理由があります。たとえば、細胞の外に、薬の成分を汲み出してしまうポンプが、細胞の表面に存在する場合があります。細胞にそういうものが備わってしまうと「耐性」となります。
田原 その人のもつがん細胞に性格があるということですね。
渡辺 性格があって、耐性を獲得するわけです。だから、アドリアマイシンはS期に効く、タキソールはM期に効くから、一緒に使うことによって、S期で生き延びたものをM期で叩くという意味で、抗がん剤の併用が行われるわけです。
副作用対策薬を使いこなす内科の真骨頂

渡辺 がん細胞でも正常細胞でも、分裂の早いものは抗がん剤によって軒並みダメージを受けます。毛根に働いて毛が抜ける。骨髄に働いて白血球が減る。消化器粘膜がやられると下痢、皮膚や爪がぼろぼろになることもあります。また抗がん剤は化学物質なので、脳の延髄に働きかけて、吐き気をおこさせます。しかし、10年前と比べると、アドリアマイシンでの吐き気は、桁違いに少なくなっています。
田原 アドリアマイシンそのものが変わったんですか?
渡辺 アドリアマイシンはアドリアマイシンです。変わったのは吐き気止めが格段に進歩したから���す。
田原 抗がん剤の研究と副作用止めの研究が2本立てで進んできたわけですね。
渡辺 ここ10年の一番の進歩は、やはり副作用対策薬ができてきたということです。デカドロンというステロイドホルモンは、上手に使うと非常にいい薬ですが、糖尿病を悪化させたり、感染に対する免疫力を低下させる副作用があります。そればかり恐れて使うべきときに使わない医師が多いのですが、必要なときに、短期間、きちっと使えば大丈夫なんです。*セロトニン受容体拮抗薬(カイトリル、セロトーン、ナゼアなど)とデカドロンでアドリアマイシンの吐き気は9割はコントロールできるのに残念です。
*セロトニン受容体拮抗薬=セロトニン受容体は自律神経系や知覚神経、延髄などにあり、嘔吐反射に関係する。セロトニン受容体拮抗薬は、セロトニン受容体の過剰な働きを抑える
田原 今も、抗がん剤の開発と同時に、副作用止めの研究はつづけられていますか?
渡辺 たとえばタキソールのしびれ止めとか、予期嘔吐といって、「明日抗がん剤治療だな」と思っただけで気持ちが悪くなるといった条件反射を抑える薬などがあります。
田原 身体には何もしていないのに起こる症状ですよね。それでも副作用というんですか?
渡辺 広い意味では副作用でしょう。これは、精神安定剤の一種を飲むと軽くなることがわかっています。
副作用のマネージメントには定番があり、それらがもっと普及する必要があります。抗がん剤そのものが良くなってきたこと、抗がん剤治療の重要性も認識されてきたこと、きわめて短時間で投与できる薬剤も増え、便利になってきたこと、副作用対策が進歩してきたこと。これらはみんな薬のことですから、内科医の腕の見せどころとでも言えるでしょう。
田原 乳がんの場合、乳腺外科にかかりますよね。内科の先生とは、考え方が違うのでしょうか?
渡辺 外科医は機械的な考え方をします。そこに何かあったら、それをいかに安全に切り取るか。そのために解剖学を学び、血管がどこにあるかなどに習熟しています。内科では、生物学的な考え方をします。そこにあるものが、身体にどういう影響を及ぼしているかを考え、その影響さえ遮断できれば、切り取らずに、身体の生物学的な調整をうまくやっていこう、という考え方です。がん治療は外科と内科、ふたつの考え方が協調することが必要ですね。
田原 副作用を止めるというのは、まさに内科的な考え方ですね。
渡辺 QOLを重視する考え方も増えてきましたし、仕事をしながら治療をしたいという人が増えて、外来での治療が増えてきました。
田原 5年前に、アメリカでは外来で抗がん剤治療ができると知ったとき、私は、「こんなに白血球が下がるのに、外来でできるわけがない」と思ったのを覚えています。今では日本でも外来で抗がん剤治療ができる。すごい違いですね。
渡辺 白血球の数が2000を割っても、熱さえ出なければ大丈夫なんですよ。点滴して1週間目には、必ず白血球は減るものです。病院も患者も忙しいのに、わざわざ減っている時期に病院に来てもらって、わざわざ測ってわざわざ驚いて、こりゃ大変だと入院させて、*G-CSFなんか投与する必要など、どこにもないんです。白血球減少に対しては、3~4年前に「知らぬがほっとけ」ということになりました(笑)。あらかじめ経口の抗生物質を処方しておいて、発熱したら内服してもらい、2日飲んでも改善しないようなら病院に連絡してもらい、そこでバックアップ態制はとります。
田原 多くの先生方は、2000以下になったら大変だから入院しなさいとおっしゃいますよね。間違いなんですか?
渡辺 間違いではありません。白血球が減る時期に下痢をするとか、具合がすごく悪いなどということがあれば要注意です。発熱だけだったら抗生物質でマネージできます。
*G-CSF=糖タンパクの一種で、造血幹細胞の中から、白血球のひとつである好中球が作られるのを助ける薬剤
交互に発達してきた抗がん剤とホルモン剤
田原 ホルモン剤と抗がん剤は、両方合わせて抗がん剤と言っていいんですか?
渡辺 抗がん剤というと、普通はいわゆる「毒」から発生してきた細胞毒性抗がん剤を指します。ホルモン剤というと、別のものをいいます。
田原 がんを抑制するという意味では同じ領域ですよね。ホルモン剤は、ホルモンレセプターに対して効果を発揮するということで、今の分子標的に近いですね。
渡辺 ホルモン剤は細胞そのものを攻撃するのではなく、がん細胞の持つホルモンレセプターだけに作用しますから、分子標的薬剤そのものです。
田原 ホルモン剤は、抗がん剤と同時進行で開発されてきたんですか?
渡辺 同じく1970年から80年、90年と開発されてきました。
田原 すると、ホルモン剤の治療も、当初からあったということですね。
渡辺 もっと古くて、19世紀からです。若い女性の乳がんは年配の女性より予後が悪いので、卵巣にその原因があるに違いない、という判断で卵巣を取ってしまったら、骨の転移が改善した。1894年にイギリスでビートソンという人が報告しています。これがホルモン療法の始まりと言われています。60年代後半にCMFなどの抗がん剤が出た頃、ちょうどホルモン療法の限界がわかってきて、細胞毒性抗がん剤の効果が見直された。その後、また別のホルモン剤が出てきて、交互に研究・検討が進んできたのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 田原総一朗手記 がんを生き抜いた人生のパートナーに捧ぐ 「5年10カ月」の価値―生きる意志をエネルギーにした妻・節子
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・竹中文良さん 『がん』と『心』の深い結びつきにさらなる注目を!!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・佐々木常雄さん 腫瘍に精通したホームドクターが増え、チーム医療が充実すれば、がんの在宅治療は定着する!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・青木正美さん 大いに語り合った医師と患者がよい関係を築く秘訣
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・荻野尚さん コンピュータと情報の時代の申し子 陽子線治療は手術に匹敵する治療法
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・幡野和男さん さらに副作用を少なく! 放射線の最先端治療 IMRTのこれから
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・西尾正道さん 初期治療から緩和ケアまで、がん治療に大活躍する放射線治療のすべて
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・渡辺 亨さん 知れば知るほど奥の深い抗がん剤、もっともっと知りたい


