- ホーム >
- 連載 >
- 田原節子のもっと聞きたい
シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい
医師の説明不足 患者の理解不足
田原 検査の方法が、CTとかMRIとかが増えることによって、診断がかつてより複雑で時間のかかる作業になっているということですか?
堤 そうなっていますね。とくに早期の病変とか、がんかどうか判断が難しいとか、微妙な病変ほどそのことがすごく大事ですね。
僕らが医学生だったころより検査の種類が増え、質も向上しています。微小ながんやごく早期のがんについては、個々の事例についてていねいに対応しないと、臨床医や患者さんのニーズに応えられませんから。
田原 よく乳がんの患者さんが手術後、「きれいに取れたと思います」と先生から言われて、そのあと実は断面に残っていましたから再手術をしましょうということになったりして、非常に混乱して傷つく場合があるんですが、いまお話を伺ったようなことなんですね。
堤 それは、最初から医師側の説明不足であることが少なくないですね。でも、患者さんも手術前に言われていても、よくわからないことが多いですよね。手術したあとに自分で勉強して、いろいろなことがわかるようになってくるし、こういうことを知りたいと思うようになってくると思うんです。だったら同じことを言われても、手術後の時点と、最初に言われたときとでは、患者さんの理解度も違ってきていますよね。
医者からすると再手術はしたくないですから、再手術を前提には考えないし、だから再手術を前提にした話もしません。それでも再発してしまうと、今の話のようなことになるのです。
みんな症状が同じならマニュアルに書いておけばいいのですが、病気というのはそんなに単純ではないですからね。僕は病理を始めて28年目ですが、それでもまだまだわからないことがたくさんありますから。
田原 ドクターにとっては、前の手術が失敗したから再手術するのではなくて、足し算なんですね。しかし、患者にとっては失敗のやり直しと感じられてしまう。難しいですね。
「小さく取りさえすればいい」は危険なことも
田原 小さく取って欲しいという患者の希望があるんですね。とくに胸に関してはいろいろな行き違いも多いと思う。
堤 大腸の話をしますと、がんのある部位によっては、そこにあるがんの部分だけをやみくもに切ると、患者さんは腹膜炎で大変なことになります。大腸には、腸間膜動脈という血管がきていますが、その血管が栄養する範囲を考えずに切ってつなぐと、つないだ部分が栄養不足になって壊死してしまう。この血管が支配している領域を考えて、大切に切り取らないといけないのです。いつも小さく取らないといけないというのは間違いで、臓器によって神経支配や血管支配などの事情から、ある一定範囲の正常部位も切��取らざるをえません。このあたりは医師に任せてもらうしかないですね。乳がんでも、無理して温存手術したために再発した例を知っています。最初から全摘すべきだったのにね。
田原 病理の先生がいる病院といない病院があるということですが、ただでさえ少ないという病理の先生がいない病院にかかった患者は、どのようにしたらよいですか?
堤 日本病理学会が認定する病理専門医制度があります。今、病理専門医は1800人ぐらいですね。毎年約80名が病理専門医になっています。全国80の医大、医学部から一人ずつ、全体の1パーセントの計算です。それを多いととるか少ないととるかですが、一般的には少ないと言われています。でも僕はそう言われていることに少し批判的なんですね。麻酔医や小児科医、リハビリテーションの医師のほうがもっと不足しているのでは、と思う側面もあります。
田原 先生は何に興味を持たれて病理の先生になられたのですか?
堤 学生時代に習ったことすべてを活かして、全部みられるような領域は何かなと思っていました。欲張りですから。病理に進んだのは、いろいろな臓器や病気を幅広く、じっくりみられることに魅力を感じたということですね。
外に向けた発信、外からなかへのアプローチ
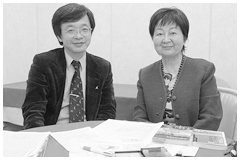
病理学会から患者サイドに向けた情報、
患者サイドから病理医に向けた発信、
ともに大きく歩み寄りたい
田原 病理学という視点からみて、現在の医療に問題点はありますか?
堤 病理学は基礎医学に属しているために、病理医が臨床医として認められていないんですね。これは日本だけだと思いますが。
田原 なんで日本だけそうなんですか?
堤 厚労省の定める医療法がありますね。このなかで標榜科は患者さんに対する「広告規定」とみなされています。つまり医療法では患者さんが直接来ない病理が、病理科を標榜してはいけないことになっている。病理は患者が直接来ないということで軽視されているんです。だから病理診断を一生懸命やる医師も育ちにくいということもあるのではないかと思いますね。これだけセカンドオピニオンの必要性が言われていても、患者さんはどこで自分の病理診断がなされるのか、どうしたら病理診断のセカンドオピニオンがとれるのか、知らないんです。
標榜科になるということはすごく大事なんですよ。臨床医学として認められるということですから。
田原 まさに臨床ですよね。診断しているんですから。それなのに患者と病理医をつなぐ道が絶たれているんですね。
手術中の迅速診断というのも、病理の先生がいないと絶対にできないことですか?
堤 できません。でも、常勤医がいなくても、毎日パートの病理医がカバーしていることもあります*。
田原 病理の先生がいらっしゃる病院で、患者さんが入院中に病理の先生のお話を聞かせてくださいと言って、お話を伺うことはできますか?
堤 実現できると思いますね。むしろぜひそうして欲しいと思います。標榜科でないことによるデメリットが大きくて、これまでは病理医がそこまでする必要はない、という風潮が強かった。患者さんがたくさん来てくれれば、標榜する必要が高まります。ぜひそういうようにしたいと思っています。
田原 その病院に病理の先生がいらっしゃるかどうかは、どうすれば知ることができますか?
堤 院内の表示をみるとかでも確認できますが、一番簡単なのは、診察中に外来の医師に確かめることでしょう。日本病理学会としても、外へ向けてさまざまな情報を発信しなければいけないと思っています。
田原 手術を受けても、自分のがんの診断は主治医だけがしているのではなく、実は病理の先生の診断があってされているんだ、ということを、患者はもっと広く知るべきですね。
*編集部注=最近では画像通信を利用した遠隔病理診断(テレパソロジー)ができるようになってきているが、堤さんはこれを「迅速診断よりも、診断に関する相談や、情報交換に適した手段」と考えている
同じカテゴリーの最新記事
- 田原総一朗手記 がんを生き抜いた人生のパートナーに捧ぐ 「5年10カ月」の価値―生きる意志をエネルギーにした妻・節子
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・竹中文良さん 『がん』と『心』の深い結びつきにさらなる注目を!!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・佐々木常雄さん 腫瘍に精通したホームドクターが増え、チーム医療が充実すれば、がんの在宅治療は定着する!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・青木正美さん 大いに語り合った医師と患者がよい関係を築く秘訣
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・荻野尚さん コンピュータと情報の時代の申し子 陽子線治療は手術に匹敵する治療法
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・幡野和男さん さらに副作用を少なく! 放射線の最先端治療 IMRTのこれから
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・西尾正道さん 初期治療から緩和ケアまで、がん治療に大活躍する放射線治療のすべて
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・渡辺 亨さん 知れば知るほど奥の深い抗がん剤、もっともっと知りたい


