特別対談・日本のがん対策を考える 土屋了介(国立がんセンター中央病院病院長)×中川恵一(東京大学医学部付属病院放射線科准教授)
がん先進国でありながらがん対策後進国の日本
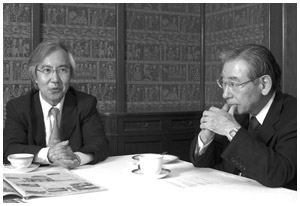
中川 先日、ある企業が発表したデータによると、その企業の社員で在職中に亡くなった社員の半数の死因ががんだったというのですよ。では、この企業が特殊なのかというと、いろんな企業の健康保健組合の方に伺うと、どの企業も大体同じ。今や死因の半分はがんであり、この比率は世界で最も高い。日本は世界1のがん大国なんですね。
土屋 しかし、がん対策に関しては後進国です。喫煙率1つとってみても、男性だと実に4割の人が喫煙者です。がん検診の受診率は2割程度にとどまっています。ですから、がん医療の質を問う前に、喫煙率を下げるとか、がん検診の受診率を高めるといった、がん医療の外側にある対策を進めないといけません。
中川 がん医療の外側にある対策というと、がん登録もぜんぜん進歩していないことも忘れてはいけませんね。がんのような国民病であれば、科学的なデータを残していかないといけません。そのためにはがんの罹患データの積み上げが不可欠で、がん登録が必要なのは自明なのですが、まったく進んでいません。死因を調査するなら死亡診断書をデータ化すればいいわけですが、罹患データはどこにもありません。感染症については感染症予防法に基づいて届け出義務がありますから、指定された感染症なら、昨年の新規罹患者数は明らかになっています。しかし、昨年、日本で何人が新たに乳がんや肺がんになったかどうかの確定的な数値はありません。
土屋 一部の政党が反対したことで国民総背番号制が実現しなかったことが大きく影響していると思います。アメリカではすべての国民がIDナンバーをもっていますが、日本はこれがない。そのため病気の登録制度が作れないままになってしまいました。ただし、がん登録については医療関係者も反省しなければならないと思います。患者の罹患データはカルテが基本となるわけですが、同じ病院であっても診療科が違えばカルテはばらばら。これではがん登録などできるはずがない。
中川 そもそも医者の頭の中に診療科の違いなど関係なく、1人の患者には1枚のカルテで病歴を追跡できるようにするなんて考え方がなかったのですね。
土屋 「1患者、1カルテ」はようやく実現しましたが、これもカルテの電子化を受けて派生的に実現したことです。30年ほど前にスウェーデンに視察に出掛ける機会があったのですが、当時は今ほどコンピュータも進歩していなかったにも関わらず、がん登録が整備されていて、全国的に患者の病歴を追跡できていました。日本では同一病院内での追跡はできるようになりましたが、全国にまで広げて追跡することはできません。がん対策で日本がいかに後進国であるかがわかりますね。
まずは会社でがん検診の推奨を
中川 がん登録の整備も急務ですが、これはもう少し時間がかかりそうです。だったら、まずがん検診の受診率を少しでも上げないといけません。そこで、まず会社でがん検診への受診を推奨していただけないかと考えています。
土屋 そのためには経営者の意識改革が必要ですね。健康診断は労働安全衛生法に基づいて実施されているわけですが、これが普及したのは従業員の健康を守ったほうが、業績は良くなると考えられたから。だったら、がんについても同様に考えてもらわなくちゃいけない。がんから従業員を守ったほうがいいと経営者が考えれば自然と健康診断にがん検診が組み込まれているはずです。ですから、ただ漠然と「がん検診は必要です」と提案してもすぐに経営者は動かないでしょうから、我々、医療関係者ががん検診を実施したほうが得だというデータを示さなくてはいけません。がん検診を受けるインセンティブ(動機づけ)が必要です。
どんな人生を送りたいかを考えることから始めよう
中川 私が議長を務めさせていただているのですが、厚生労働省が「がん検診企業アクション」というプロジェクトを始めました。受診率向上に賛同した企業に参加してもらい、社内でがん検診の普及啓発を促してもらう取り組みです。参加する企業にとっては、社員の健康を考え、がん検診を推奨している姿勢をアピールできればイメージアップにつながるというインセンティブを提供しているわけです。
土屋 となると、個人の受診率の向上が必要となりますね。より受診しやすくしていかなければならないわけですが、自治体によっては無料で実施しているところもありますし、有料であっても決して高くはありません。受診の手間だってたいしたことではありません。
中川 子宮頸がんの場合、子宮の出口(子宮頸部)を綿棒で拭うだけです。乳がんはマンモグラフィで検査できますし、大腸がんなら検便だけで調べられ、いずれも煩わしい手間がかかりません。これらの3つのがんについては検診の有効性は科学的に証明されています。進行がんになってがんが見つかれば、完治が難しくなるだけでなく、抗がん剤を服用し続けなければなりません。患者さんによっては強い副作用に苦しめられることもあるでしょう。早期であれば、ほとんど完治が望めるわけなんですから、子宮頸がん、乳がん、大腸がんついては検診を受けないのは損ですよ。
土屋 結局、どんな人生を送りたいのかを考えることから始まるんじゃないでしょうか。人生をよりよく生きるために最も重要な資産は体であることは言うまでもありませんが、その体をより良い状態に保つには何が必要なのか、もっと考えていただきたい。
今や2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる時代なのですから、誰でも共通にがんになるリスクを負っています。だったら、進行してから初めてがんが発見されるのではなく、早期発見、早期治療を実現するしかない。自分がどう生きたいのかをもっと考えれば、自ずとがん検診の受診率は上がっていくんじゃないでしょうか。
(構成/齊藤勝司)
同じカテゴリーの最新記事
- がん治療も自分で選ぶ時代に~菅原文太の膀胱がん治療体験に学ぶ~ 菅原文太(映画俳優) × 中川恵一(東京大学医学部放射線教室准教授)
- 特別対談・鈴木 寛(文部科学副大臣)×樋野興夫(順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授) 東日本大震災・原発事故を乗り越え、人類に貢献する日本をつくるために
- がん闘病中の「知の巨人」VS「がん検診の伝道師」 がん徹底対論・立花 隆(評論家) × 中川恵一(東京大学病院放射線科准教授)
- 特別対談・日本のがん対策を考える 土屋了介(国立がんセンター中央病院病院長)×中川恵一(東京大学医学部付属病院放射線科准教授)
- 子どもが欲しいという想い、そして持たないという選択 特別対談・洞口依子(女優) × 高橋 都(東京大学大学院講師)
- がん細胞から世界平和まで縦横に語り合う白熱の3時間 「知の巨人」立花さんが自らのがん体験を踏まえ、樋野さんに鋭く迫る がん特別対論・立花 隆(評論家) × 樋野興夫(順天堂大学医学部教授)
- 子宮をなくしたが、「女であること」を自分の中でもっと開花させたい 特別対談・洞口依子(女優) × 高橋 都(東京大学大学院講師)
- がん緩和ケアのコンセプトが未だに理解されていないのが問題です 特別対談・岸本葉子(エッセイスト) × 向山雄人(癌研有明病院緩和ケア科部長)
- 特別対談・日本のがん医療を考える 養老孟司(北里大学教授、東京大学名誉教授)×中川恵一(東京大学助教授)


