- ホーム >
- 患者サポート >
- 患者のためのがん医療
不安や悩みを吐き出して力を抜けば、再度力を入れられる 患者とともに創る「乳がん女性のためのサポートプログラム」
一般の患者会とサポートグループの違いとは

サポートプログラム創りのために話し合うスタッフたち
このサポートプログラムと一般の患者会の違いは、グループごとに小松さんはじめ同大学のスタッフや聖路加国際病院の乳がん看護認定看護師などの専門職がファシリテーター(調整役)として加わり、参加者1人ひとりが快く話せるように伴走していることです。
「体験者同士の衝突や議論はあってよいのですが、だれかが深く傷つくことがないように、場の雰囲気や話の流れを臨機応変に調整するのがファシリテーターの役割です。また、医学的に間違った情報については訂正し、正しい情報を提供します」
話し合いの内容は口外しないこと、話し合いの時間を1人で独占しないこと、医療機関や医療者への批判に終始しないことは、この場での「お約束」です。
もう1つ、このサポートプログラムの大きな特徴は、患者さんにもプログラム創りに参加してもらうことです。サポートプログラムに何回も参加してつらい状況を乗り越え、勇気を得た患者さんは成長して、自分もなんらかの役に立ちたいと思うようになるといいます。現在、コアメンバーとなっている10数名がプログラムの内容への提言、ツールのデザイン等を行うほか話し合いのグループ内ではファシリテーター的な役割も担っています。
「コアメンバーの方が、初めての参加者にさりげなく水を向け、体験者ならではの視点と気づかいで接してくださっていますが、これは大変プラスになっています」
体験者がプログラムに参加し、伴走もすることで、医療者・専門家側からの一方通行でなく、より参加者のニーズに合ったサポートになるのです。
「通常のグループセラピーなどは、毎回同じメンバー構成で、セッションの回数を決めて終了というケースがほとんどです。でも、サポートグループの効果は、頻度が多く、長期に継続するほど高いといわれているので、このサポートプログラムでは、参加期間を限定せず、長期の参加もできるようにしています。また、話し合いの内容がマンネリ化しないようにグループのメンバーも固定化せず、その都度変えています。参加が負担にならないように、出席を強制することはありません」
巣立ちの日は参加者が自分で決めます。配布される「サ���ートプログラムテーマカード」の8つのテーマについてメモしていき、自分自身で各テーマについて深められた、クリアした、と思えたときが巣立ちの目安になります。
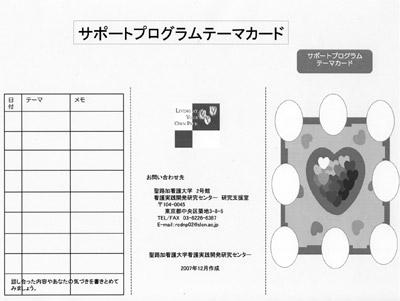
参加者に配布されている「サポートプログラムテーマカード」
「答えは1つではない」と感じ取れる大切さ
一般の社会では、手術がすんで退院すれば終わり、という程度の認識しかされないことが多く、その後のサポートは貧しいものです。化学療法、ホルモン療法中でも、子供の行事や家事、仕事を休むことはなかなかできません。先行きの不安がちらつくこともあります。それらの悩みをじっくり聞いてくれる人、一緒に考えてくれる人が身近にいなくて、たった1人で心身ともにストレスを抱え込んでいる方も多いことでしょう。
その点、同じような体験をした患者さん同士が気兼ねや気負いなく、ありのままの自分の状況を話し、それを聴いてもらう、受け止めてもらう場があるのは心強いものですし、一時的にでも肩の荷をおろすことができます。直接の解決方法が見出せなくても、人の体験を聴くことで、悩んでいるのは自分だけではない、と孤立感から救われることもありますし、人それぞれ違うのだ、いろいろな考え方があっていいのだ、答えは1つではない、とおおらかな気持ちになることもできます。
「家庭では、いつも明るい元気なお母さんでいなければ、と弱音を吐かず、不安を心の奥にしまいこんできた人でも、グループの中で悩みを話すことで、すっと力を抜くことができます。力を抜ける場があれば、もう1度力を入れることができるんです」
手術直後に、主治医の許可をもらって病室から参加する方もあるとか。退院後はどう生活をしたらいいのか、先輩たちから吸収したいと思われてのことでしょう。
「抗がん剤治療の翌日は吐き気が強いので、治療した日に買い物や料理をして冷凍しておくなど、体験者ならではの苦闘がにじむ話もあり、これから抗がん剤治療を受ける人へのよきアドバイスとなります。最近の会では、ホルモン療法中の複数の方から、バネ指といって指がつっぱる副作用の症状があるという話が出ました。即効的な解決法はないけれども、起床時に指を動かしてウォーミングアップしてから家事に取りかかるとよい、などの知恵が交換されていました」
病気のことを家族や友人にどう伝えるかという問題では、「人には話しにくい」「まったく話していない」という人もあります。人それぞれの状況に応じて違い、答えは1つではない、ということを感じ取れるのも有用です。
「がんとともに歩んできた人は自分の経過を振り返り、その体験をこれから歩んでいく人に伝えることができます。治療を開始したばかりの緊張している人たちも、サポートプログラムを通してさまざまな体験をシェアし、ものすごく苦しい時期を乗り越えられる。そして、乗り越えた後、自分の体験や知恵を伝えて、これから歩んでいく人をナビゲートできる。そのようなよい循環になっていることを、私たちも実感しています」
落ち込んで暗い顔をして参加した人が、笑顔で帰宅することもよくあるといいます。
参加者の声を見ると、「本やインターネットではわからないリアルな話が役立った」「同じ状況の仲間とかつらの話題など気兼ねなく話し、笑い飛ばせて、元気がもらえた」「揺れているのは皆同じだと安心した」「落ち込んでも、再発していても、この場で一休みし、活力を取り戻して、また新たな気持ちで暮らしていける」など、揺れる心をほっと落ち着けたり、パワーアップしたりしている姿が目に浮かびます。
何処でも誰でもサポートが受けられる体制にしたい
小松さんは、現在まで5年間のサポートプログラムで蓄積された、体験者ならではの知恵をまとめて発信する準備を進めています。
「将来的には、インターネットなどを通して、だれでもサポートが受けられるようなプログラムも作る予定です」
現在行われているサポートプログラムに参加したい方は、インターネットの「看護ネット」から乳がんサポートプログラムのページにアクセスして、サポートプログラムの内容と開催日時、場所を確認し、メールまたはFAXで「乳がんサポートプログラム希望」と書き、連絡先と名前を明記して申し込みをしてください。参加費は無料です。
「悩みはあるけれど、このサポートプログラムには参加できないという場合は、まず、現在かかっている医療機関の医療者に相談してみてください。乳がんはチーム医療ですから、主治医が忙しかったら、看護師に声をかけるといいでしょう。1、2分話すだけでも気持ちが楽になることがありますし、解決することも多いものです」
一言、二言でもまず言葉を発することで、次の1歩が踏み出せるかもしれません。
同じカテゴリーの最新記事
- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院
- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート
- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす
- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を
- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します
- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい
- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい
- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート


