- ホーム >
- 患者サポート >
- 患者のためのがん医療
日本のがん治療が新たなステージへ がん対策基本法で何が変わるか?
「がん対策基本法」の施行後に残る課題
平成19年4月1日施行
がん対策基本法の目的
この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
「がん対策基本法」が成立する過程で、行政・医療者・関係企業の尽力の結果、幾つかの問題は改善に向かっている。
未承認薬の問題では、国が「未承認薬使用問題検討会議」を設置。11回におよぶ会議では、従前より高い問題意識のもと早期承認に取り組んでいる。適応外使用の問題についても、海外で標準化している治療法・治療薬の多くに適応症が追加され、保険適用となってきている。
なおも残るのは、有用性が確認されている治療法や治療薬が提供されていないという実態である。標準治療における地域や施設間の格差はいまだ是正されておらず、施行後も課題として残っている。標準治療が実施されていないのは、抗がん剤に限ったことではない。疼痛緩和におけるモルヒネの使用量や放射線治療についても同様のことが言える。
こういった問題の背景には、専門医の不足、それらの治療をサポートする専門医療者の不足、さらに遡ればそれらの人材を養成する教育システムがないといった根源的な問題が存在する。
この法律を実効性のあるものにするには、まず医療者の認知度を高める必要がある。
「がん対策基本法」成立後、私は多くの医療者や医療関係者に会い、この法律が可決したこと、その内容について認知しているかどうかを尋ねたが、その認知度は著しく低いものであった。
この法律を認知し内容の詳細を把握するだけでなく、それを実際の「がん医療」の現場にどう還元していくか、医療者の裁量が問われていると考える。
| 患者・一般 n=52 | 医療関係者 n=49 | 合計 n=101 | |
|---|---|---|---|
| よく知っていた | 26.9% | 18.4% | 22.8% |
| 知っていた | 50.0% | 57.1% | 53.5% |
| あまり知らなかった | 15.4% | 4.1% | 9.9% |
| 全く知���なかった | 5.8% | 20.4% | 12.9% |
| 無記入 | 1.9% | 0.0% | 1.0% |
日本のがん医療は変わると思いますか?]
| 患者・一般 n=52 | 医療関係者 n=49 | 合計 n=101 | |
|---|---|---|---|
| 強く思う | 5.8% | 6.1% | 5.9% |
| 思う | 53.8% | 49.0% | 51.5% |
| 思わない | 13.5% | 12.2% | 12.9% |
| どちらとも言えない | 26.9% | 32.7% | 29.7% |
| 無記入 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
何を今更との声も。当たり前を明文化した「がん対策基本法」
「がん対策基本法」第2条には、3つの基本理念が示されている。複数の医師から、「当たり前のことばかりが記載されており、また罰則規定もない。施行されても大きな意味はないのではないか」との声を聞いた。
では、なぜその当たり前を法律にする必要があったのだろうか。医療者には、その点についてもっと深く考えてもらいたい。日本の「がん医療」の現場は、「当たり前」と思われることが実施されていない状況にあった。形骸化したがん医療の「当たり前」の中身を再度確認し、行動化していくうえで、この法律は意味を持つだろう。
がん対策基本法の3つの基本理念
1 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること
ここ数年、乳がんの死亡率が低下している米国では、マンモグラフィなどによる検診(スクリーニング)と並行して、そのときどきの最新かつ最適な治療が実施されている。死亡率の低下は、検診と臨床的な取り組みの双方があってこそ達成されたのである。
これまでの日本は、予防・診断に重点がおかれる傾向にあった。今後は、海外での成果と現状を踏まえたうえで、新しい治療法の開発、特にその基礎をつくる臨床試験等に対する正しい理解と取り組みを行っていく必要がある。
欧米並みのスピードで期待される治療法を手にするには、エビデンス(科学的根拠)をつくり(臨床試験等で)→そのエビデンスを普及し(ガイドラインなど)→実地医療で使用するという一連のサイクルの重要性を認知しなければならない。貴重な予算が、臨床試験などの研究に投じられることを期待したい。
2 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること
平易な表現にすれば、日本全国どこに住んでいても、同じ「がん」、同じ病期(ステージ)、同様の予後因子(生存に影響を与える因子)であれば、その時々の最も期待される標準治療が提供されるようにするという意味である。現在、同様の背景を有する患者に対して、科学的知見に基づく適切な医療が平等に提供されているかと問われるならば、答えは「ノー」である。
この原因としては2つが考えられる。1つは、そもそもガイドラインなどに示されている医療自体が、すべての患者さんには適合できないというガイドラインの限界に起因している。
もう1つは、地域間・施設間・医師間での、治療法のバラツキによるものである。こうした実態により、一部の患者は不利益をこうむっていると言わざるをえないだろう。
もし医療者が、公的なガイドライン、それに関連する指針、コンセンサスなどがあるにもかかわらず、これらに記載されていない治療を提供するのであれば、その理由を明瞭にし説明する責任がある。
3 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分に尊重してがんの治療方法などが選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること
患者にとって最も重要な問題であるが、対応が行き届いていない。
個々の患者に対し、十分な説明をしたうえで、適切な治療法が複数提示されたか? 患者が抱えるのは直接治療に関する問題だけではない。家族構成、社会的役割、治療に対する希望など、考慮する必要がある。
ある患者会のリーダーは「この法律が施行されることで、治療の選択肢が増えることはうれしいことです。ときとしてその選択は患者にとって難しいものになるかもしれません。ですが、患者の意思に基づく医療実現のためには、その苦労もまた必要なことなのだと思います」と話す。
がん対策基本法で何を変えるのか?
「がん対策基本法」が施行となったものの、医療者におけるその認知、これから整備される事項を考えると、今すぐ何が変わるという大きな期待はできない。
しかし、この法律には特筆すべき点がある。それは、第4章第20条にある「がん対策推進協議会」の委員に、「がん患者及びその家族又は遺族を代表する者を厚生労働大臣が指名する」という記述である。
「患者中心のがん医療」を実現するうえで、この条項は大きな意味を持つ。がん患者を代表する委員の活躍によって、「がん対策基本法」の実効性が高まることを望む。
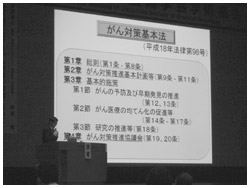
「日本臨床腫瘍学会総会」(札幌)における特別講演のようす
現在、私は札幌で開催されている「日本臨床腫瘍学会総会」に参加しながら原稿を執筆している。
今学会でも「がん対策基本法」は、特別講演にプログラムされていた。厚生労働省がん対策推進室の佐々木さんが講演する会場には、熱心に耳を傾ける医療者達の姿があった。
「この法案に関しては、党派を超え全会一致で成立し、また厚生労働省も本気で取り組んでいます」という佐々木さんのコメントが強く印象に残っている。
患者・家族・遺族・国民は、「本法で何を変えるのか?」を問うている。日本のがん治療は、ようやくスタートラインに立ったと言えるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院
- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート
- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす
- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を
- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します
- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい
- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい
- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート


