- ホーム >
- 患者サポート >
- 患者のためのがん医療
診療科の垣根を取り払い、「患者中心」の医療を実践 癌研有明病院消化器センターのキャンサーボード
議論の中では最新の治療報告が飛び出す

症例を発表する外科医長の大矢雅敏さん
2例目は家族性大腸ポリポーシス。若年で大腸にポリープが多発し、必ずがん化してしまう遺伝性の病気である。
「2年前にも消化器キャンサーボードで検討していただいています」
話を切り出したのは、担当医の武藤病院長の依頼を受けた外科医長の大矢雅敏さん。症例がモニターに。やはりカルテやCT、MRI画像を示しながら経過説明を始めた。この症例は、以前に家族性大腸ポリポーシスの標準治療として、大腸全摘出の手術を受けている。その翌年には、細胞は良性だが大きくなると致命的になることもあるデスモイド腫瘍を発症し薬物投与が行われたが、発熱や下痢などの副作用により中止。デスモイド腫瘍切除が実施されている女性だ。そして、2年前には腹部の腹直筋内に生じたデスモイド腫瘍が再発したため、「消化器キャンサーボード」で検討した結果、放射線治療が行われた。
「最近、再びデスモイドが増大したということで、どのような治療をしたらよいか」
そう話して、大矢さんは手術を提案する整形外科医のコメントを紹介。また、手術以外の方法として、従来から整形外科でデスモイド腫瘍に使用されている薬と抗がん剤による化学療法、あるいは、抗がん剤グリベックの投与、さらには、イタリアからの報告で有効だったとされる骨粗鬆症で使用されているエビスタという薬の使用と、症例に対する治療には4つの方法が考えられることを提示して意見を求めた。
「切除してもまた再発しますね」
「エビスタが効くのであれば試したほうがいいのではないか」といった意見の後、別の医師が次のように発言した。
「目の前の治療も重要ですが、女性の患者さんですから出産や授乳といった可能性もあります。ホルモン薬を使ったときの影響はどうでしょうか? また、今治療する必要は無いかもしれません」
他の医師からも「ご本人の希望を確認する必要があるのではないか?」との意見が……。話し合いは続き、結果として司会進行役の医師が、「この場で結論を出すのは難しいケースだと思います。今のところ手術は少し見合わせて、本人の希望を聞き、婦人科的な面を考え、エビスタの副作用を確認し、検討することでいかがでしょうか」と話をまとめた。
その後は、個人情報保護法への対応として、厚生労働省のガイドラインのビデオが流され、情報の共有化を図った後に、この日の「消化器キャンサーボード」は終了。
検討により患者へ最善の選択肢を示すことが可能
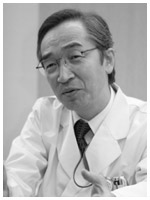
癌研有明病院消化器センター長の
山口俊晴さん
講堂から出てきた山口さんに、改めて話を聞いた。
「5年前から『消化器キャンサーボード』は行っていますが、今ではないと困るものになっています。他の病院にはこのような形のものはないと思いますよ。よく外科医だけでカンファレンスを行っていますが、切除した方がよいか否か意見が一致しないケースがあります。しかし、症例の難しいものは、『消化器キャンサーボード』で検討すると、外科だけでは考えられなかった意見が出てくることがあります。患者さんにも、外科だけでなく化学療法や放射線治療の先生方と集まって一番ベストの治療を検討します、というと喜ばれます」
一般病院では、治療の選択が難しい症例について、患者自身にその選択を迫るような場面が生じる。外科医から手術、内科医から化学療法、放射線科医から放射線治療と、それぞれの治療のメリット・デメリットを患者は聞かされることになる。
「患者さんが一番困りますよね。本当に聞きたいのは、患者さん自身に最も合っている治療法は何かでしょう。だから、患者さんを中心に置いて、『消化器キャンサーボード』で科を超えた専門医たちが話し合い、最善の選択肢の治療は何か、きちんと患者さんに提供することが大事だと思っています」
昔から手術、化学療法、放射線治療を組み合わせた“集学的治療”という言葉が、医療現場ではよく使われていた。が、それはけっして各科が一緒にという患者中心の医療ということではなかった。癌研有明病院では、本来あるべき集学的治療が、診察室の中でも科の壁が取り払われて行われている。
治療法に迷った場合は他科の医師の意見も聞く

病院内は、一般診療部門とは別に、臓器別診療に基づくチーム医療に分かれ、呼吸器センター、消化器センター、前立腺センター、レディースセンターを設置。センター内では、内科医や外科医が並んで診療に当たっている。
「私たちにしても、外来で外科と内科が一緒になっているとやりやすいのです。たとえば、内視鏡検査をしたときに、手術ではなく内視鏡で切除できそうだと判断した場合、内科の先生にすぐに電子カルテを見せながら相談できますし、処置してもらうことも可能です」
外科と内科が分かれているときには、外科で内視鏡による治療が可能だと判断された場合、患者は内科を改めて受診することになる。内科の予約を1、2週間後に入れて、やっと受診したものの、内科医からは手術が妥当と判断されて再び外科へ。患者は治療を受けるまでに時間がかかってしまう。
「内科の先生にすぐに相談できるだけではなく、医局は全ての科がひとまとめになっているので、電子カルテを見ながら別の科の先生にも意見を聞くことができるのです」
医局はワンフロアで、オフィスと見間違うほどの開放的な空間にデスクが並べられている。相談したい科の医師とは、デスク上の電子カルテで話がスムーズにできる。
このように、『医療の中心は患者』。患者にとって何がベストかを考え築かれた癌研有明病院のシステムは、病棟にも活かされている。
病棟も臓器別に分けられ、手術を受ける人、術後の人もいれば、抗がん剤治療、放射線治療を受けている人も一緒。従来は、内科や外科に病棟が分けられていたため、手術後に抗がん剤治療を受ける場合には、外科から内科の病棟へ患者は移らなければならなかった。ところが、臓器別にすると治療が変わっても患者は同じ病室のまま。外科や内科や放射線科の医師たちが、患者のところへ集まってくることになる。
「ドクターと看護チームのカンファレンスも、週3回、早朝に行っています。患者さんについての情報を共有することで、風通しをよくしているのです。初めは話しにくそうな看護師さんもいましたが、今は何でも話してもらえるようになりました。このように取り組んでいると、一体感が出てくるのです。お互いにカバーもし合えます」
とかく大学病院などにありがちな診療科ごとの壁や、看護師とのコミュニケーション不足など、癌研有明病院では無縁。患者中心の医療を実践している。
また、診断や治療のみならず、痛みなどに対する全身管理チーム、患者やその家族の悩みや問題に対して相談・援助を行う専任の医療相談員(MSW)、在宅医療をサポートする在宅医療支援室など、あらゆる面から患者へのサポートを実施。全室個室の緩和ケア病棟もあり、また、新たに開設したセカンドオピニオン外来では、治療法の選択に迷う場合の相談にも対応している。
「治療のガイドラインに当てはまらない症例は、『消化器キャンサーボード』にも登場した症例のように、セカンドオピニオンで相談に来られるケースがよくあります」
患者にとっての医療の在り方とは何か、その答えが癌研有明病院にはある。
「診療の垣根もどんどんなくなってくると思いますよ」
そういって山口さんは、約束している患者のところへ戻っていった。
同じカテゴリーの最新記事
- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院
- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート
- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす
- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を
- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します
- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい
- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい
- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート


