- ホーム >
- 患者サポート >
- 患者のためのがん医療
良い医療は、患者と医療者と行政が協力しあうことから始まる 患者よ! 声を上げよう。患者本位の医療の実現に向けて
愚痴をこぼすより声を出し、動こう
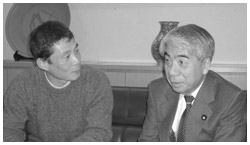

2003年のクリスマスに、厚生労働省の記者クラブで小さな記者会見が開かれました。患者の権利法を作る活動に、患者会として着手することを宣言したときです。昨年末から今年にかけて、議員会館内でシンポジウムを4度開催し、議員の方々からも多くの理解をいただきました。
これまで日本の医療はパターナリズムで、医療知識のある医師が患者へ提供するものであり、患者は素人なのだから口を出すなというスタンスでした。しかし患者も医療の消費者であり、人権を尊重される立場であり、最新で最良の医療を求めるニーズが高まっていることから、医療内における患者の位置付けが日本でも新たなものに変化しつつあります。
そうした環境の変化を受け、従来の医療を一方的に患者へ提供する考え方とは違い、患者を中心とした医療への新しい体制の整備が必要になってきています。つまり患者の権利を確立し、医療提供者(医師や病院、製薬企業)や行政と対等の立場で、お互いが協力し合いながらより良い医療を目指すことが必要だと考えられます。
この活動について、多くの場所で僕は話したり書いたりして来ましたが、心の中では『患者の権利法』ではなく『患者の義務法』だと思っています。『医療提供者や行政と対等の立場で、お互いが協力し合いながらより良い医療を目指す』とは、患者に対しても自分で考え判断するという責任という義務が求められます。もちろん正しい情報を受けるという権利とセットで。言うまでもないかもしれませんが、権利と義務は裏表一体であり、単なる権利を主張するのはただのわがまま以外の何物でもありません。
これまで日本の医療が遅れてきたのは、患者にも原因があり、患者も責任を負うという自覚がなく、医療提供者へおんぶに抱っこだったことが原因の1つだと僕は思っています。
良い医療とは、患者が満足する医療ですが、それは医療提供者より患者へ与えられるものではありません。権利法の制定だけにかかわらず、必要なことは受益者本人が声に出して活動しなければ得られないのです。
均てん化や未承認薬の問題も、多くの患者の熱意が行政や医療提供者を動かしました。これらも愚痴をこぼしていただけ���は今も解決は覚束なかったでしょう。お腹が空いたときに口を開けて上を見ていれば、誰かが口に食事を入れてくれますか? 食事をしたかったら、自分で働いてお金を稼ぐ以外には方法が無いことは大人なら気付くはずです。
これまでの患者会活動で分かった事実は、
・国民のレベル以上の医療は出来ない。
・医療を受けている患者にしか医療はよく出来ない
ということです。患者の権利法活動は、患者自身に『良い医療は、医療消費者と医療提供者、行政がお互いに協力し合い実現されるので、患者もそれに協力する義務がある』ということを宣言するための活動なのです。
患者本位の声を元に、医療を組み立てる

今、日本の医療の置かれている立場は、とても大きな曲がり角に差し掛かっていると言って良いでしょう。これまでのように日本経済が成長している間は医療費の伸びも気になりませんでしたが、経済の長期低成長化と少子・高齢社会の到来で、保健医療を賄う財政もピンチに陥っています。
また、肝心の医療もこれまではパターナリズムで『先生にお任せ』で済んでいましたが、患者の意識変化やインターネットによる情報のボーダーレス化により、より良い医療を自分で調べて選択をする患者が増えました。そのような現実を踏まえ、患者本位の医療(患者が満足する医療)を実現するためには、患者の声(ニーズ)を直接反映させるシステムを構築する必要があると考えています。
この度僕たちは、患者会が共通する目標に対し、共同で活動をするネットワーク作りを行います。国民医療費の引き上げ問題や中医協へ患者の声を反映させるために、患者会から委員を送り込むための法律の改正などにフォーカスをしていく予定です。このネットワークには、まだ名前もありませんが、2005年8月3日(水)に鎌倉市「鎌倉芸術館」において、がんに関する講演会とニューヨーク・シンフォニック・アンサンブルによるコンサートの夕べを計画しています。
これからはお上にお任せではなく、患者本位の声を元に医療を組み立てる必要があるでしょう。
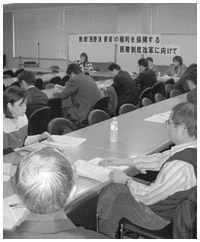
現在のシステムの欠点は、
・行政に患者がかかわっていない(行政への信頼性がない、情報公開が不足、行政と患者との意識格差大)
・医療提供者とパートナーシップがない(パターナリズム、医師と対等の立場ではない、情報量の不均等、情報公開不足、コミュニケーション不足)
・患者が自立していない(患者が主役との自覚がない、情報不足、患者同士の横のつながりがない)
など、医療提供者、患者とも反省しなければいけない面が多々あります。
これから患者参加型の医療行政を行なうためには、各々のエゴから出発するのではなく、行政と医療提供者に対し、パートナーシップとアライアンス(協働)を機軸とした、共通の目的(理念)を持ち対等性と透明性が確保された、どちらも損をしない『WIN・WIN』の関係を構築する必要があるのです。
患者会と行政、学会、医師会等の関係も、これまでの依存型(要望型)からプロジェクト創造型・提案型(共同作業型)へ転換し、医療提供者と一緒になって問題解決を図る、医療環境の変革に適応できる新しいモデルと手法を作らなければなりません。
より良い医療を求めるには、患者や患者会も主体的な参加と自己責任を前提とし、独立した、開かれた組織と横断的ネットワークの構築を目指す必要があります。
同じカテゴリーの最新記事
- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院
- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート
- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす
- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を
- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します
- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい
- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい
- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです
- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート


