- ホーム >
- 患者サポート >
- 医師と患者のコミュニケーション
医師と患者のコミュニケーションをより良くする情報提供技術を学ぶ SPIKESって何!?もっと知って、広めよう
SPIKESとは
そもそもSPIKESという言葉は、医療者が情報を提供するときポイントになる6つの要素の頭文字を集めた造語です。医療者と患者さんとの情報交換をスムーズにする大切な要素となります。
S Setting=面談のための環境設定をすること
P understand patients’ Perception=患者さんがどのように自分の病気を理解しているかを
把握すること
I obtain patients’ Invitation=患者さんに聞く耳を持ってもらうこと
K provide Knowledge=知識を提供すること
E have and show Empathy=共感を示すこと
S suggest Strategy=どういうふうにがんと戦っていくかを提示すること
この6つの要素について詳しく見ていきましょう。
Setting
- 立った状態での話は避けよう
- 廊下での立ち話は言語道断
- 静かで落ち着いた個室、診察室を使う
- 座る位置にも配慮
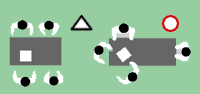
マスコミに名前の売れているあるがん専門医が、廊下で立ったまま患者さんに病気の説明をしている光景がテレビで伝えられました。こうしたことは言語道断であり、話をするためには静かで落ち着いた個室、面談室、診察室などを使うべきです。
面談のとき、座る位置に配慮することもポイントになります。医療側と患者さん側が正面から向かい合って対峙する形よりも、90度のアングルで患者さんを説明者がちょっと離れて見守るような感じにしたほうが話を伝えやすく聞きやすいでしょう。
また、医療側は面談のとき、ポケベルのスイッチを切るべきです。面談中にベルが鳴ればお互いに落ち着かないし、患者さんは「先生は忙しいのだ」と気を遣ってしまうことになります。
understand patients’ Perception
- 患者さんがどのように病気/治療を理解しているかを知る
- ここではよく聞くことが重要
- 時にはじっと我慢
- 適度に相づち
- 適切に言い換えて、こちらの理解を表明する
患者さんがどのように自分の病気や治療を理解しているかを知ることが必要です。医療者が患者さんの話をよく聞くことが必要であることはいうまでもありませんが、時には話がまわりくどくて、言いたいことを上手に伝えられないという患者さんにもしばしばお目にかかります。そこで、「時にはじっと我慢する」「適��に相づちを打つ」「適切に言い換えて、話を理解していることを表明する」などの態度が求められます。
obtain patients’ Invitation
- 患者さんに「聞く耳」を持ってもらう
- この先生の話なら聞いてみよう
- 信頼できそうだ
- よく勉強しているな
- 私の悩みをわかっているわ
- 他者(医師など)の批判はしない
- 「後医は名医」
- 結果論なら誰でも言える
- 職業人としての自覚と責任
患者さんに情報を伝えるためには「聞く耳」を持ってもらうことが前提になります。そのためには、「この先生の話なら聞いてみよう」「信頼できそうだ」「よく勉強しているな」「私の悩みをわかっているわ」というふうに感じてもらうことは大切な要素です。
また、患者さんやご家族の前では、医師など他者の批判はしないようにします。「後医は名医」という言葉がありますが、患者さんは前の病院の治療が効かなかったからこそ、現在の医師の前に相談に訪れているわけで、結果論なら誰でも言えることです。医療者は個人としての感覚で接してしまいがちですが、職業人としての自覚と責任を持ちながら接して患者さんの状況を十分理解する必要があります。
provide Knowledge
- 知識、情報を提供する
- 提供するためにはまず、正しい理解が必要
- 専門用語をできるだけ避ける
- ひと区切りずつ患者さんが理解しているかどうか確認しながら進める
医療者は患者さんに知識、情報を提供することも大切な仕事です。しかし、それを提供するためにはまず正しい理解が必要であることはいうまでもありません。
たとえば乳がんの患者さんが肝転移を来したとき、動注化学療法という治療を推奨する医師や医療機関が少なくありません。これについて「日本乳癌学会診療ガイドライン」には次のように記述されています。
【推奨】
乳がん肝転移に対して、動注化学療法は推奨するだけの根拠がなく、臨床試験においてのみ行われるべきである。一般臨床で成り立つものではない。
【解説】
乳がん肝転移に対する動注化学療法は一定の有効性が示されているが、静注化学療法との比較試験が行われておらず、また生存期間に与える影響が明らかでないため、日常臨床での使用は勧められない。正しい情報に基づいてわかりやすく説明することが大切です。
have and show Empathy
- 患者さんの状況に共感を抱く
- 感情ではなく理性で共感する
- あくまで医療者としての言動と行動
- 患者の家族の一員になりきって医師を批判する看護師がいた
医療者が情報提供を行うとき、患者さんの状況に共感を抱くことは大切ですが、あくまでも感情ではなく、理性に基づいた共感であることが必要です。また、あくまで医療者として、さらにチームの一員としての言動と行動が求められます。ある看護師が患者の家族の一員になりきって医師を批判した例がありましたが、「患者本位の医療」を履き違えたものといえます。
suggest Strategy
- 具体策、解決策(ソリューション)を提案する
- 患者さんのタイプに応じて適切に対応
- 患者さんは今日からどうすればいいのか
- フォローアップも大切
医療者は患者さんに対して、がんと闘っていく上での具体策、解決策(ソリューション)を提案することが大切です。なぜがん名門病院がしばしばがん難民を発生させているかというと、このストラテジーの提供がなされていない場合があるからです。たとえば「もう治療法はありません。ホスピスに移ってください」といった話し方をして、患者さんが困ってしまうケースがあります。患者さんのタイプに応じて、少しずつ状況を説明しながら、具体的に患者さんは今日からどうすればいいのかを伝え、伝えたらフォローアップすることも大切です。
以前アメリカの医学雑誌『JAMA(the Journal of the American Medical Association)』に医師と患者さんの関係には4つのモデルがあることが示されていました。それは「情報型」、「解釈型」、「審議型」、「父権型」の4つです。
このうち父権型は、昔からよくあった医師と患者の関係です。医師は「黙って俺について来い」と話し、患者のほうは「お任せします」という“おまかせ定食型”ということになります。
これとは対極にあるのが情報型です。この場合、患者や配偶者などの家族がインターネットを利用して病気のことをよく調べており、患者さんの価値観が固まっています。さらに医師はどんどん情報を提供して「ではこの方法で治療しましょう」ということになるわけです。
すると、「父権型の医師―患者関係はもう古い」「今は情報型にしなければならない」ということになるのかというと、そんなことはありません。患者さんの中には年齢に関係なく、今でも父権的な関係を求める人もいます。また、医師がカウンセラーのように適切な情報提供を行う解釈型を求める人もいるし、医師が教師のような立場でいくつかの選択肢を用意してその中からどういう治療がいちばん最適かを検討する審議型がいいという人もいるでしょう。つまり、患者さんがどのようなタイプの医師と患者の関係を求めるかによって、医療側がどのような情報提供をするかがなされるべきだということになります。
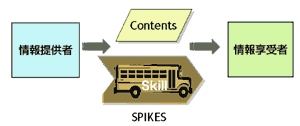
現在はあまりにも、情報提供技術を身につけていない医師が多すぎます。「あの先生はすぐキレるから、怖くてものが言えない」などという声が患者さんの間から出るようでは、医師として論外です。医師が情報提供をきちんとできる技術を身につけることが、がんだけでなく、すべての医療に求められます。患者さんも是非そのような認識を持ちながら、医療者と接してください。
| Informative 情報型 | Interpretive 解釈型 | Deliberative 審議型 | Paternalistic 父権型 | |
|---|---|---|---|---|
| 患者の価値観 | 固定・明確 | 未熟・軟弱 | 柔軟・可変 | 謙虚・慎遠 |
| 医師の義務 | 関連情報をすべて提示し患者の選択した治療を実行 | 患者の意志決定のプロセスに必要な情報を随時提供、最適な治療を提案し実行 | 複数の選択肢の中から適切類型を説明し実行 | 患者の意向に関わらず医師の信じる最善の治療を実行 |
| 患者の自主性 | 選択、制御 | 自己学習 | 納得 | 従属 |
| 医師の役割 | 知識・ 技術提供者 | カウンセラー 助言者 | 友人、教師 | 保護者 |


