- ホーム >
- 患者サポート >
- 医師と患者のコミュニケーション
医師と患者のコミュニケーション もっと上手にスムーズに!
医師の側から
「患者さんと医師のギャップを埋める努力を、医療側も始めています」

吉田和彦さん
患者さんの「自己決定権」を尊重しながら、リベラルな立場で治療を行っている東京慈恵会医科大学青戸病院副院長で、同大外科助教授の吉田和彦さんも、「医師と患者のギャップ」について、次のように話します。
「医療者にも患者さんにも幅があり一概には言えませんが、医療者と患者さんの間には図のような深い溝があり、コミュニケーションを難しくしています。まず、患者さんやご家族にとって病気は一人称、二人称であるのに対し、医師にとっては三人称。患者さんの主治医は一人でも、医療者は多くの患者さんを診なければなりません。患者さんは感情で、医療者は理性で対処する傾向がありますし、専門的な知識の量も違い、勉強している方でも偏りがある場合もあります」
それでも「このような溝を埋めるのもまた、コミュニケーションしかありません。医療者は、患者さんを三人称ではなく、なるべく二人称に近づけて考え、限られた診療時間内で不十分になりがちなコミュニケーションを補う努力も必要ですね」(吉田さん)
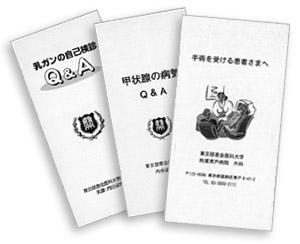
吉田さんが患者さんに配布している資料
乳がん、消化器がんなど年間150件程度の手術を行い、1000人を超す患者さんをフォローアップし、外来では3時間に50人以上の患者さんを診察するという吉田さんは、コミュニケーション不足を補うために、いくつかの方法を実践中だとか。初診や手術前の患者さんに口頭で説明するほか、検査の流れや予測できる病気の解説、標準的な治療法と補助療法のメリット、デメリット、治療の合併症などを優しく解説した冊子(写真左)を渡し、次の外来で質問してもらうそうです。
「初めてがんと知った患者さんは、頭が真っ白になってその場で理解できないことがあります。医学用語や検査機器の名称、例えば繊維腺腫とか嚢胞、シンチグラフィなんて、初めての患者さんには耳慣れない言葉ですよね。書面で渡しておけば、後で読み直すことができます。手術前の患者さんや緊急時の患者さんにはメールアドレスも教えて連絡を取り合うこともあります」(吉田さん)
患者さんが多くて忙しく、短い時間では説明しきれないという医師にも、可能な範囲でこれらの工夫をしていただけると、患者サイドの不満もかなり解消できるのではないでしょうか。
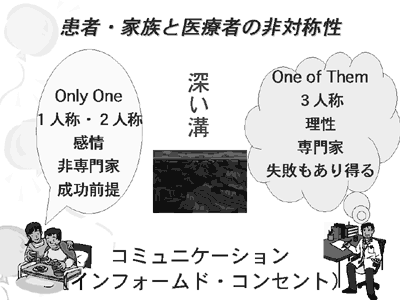
医師の側から
「がんという病気の難しさから、すべてを話しにくい面もあります」
「がんという病気の難しさから、すべてを話しにくい面もあります」
がんという病ならびにそれに対する治療の不確実性も、医師と患者の間に距離をつくる要因の一つ、と吉田さん。
「がんの治療というのは、機械を修理するのと違ってかなり不確実なサービスなんですね。乳がんなら7、8割は助かりますが、治療法や薬が進歩し、医師がいくらがんばっても100パーセントにはならない。同じ病期でも、現代医学では十分に解明されない遺伝子の変化が主な原因と考えられているタチの違いがあり、再発のリスクは異なるということを、患者さんにはなかなか伝えにくいものです」
裁判が多いアメリカでは、インフォームド・コンセントをせずに、最悪の事態が起こった場合、裁判で負ける可能性があるため、生存率、再発のリスク、余命など、患者にとって悪い情報を含めてすべてを伝えるそうです。日本でも、それに準じる施設や医師もあるようですが、医療者側も患者さん側も、怖いものには目を向けたくないのが心情です。とはいえ、がんには「不確実性がある」ということを頭の片隅に入れて、医師と話をする必要がありそうです。
「乳がんの場合、3年たてば多くは再発しないし、10年もたてばほとんど再発がなくなるのに、まだ油断できない、と強調する医師もいます。それでは患者さんはずっと不安ですよね。僕はウソをつかない主義ですが、患者さんをおどすより8割のよい情報を強調して人生をハッピーに過ごしていただきたいと思っています」(吉田さん)
「余命告知」についても、医師たちの感想を聞いてみました。
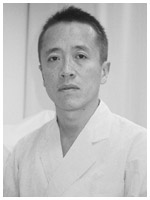
村上博史さん
消化器がん等の集学的治療に取り組み、患者さんとの信頼関係を大切に考えるという総合西荻中央病院外科医長の村上博史さんは、「がんの専門病院など、がん患者数の非常に多い病院では、病名、進行度、余命をドライにはっきり言う傾向があります。これはある程度やむを得ないでしょう。打つ手がなく、余命が限られている患者さんであれば、できれば楽観視して過ごしていただきたいものです。ただ、できる治療があるのに全く考慮もしないのであれば、放置すれば余命はどのくらいになるかを伝える必要があります」と話します。
吉田さんは「余命告知をする医師は、長く生きると伝えて早く亡くなってしまっては困るので、防御の姿勢から最悪のシナリオを予言したのでしょう。でも、余命はある程度の予測に過ぎず、本当のところはわかりません。末期でも、低空飛行で長生きする方も多いですよ。ポイントは医療はだれのためにあるか、ということ。僕は患者さんに安心と幸福を与えたい、再発してもそれはできると思います」
第三者機関からのアドバイス
「医師はもてなしの心を、患者さんは節度を」
患者中心の医療を目指し、14年前の発足以来、3万件の電話相談を受けているというNPO法人「ささえあい医療人権センターCOML」事務局長の山口育子さんは、医療者、患者さん双方に対して、次のように提案しています。
「月350件の電話相談のうち、医療不信についての電話が約3割ありますが、ほとんどは医療側と患者側のコミュニケーション不足が原因です。両者の意志疎通があったら、このような不信は生まれていないんですね。お互いに不信感をもって向き合ったのでは、決して医療者と患者さんのよい関係は生まれません。患者さんの気持ちを逆なでする医療者側の言葉を聞くにつけ、もう少し配慮ができないものかと思う一方で、患者さんの電話での話し方にも気になる点がいろいろあることを感じます。
たとえば、ポイントのない話を延々と続ける、感情的になる、唐突な質問をぶつけるなど。医療機関での短い診療時間に、このような話し方をしていたのでは、伝えたいことも伝わらないでしょう。患者さんもこの点を改善して賢い患者になり、医療者側と双方でお互いに人間対人間という基本に立ち返り、よりよいコミュニケーションをめざしていただきたいと思います。医師は“もてなしの心”を、患者さんは“節度”をもつことが大切ですね」
医師との間に深い溝があったとしても、患者の側も医師の現実を理解して、コミュニケーション能力を高め、近づく必要があるのかもしれません。


