- ホーム >
- 患者サポート >
- 医師と患者のコミュニケーション
医師と患者のコミュニケーション もっと上手にスムーズに!
検査結果を聞くコツは?
ある種のがんを除いては、手術後の定期的な検査で早く再発を見つけて早く治療を始めても、症状が出てから治療を始めてもトータルとしての生存期間は変わらない、と言われていましたが「たとえば乳がんに関しては、最近ではハーセプチンやタキサン系などの新しい薬剤が開発され、延命効果も認められていることもあり、手術後の遠隔再発を発見する目的での検査の意義に関しては医師の間でも意見が分かれています」と吉田さん。
いずれにせよ、患者さんにとって、検査結果を聞きに行く日は、不安な心境でしょう。乳がん体験者の会「虹の会」事務局の田中伸子さんは、「CTや血液検査の結果を聞きに行ったとき、医師に大丈夫、の一言で済まされると患者さんが不安になるので、ドクターにその根拠を簡単に説明していただければと思います。患者さんの情報は患者さん自身のものなので、不安なときは検査結果のコピーをお願いし、疑問があったらお聞きするとよいのではないでしょうか」
痛みなどの症状は具体的に伝える
「外来患者さんを診察する前は、今日は何を求めて受診されているのか、こちらは何を説明せねばならないかを考えてからお呼びします。前回何をお話ししたか覚えていないケースもありますが、それを補うのがカルテ記載です。直接病気と関係ないと思われる症状や変化も伝えていただくと、転移や副作用の早期発見につながることがあります」(村上さん)
苦痛や痛みなどの症状は、医師になかなかわかってもらえないものです。短い診療時間に上手に伝えるコツは?
「医師がいちばん知りたいのは (1) いつから (2)どこが (3) どのように痛むのか、(4)痛みの頻度や持続時間、(5)痛みが強くなっているか、(6) どうすると痛いのか、どうするとラクか、(7) 別の症状を伴うかなどです」(箕輪さん)
重い痛み、さし込むような痛み、長時間立っていると痛い、ご飯を食べた後に痛い、横になるとラク、吐き気や腹痛、せきが出る、しびれがあるなど、具体的に伝えることが大切です。
「医師は、病歴、自覚症状、診察、検査結果などを総合し、いろいろな可能性を消去しながら病状を診断するものです。患者さんから、肺転移では?骨転移では?と主観的な推測でものを言われると気分を害する医師もいるかもしれません。いつからどのような自覚症状があり、別の診療科でこう言われ、薬を処方されているなどの客観的な情報を伝えた上で、“肺転移が心配なんですけど”と伝えるとよいでしょう」(箕輪さん)
骨転移ではないか、と医師に尋ねたら「大丈夫」との返事だったのが、職場で倒れ、本当に骨転移だったとわかった例があります。患者さんも、ここが痛いから骨転移ではない���と思う、などと根拠を具体的に説明しながら検査を依頼する必要があるでしょうが、医師の側も、体の変化を敏感に感じ取る患者さんの声に耳を傾けていただきたいと思います。
治療法の相談をするときは
新しい治療法や、QOLを考えた治療法、代替療法などについて、主治医と相談したいときは、どのような伝え方をするとよいのでしょうか。
「新しい治療法がテレビで紹介されていたとか、新聞や雑誌に出ていた、などと言って切り抜きを持ってくる患者さんがおられますが、抵抗を感じる医師が多いと思います。医師はそれらの番組や記事を見ていないことも多いですし、医学雑誌などの専門誌に比べて一般誌の医療記事を軽視する傾向があり、プロとしてのプライドが許さない、と感じるわけですね。逆に言うと、それらの申し出を受け止めて、一緒に考えてくれる医師は、それだけで二重丸ではないですか?」(箕輪さん)
「どうしてもこの方法を試してみたい」という場合のアプローチ法として山口さんのアドバイスは――。
「こんな方法があると聞きましたが、どうでしょうと穏やかに、率直に聞いてみる。日常生活の中でも、相手と対話をするときにはいろいろな工夫をするのと同じように、権利だけを強い口調で訴えるのではなく、ソフトな言い方で相談するのがよいでしょう。医師に遠慮し、こびへつらうと対等な関係は生まれないので、相手が受け入れやすいような雰囲気で言葉を選びながら、病気に対しての真剣な姿勢を見せ、自分の思いを伝えることが大事です」(山口さん)
肺がん患者のBさんが、がんの増殖に関連するといわれる酵素COX2を阻害する薬剤について質問したところ、最初はムッとした顔をしていた主治医も、次の外来までに調べてくれていたそうです。また、小誌の記事を見せて、希望の治療を受けられたという患者さんもいます。主治医のキャラクターやそれまでの主治医との関係の作り方、伝え方などによっても違うのかもしれません。真剣に思いを伝えても受け入れてもらえないときは、セカンドオピニオンを求めるなどの方法を検討します。
セカンドオピニオンの求め方
「虹の会」の電話相談の中でも「セカンドオピニオンを求めたいが、主治医に言い出せない」という悩みが多いそうです。
「主治医のご機嫌を損ねるのではないか、今までの信頼関係が壊れるのではないか、というのがその理由ですが、実際に申し出てみると、うまくいくことが多いのも事実です。困ったときは、病院の相談窓口か、その医師のことを熟知している外来の看護師長さんに相談してみては? 当会では、セカンドオピニオン医の紹介もしています」と田中さん。
ドクターの本音をうかがうと――。「医師には自尊心の強い人種が多いので内心では、ムッとする人が多いと思います。患者さんもそれを敏感に感じるから、言い出せないところがあるのでしょう。僕だってまったくないと言えばウソになるし、どうしてそんな病院に行くのだろう、と思うこともありますが、患者さんの自己決定権を尊重して、申し出があれば気持ちよく資料を渡します。言い出せないときは、友人に医師がいるので聞いてみたいなどとお願いするのも一案だと思います」(吉田さん)
セカンドオピニオンを求めるときは、主治医の了解を取り、診療情報提供書(紹介状)、画像、病理検査のコピーなどの資料を借り、セカンド医に第2の意見を聞いたら、主治医のところにいったん戻ってそれを伝えるのが原則。セカンドオピニオンイコール転院と考えている方もあるようですが、治療の参考に第2の意見を聞くのが本来の目的です。
「セカンドオピニオンにはできる限り対応するのが最近のコンセンサスになっていますし、イヤな顔をする医師はある意味で自分の医療行為に自信がないわけですから、敬遠したほうがよいですね」(吉田さん)
COMLの「新・医者にかかる10箇条
(1) 伝えたいことはメモして準備
(2) 対話の始まりはあいさつから
(3) よりよい関係づくりはあなたにも責任が
(4) 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
(5) これからの見通しを聞きましょう
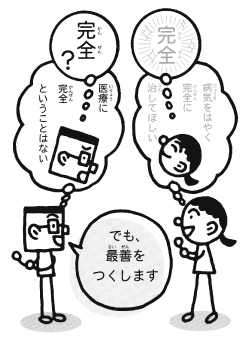
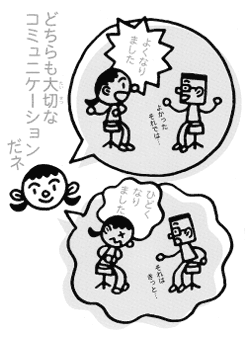
(6) その後の変化も伝える努力を
(7) 大事なことはメモをとって確認
(8) 納得できないときは何度でも質問を
(9) 医療にも不確実なことや限界がある
(10) 治療方法を決めるのはあなたです
ささえあい医療人権センターCOML(コムル)作成
医師にも患者さんにも必要なのは「人間力」。
ふとした一言で、信頼関係が深まることもある
医師と患者さんのコミュニケーションを豊かにするためには「お互いの人間力」も必要、と医療関係者のYさんは言います。以前は、医師の言葉や態度に一喜一憂する患者さんの心情を理解できなかったYさんも、がんになって初めて「その気持ちがわかった」とか。「外来の医師が、待合室の患者さんをマイクで呼ぶときに、〇〇さん、〇〇さん、と早口で繰り返すと、隣の老夫婦が“今日は先生、ご機嫌悪いのかね。3つ聞こうと思ってたけど、1つにしようか”なんて話しているんです。医師は待合室の患者の心理など考える余裕はないでしょう。僕は医師に情など求めない自立した患者になれると自信をもっていましたが、いざ患者になると、その老夫婦と同じ気持ちなんですね。診療中に主治医が“僕もトシだからお酒を控えているんですよ”などと話してくれると、人間同士の触れ合いができたみたいで嬉しくなる。やはり、医師も患者も単なるコミュニケーションスキルではない人間力が大切、という気がします」


