患者の不安や痛みを軽減する音楽療法 手術前後のQOLアップが実証された!
不安や痛みの変化を、生理的・心理的指標で測定。
音楽療法後は、不安、痛みの尺度が有意に下降
では、患者さんの不安や痛みが音楽療法を行う前後でどう変化するのでしょうか。体の変化を表す血液中の副腎皮質ホルモン(コルチゾール)値、不安の状態を示す数値(STAI)や痛みを表す値(VAS)などを測定した結果は「術前、術後とも、音楽療法を行った後は、不安を表す数値、痛みを表す数値とも有意に下降しました。音楽療法は、手術前後の不安減少、疼痛緩和に大きな役割を果たしたと考えられます(図(1)(2)(3)(4))」。
血圧は、手術前は歌った後、わずかに上昇しましたが、手術後は有意に下降しました。血圧が100以下の方は、歌った後、わずかに上がるのですが、160以上の高血圧の方は、歌った後に下がるので、音楽療法は血圧を調節する働きもあると考えられます。また、ストレスを示す唾液中の副腎皮質ホルモン値は、手術前の音楽療法後はわずかに上昇しましたが、手術後の音楽療法後は下降しています。ただ、個人差が激しく、ばらつきがあるので、有意差があるとはいえないそうです。
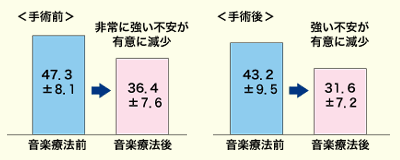
[図(2) 痛み(VAS)の変化]
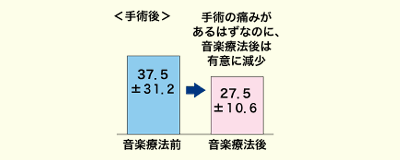
[図(3) 最大血圧の変化]
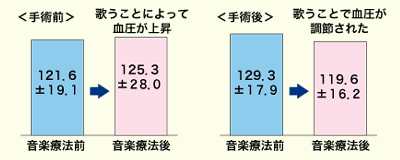
[図(4) コルチゾール値の変化]
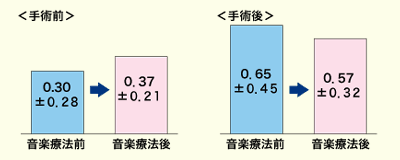
「手術後、皆さん、痛いと言いながらも、歌った(あるいは聴いた)後、痛みの数値が低くなっているのは注目に値します。痛みは、物理的な要素だけでなく心理的な要素も関係するもの。おなかが痛いときに旧友から電話がかかってきて、話に夢中になっていたら痛みを忘れた、ということはよくあります。それと同様に、痛みを感じる神経のゲートに流れる情報の量は一定なので、そのゲートに音楽が入ってくると痛みの量が減る、と推測できます。これはゲートコントロール理論と呼ばれています(図(5))」
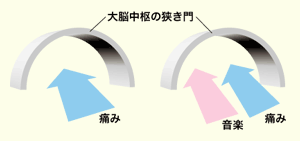
大脳中枢の情報処理能力には限界があり、1度に多くの入力はできないため、痛みの感覚と他の入力信号が競合状態になる。好きな音楽などの情報がゲートに入ってくると、痛みの知覚は結果的に弱められ、私たちの注意は音楽の刺激に向かう。(Jacox 1977)
音楽療法の可能性は?
がん闘病中のQOLを高め、免疫力アップも期待できる
「“なじみの歌を歌う”という音楽療法は、がんの手術前後の不安や痛みを軽減し、QOLを高めることが確認できたので、これから手術を受ける患者さんにお勧めできますね。手術後の痛みを減らすだけでなく、退院後や、闘病中の落ち込みや不安を防ぐ上でも効果が期待できますし、免疫力を高める可能性もあるのではないでしょうか。
今回は、対象者が手術前後の患者さんだったため、身体への影響を配慮して血液検査はしていませんが、高齢者の場合は、音楽療法後、免疫力の指標となるNK細胞が有意に高まっています。今後の研究によって、がんの患者さんの免疫活性への影響などもだんだんにわかってくるでしょう」
この研究では、セラピストとともに“なじみの歌”を歌い、回想するという方法がとられていますが、家族とともに、または自分1人で、好きな歌、歌いなれた歌を歌うことも推奨できる、と高橋さん。
「好きな歌は、個人個人によって違います。がん治療でもオーダーメイド医療が目標とされる今、音楽療法も個人差を大切にする視点が必要ですね。聴いたこともない、なじみのない曲を聴くより、ご本人の好む歌を歌ったり、聴いたりする方法がもっと活用されてよいと思います。心理療法の効果には、技法の要素は15パーセント程度しか影響しません。
患者さんの自我の強さは40パーセントとより大きく関係するとされていますから、手術前後も、退院後も、ご家族でも友人でも巻き込んで一緒に歌ったり、1人で涙ぐみながら歌ったりして、自らを解放し、感情を発散させることは、QOLを高める上でもプラスになるといえますね」
手術室や病室などで、好きな歌を聴いたり、歌ったりできるような環境の整備も望まれます。
また、高橋さんは、歌を歌うことの利点として「呼吸調節機能」がある、と付け加えます。
「歌を歌うと、長く息を吐くことになり、自動的に自然に深く息を吸い込むことができるので、リラクゼーションの効果が生まれます。歌を歌うのは抵抗がある、という方は、古池や~、かわず飛び込む水の音オ~~、とか、笑う門には福きたるウ~~、などと言葉に出しながら、息を長く吐き伸ばす呼気コントロール法を試してみるのも効果的。俳句でなくても、春が来たア~~、でもてんぷらご飯ン~~、でもなんでもいいんです」
これなら、難しいこと言わずに、今すぐ、どこにいてもできますね。今、入院中で、病室が大部屋、という場合は、待合室や廊下などでどうぞ。気分転換にもなりますから、早速試してみましょう!
なお、専門の音楽療法士に音楽療法を受けたい、どんな歌を歌ったらよいか電話相談をしたいなどの希望がある方は、編集部にご連絡ください。
『認定音楽療法士の臨床に関する調査』によれば、対象者は高齢者領域が35.3パーセントで1番多く、児童領域は32.9パーセント、成人領域は25.8パーセント、その他、総合病院が6パーセントとなっています。その内訳について、厚生科学研究費補助金、傷害保険福祉総合研究事業『わが国の教育・福祉領域における音楽療法の実態に関する研究』によると、高齢者では認知症、脳血管障害、脳神経障害の順であり、児童領域(障害児・者)の内訳が1番多く、自閉症、重複障害、肢体不自由の順になっています。
また、成人では統合失調症、うつ病、ボーダー、神経症、心身症、摂食障害、嗜癖という順になっています。2000年の調査では、音楽療法の対象者の約50パーセントが障害児・者でしたが、2004年の調査では、高齢者が1位になっています。 わが国は高度高齢社会に到達して、ますます高齢者が増加してくると思われます。最近では医療現場での音楽療法士の数も増え、緩和ケア病棟、ホスピスでの音楽療法が行われるようになってきています。
| 高齢者領域 | 35.3% | 認知症 脳血管障害 脳神経障害 |
|---|---|---|
| 児童領域 | 32.9% | 知的障害 自閉症 重複障害 肢体不自由 |
| 成人領域 | 25.8% | 統合失調症 うつ病 ボーダー 神経症 心身症 摂食障害 |
| その他 | 6.0% | 総合病院 |
同じカテゴリーの最新記事
- がん治療中の食欲不振やしびれ、つらい副作用には漢方薬を使ってみよう!
- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること
- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が
- ハイパーサーミア(がん温熱療法)とは――抗がん薬や放射線療法の標準治療との併用で効果
- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用
- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法
- 香りで不快な症状を緩和し、心身を癒すアロマトリートメント
- 相互作用を見極めるためサプリメントは1種類を慎重に
- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療


