温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み
精神的に楽になる治療法
こうした治療が奏効した具体例も見ておこう。昨年5月、進行卵巣がんが見つかった73歳のある女性は、病院で手術を勧められたが拒否。西出病院でタキソール(一般名パクリタキセル)、ブリプラチン(またはランダ、一般名シスプラチン)の少量2剤併用療法に、週1回40分の温熱療法を加えた治療を行っている。
初診時の腫瘍は直径5センチ。卵巣がんのマーカーとなるCA125の値は正常の37以下を大幅に上回り274に達していた。それが併用治療で抗がん剤治療2クールを終えた時点で腫瘍は直径2センチに縮小、腫瘍マーカーも21と正常範囲内に減少する。
もっとも、この女性はその後、抗がん剤の副作用を恐れたために治療を中断、温熱療法単独で治療を行ったところ、腫瘍マーカーは再び236にまで上昇している。そこで、抗がん剤治療をイリノテカンの少量投与に変更して、温熱療法を続けたところ、2クールの抗がん剤投与終了後に腫瘍マーカー値はまた61に減少しているのである。
この女性は現在も週1回の抗がん剤治療と温熱療法を行っているが、副作用もなく、がんが見つかる前と変わらないQОLを維持しているという。
オスタペンコさんは、こうした温熱治療の効果の中でも、とくに多くの人に成果が現れやすいのがQOLの改善だという。西出病院ではこの治療を受けた人たち32人を対象にアンケートを実施しているが、その結果、53パーセントが「精神的に楽になった」と答え、疲れやだるさなどの身体症状、痛みについても、それぞれ38パーセントが改善したと回答している。これは患者にとっては見逃せない効果ではないだろうか。
温熱療法に休眠療法を組み入れた

岡山県岡山市にある岡村一心堂病院
「当院を訪れるがん患者さんは、他病院で治療の術なしとさじを投げられたがん難民と呼ばれる人ばかり。そうした人をどう救っていくか。そのためのひとつの試みとして8年前に温熱療法を導入したのです」
こう語るのは、岡山県にある岡村一心堂病院理事長の岡村一博さんである。最初の1年は抗がん剤や放射線治療もできない末期患者に温熱療法だけを実施していたが、目立った効果が現れないばかりか、逆に急激に腫瘍が増大するケースもあった。
しかし2年目からは、放射線治療とともに、金沢大学助教授の高橋豊さんが考案した「休眠療法」を組み合わせることで、効果が現れ始めたという。休眠療法は、強い副作用を出さないように(グレード2まで)抗がん剤の投与量を調節してがんを眠らせる治療法だ。現在までの治療件数は約400例に達しているという。
「ある抗がん剤のように分割投与すると、副作用ばかりが重くなる薬剤もある。そうした一部の例外を除けば、本来の使用量の50~80パーセント程度の抗がん剤と温熱療法を組み合わせて治療しています。そのことで副作用を抑えながら、がんをコントロールできるケースも少なくないのです」
常識を覆す週5日の連続治療績
この岡村さんの言葉からもわかるように、岡村一心堂病院の温熱療法の手法は西出病院のそれとは少々様相を異にしている。抗がん剤治療との併用の場合に抗がん剤の量を抑えるだけでなく、原則として温熱療法そのものも、鈴鹿医療短期大学での動物実験の報告を基に週5日の連続治療を基本としている。
また放射線治療との併用では、温熱療法だけでなく活性酸素の作用でがん細胞を叩くとされる高気圧酸素の吸入治療も、並行して行われることが少なくない。「温熱療法もそうですが高気圧酸素による治療も明確なエビデンス(根拠)があるわけではありません。しかし副作用がなく患者さんにプラスになる可能性がある治療はどんどん取り入れていきたいのです」(岡村さん)
もっとも、これは同病院に限らないが抗がん剤の使用量やラジオ波の照射時間、さらにこの治療法が適用されるがんの種別についても明確な基準が定められているわけではない。患者の容態変化をみながら、その時々の状況に応じて、手探りで治療内容を決定しているのが実情だ。とはいえ、結果として効果はあがっていると岡村さんはいう。
転移のある非小細胞がんに対する治療データ
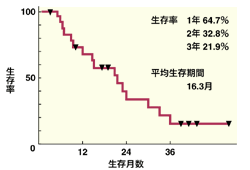
具体的に治療データを見てみよう。
岡村一心堂病院では2000年4月から2004年4月にかけて、その間に来院した肺、脳、肝臓など遠隔転移のある非小細胞がん患者24人を対象に、抗がん剤の休眠療法に温熱療法を加えた温熱化学療法を実施、予後を調べている。
具体的な治療法は温熱療法の30分前に副作用予防の点滴を実施、解熱鎮痛のためにインダシン座薬を挿入する。そうして平均40分のラジオ波照射中に20ミリグラム/平方メートルと少量のカンプト(またはトポテシン、一般名イリノテカン)を点滴投与するというものだ。温熱療法の回数は週3~5回で、そのうち月、火、水曜日の3日間、化学療法が行われる。
そうした治療の結果、従来の治療に比べて腫瘍の縮小という点では効果は見られなかったが、生存率では明確な差異が現れている。たとえば他の施設で行われた同じ4期の非小細胞肺がん患者80人を対象にイリノテカンを用いた治療では、平均生存月は10.5カ月だが、同病院の温熱化学療法では16.4カ月に達し、1年生存率も前者の36.4パーセントに対し64.7パーセントと大幅な上昇がみられているのだ。
もちろん、この場合も比較した試験ではなく、この結果だけから温熱療法の効果を云々することはできないだろう。しかし延命に関して可能性が感じられるのも事実ではないだろうか。
同じカテゴリーの最新記事
- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用
- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法
- 肝がんや膵がんで効果が現れたというが、まだ試験段階 温熱・免疫療法の併用は標準治療の効果を高めるか
- これだけは知っておきたいがん温熱療法の基礎知識 放射線や抗がん剤との併用で効果。何より副作用がないのが利点
- 海外におけるがん温熱療法の現況 子宮頸がんや乳がんで好成績。見直される温熱療法
- 注目されるマイルドハイパーサーミアという新しい温熱療法 低めの加温で放射線、抗がん剤の効果を一層高める
- 動脈塞栓で温度を高めるというユニークな方法で効果を上げる 肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の効果
- 温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み
- 悪性胸膜中皮腫、軟部組織肉腫に対する温熱化学放射線治療 抗がん剤、放射線と天秤にかけ、より効果が望めるがんに限定して行うべき


