温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み
温熱化学療法で腫瘍が縮小
岡村一心堂病院では入院治療中の患者2名から話を聞くことができた。
その1人、大阪府在住の66歳の男性患者は、今年の1月、胃の不調による食欲減退から、近隣の病院でCT検査を受けたところ膵臓に腫瘍が発見された。その後、大阪の大学病院で精密検査を受診、その結果、症状は周辺のリンパ節や肝臓への転移が判明し、担当医から延命治療以外に術はないと告げられる。
担当医の言葉に納得できない男性は、独自に情報を集め温熱療法を発見、今年の3月、治療相談に来たその日に入院する。翌日から温熱療法とジェムザール、さらに放射線治療を加えた温熱化学放射線治療が開始された。放射線治療と温熱療法は週5日行われ、木曜日の温熱の治療中にジェムザールが点滴投与される。その時点での膵臓の腫瘍の大きさは直径60ミリ、腫瘍マーカーのCA19-9の値は正常値の37をはるかに上回り570に達していた。
それが前述の治療により、5月ごろから症状が改善し始めた。体調がよくなるとともに腫瘍マーカーが正常値近くにまで減少する。さらに7月初めに行われた検査では、腫瘍マーカーは正常範囲内にまで減少し、PETによる検査でも、腫瘍が直径10ミリに縮小していることがわかった。そこで7月中旬に男性は同病院を退院、現在は週に1度来院して1泊2日の治療を受けている。
「7、8割方は命を落とすといわれる末期の膵臓がんで、これだけ症状が改善していることが自分でも信じられない。もちろん予断は許されないが、これからの治療にも希望を感じています」
と、その男性は語る。
| 症例1 | |
|---|---|
| 年齢、性別 | 55歳 男性 |
| 病期 | 4b期(肝転移、大網転移) |
| 治療経過 | 放射線治療、温熱化学高気圧療法、胃空腸バイパス術 |
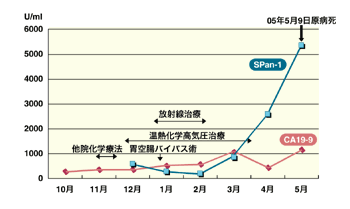
| 症例2 | |
|---|---|
| 年齢、性別 | 58歳 男性 |
| 病期 | 4a期(肝転移、大網転移) |
| 治療経過 | 放射線治療、温熱化学高気圧療法、胆管ステント留置 |
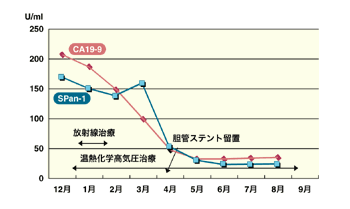
もう1人、静岡県浜松市の60歳の女性肺がん患者のケースも見ておこう。この女性は3年前に浜松市の医療機関で肺がんの疑いが指摘されたものの、容態に変化がないために、その後、慢性肺炎に診断が変更されていた。ところが今年の5月、胸や背中が激しく痛むことから、同じ医療機関で検査を受けたところ、第1胸椎、第2胸椎に転移が進んでいる末期の肺がんと診断されている。その医療機関で大用量の抗がん剤治療を打診され、副作用を危惧したことから、すぐに転院している。
岡村一心堂病院での治療は週5回の温熱療法と少量のイリノテカン投与。1カ月後には治療効果が現れ、咳や痰などの症状がピタリと治まった。現在、肺の原発巣は増悪が抑えられており、これからは転移部分の温熱療法を始めるという。
「髪が少々薄くなりましたが、それ以外に抗がん剤の副作用はありません。体が楽な状態が続いているだけでもありがたい」と、その女性は治療を受けた感想を語る。
ここでとりあげた2人の患者は現在も治療を継続中で、温熱療法の効果を軽々と云々することはできない。 しかし少なくとも現時点では治療がうまく成果をあげていることは事実だろう。
| 年齢、性別 | 65歳 男性 | 61歳 男性 | 57歳 女性 |
|---|---|---|---|
| 組織分類 | 扁平上皮がん | 腺がん | 腺がん術 |
| 転移 | 肺、脳、肝臓 | 肺、脳 | 肺、脳 |
| 治療法 | 温熱療法 216回(週4回) 温熱化学療法 29回(週3回) ガンマナイフ(脳転移) | 温熱療法 113回(週5回) 温熱化学療法 45回(週3回) ガンマナイフ(脳転移) | 温熱療法 390回(週5回) 温熱化学療法 101回(週3回) ガンマナイフ(脳転移) |
| 治療後の状態 | CR(完全寛解) | PR(部分寛解) | PD(進行) |
| 結果(生存期間) | 不明で死亡(21カ月) | 生存(38カ月) | 生存(36カ月) |
患者に負担が少ない治療法
ここまで見てきて温熱療法という治療法についてどんな印象を持たれただろうか。
ひとついえるのは、温熱療法は新しい可能性を秘めた治療法であることだ。ただ、現在、個々の症例を集めている段階で、また効果のあるがんの種別も不透明だ。
さらに付け加えれば、とくに抗がん剤との関係では、効果を高める増感作用のしくみも色々考えられるので、そのために治療法そのものも確立されていない側面もある。そのことは西出病院と岡村一心堂病院での治療手法の違いを見ても明らかだろう。現時点ではすべてが手探りで、経験主義に基づく治療法といえるかもしれない。
しかし、それでもなおこの治療法にある可能性が感じられるのも事実だ。
それはひとつには現実にこの治療法を受けた患者が、治癒とはいかないまでも、延命、QOLの向上などの治療成果を享受していることだ。そしてもうひとつは、この治療法を受けることによって患者に生じる負担の小ささだ。
体温の上昇にともなう熱傷以外には、原則的に副作用は生じない。また、この治療は保険が適用されるため経済面でも負担はそう大きくない。たとえば西出病院の場合で1カ月の治療費は3万円程度だ。
これだけでがんが根治するものだと期待していたら、失望を感じるかもしれない。しかし、たとえば、他に治療の術がない進行がん患者が、がんとともに生きるための方策と考えれば、考慮に値する治療であることは間違いなさそうだ。
もっとも前にいったように現段階では、治療法も確立されていないのが実情だ。もしこの治療を受けるのなら、いくつかの治療機関で事前にじっくりと話を聞き、自らのがんや身体状況との相性を考えることも大切だろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用
- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法
- 肝がんや膵がんで効果が現れたというが、まだ試験段階 温熱・免疫療法の併用は標準治療の効果を高めるか
- これだけは知っておきたいがん温熱療法の基礎知識 放射線や抗がん剤との併用で効果。何より副作用がないのが利点
- 海外におけるがん温熱療法の現況 子宮頸がんや乳がんで好成績。見直される温熱療法
- 注目されるマイルドハイパーサーミアという新しい温熱療法 低めの加温で放射線、抗がん剤の効果を一層高める
- 動脈塞栓で温度を高めるというユニークな方法で効果を上げる 肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の効果
- 温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み
- 悪性胸膜中皮腫、軟部組織肉腫に対する温熱化学放射線治療 抗がん剤、放射線と天秤にかけ、より効果が望めるがんに限定して行うべき


