抗がん剤、放射線の副作用を軽減し、QOLを高める 漢方薬の症状改善力を見直す
直接がんを攻撃しないが、全身状態を改善
2005年3月に開院したばかりの癌研有明病院(東京都江東区有明。700床)消化器センター内科副部長の星野惠津夫さんは、がんの症状の緩和を目的に漢方薬を処方して効果を上げている。星野さんは、注腸造影検査件数で1万例を超える腸の病気の専門家だが、漢方医学にも精通し、これまでにがん患者の多くに漢方薬を処方してきた。
星野さんは「がん患者は『がん証』ともいうべき証を呈しており、これは漢方補剤が有効な状態である」と考えている。
「漢方補剤は、がんに直接作用するのではなく、患者さんの消化器機能をサポートして栄養状態を改善すると同時に、身体機能を調整して免疫系の働きを賦活させます。近代医学ではがんを直接攻撃しますが、その治療の副作用によって、患者さんの全身状態は低下します。漢方補剤には直接がんを攻撃して排除する作用は期待できませんが、患者さんの全身状態を改善して、間接的に抗腫瘍効果を発揮すると考えられます。たとえ、がん自体の進行を抑制できなくても、患者さんの全身状態の改善は期待できます」(星野さん)
漢方補剤の代表的なものが、十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、加味帰脾湯、清暑益気湯の5つだ。5つの漢方補剤は、人参、黄耆、当帰、甘草の4つの生薬をベースに、さらに5~10種類の生薬をプラスして構成されている(表2参照)。星野さんは、がん患者の症状に応じて、5つの漢方補剤を使い分けている。
「がん患者さんで、気力・体力ともに低下して、全体的に衰えているときには初めに十全大補湯を用います。気力・体力の低下と同時に、咳や息切れなどの呼吸器の症状があるときは人参養栄湯を処方します。補中益気湯の『中』とは消化器のことで、『気』とは気力のことです。つまり、補中益気湯は、便秘や胃もたれがあって消化器の働きが悪く、うつ状態で元気のないときに有効です。
加味帰脾湯は、とくに貧血が強く、不眠や健忘などの精神症状が目立つときに用います。清暑益気湯は、夏の暑い季節にだけ、これらの補剤に替えて用いる漢方補剤です」(星野さん)
| 漢方薬 | 構成生薬 | 適応 |
|---|---|---|
| 十全大補湯 | 人参、黄耆、当帰、甘草、朮、茯苓、地黄、*川キュウ、芍薬、桂枝 | 気力・体力ともに低下して、全体的に衰えているときに用いる |
| 人参養栄湯 | 人参、黄耆、当帰、甘草、白朮、茯苓、地黄、芍薬、 桂枝、遠志、陳皮、五味子 | 気力・体力の低下とともに、咳など呼吸器系の症状があるときに用いる。放射線障害を予防するときによく使用する |
| 補中益気湯 | 人参、黄耆、当帰、甘草、白朮、陳皮、大棗、柴胡、 生姜、升麻 | 消化器系の働きが落ちて便秘、下痢などの症状があり、不眠やイライラするときに用いる |
| 加味帰脾湯 | 人参、黄耆、当帰、甘草、白朮、茯苓、酸棗仁、 竜眼肉、遠志、大棗、生姜、木香、柴胡、山梔子 | うつ状態など精神症状が前面に出たときに用いる |
| 清暑益気湯 | 人参、黄耆、当帰、甘草、白朮、麦門冬、陳皮、 黄柏、五味子 | 真夏の食欲がないときに用いる |
[漢方薬が有効ながん患者の症状]
| 全身状態 | 全身倦怠感、食欲不振、冷え、しびれ、頻尿、口渇、しゃっくり |
| 消化器症状 | 吐き気・嘔吐、便秘、下痢、腹痛、腹部膨満、口内炎、口内乾燥 |
| 精神状態 | うつ、無気力、不安、不眠、焦燥 |
| 難治性疼痛 | 神経原性の疼痛(帯状疱疹痛など) |
| 抗がん治療 (手術・抗がん剤・放射線) の副作用 | 全身倦怠感、食欲不振、術後の気力・体力の低下、神経損傷による知覚異常、癒着性イレウス(腸閉塞)、吐き気・嘔吐、下痢・便秘、日和見感染、放射線腸炎・膀胱炎 |
胃がんの肺移転に漢方薬治療で8年生存
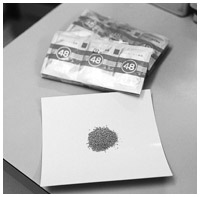
十全大補湯
星野さんは、5つの漢方補剤の中から1つを選択する。その第1選択の漢方補剤を2週間から1カ月間服用してもらって症状を見る。血液検査で栄養状態や免疫力のマーカーもチェックする。
「それぞれの患者さんに最も適した漢方補剤を選びます。さらに、冷え、痛み、しびれ、のどの渇きなど、他の症状を伴う場合にはそれに適した漢方薬をプラスして、併用します。通常、2~3回受診していただくと患者さんの状態に合った漢方薬が決まります」と星野さん。
第1選択の漢方補剤として、最もよく用いるのは十全大補湯だという。前述したEBM委員会でも高い評価を得ている漢方補剤だ。星野さんは、再発・進行がん20数例に対して漢方薬による治療を行っている。そのうちから、十全大補湯を用いて治療した2つの例を紹介しよう。
Aさんは、胃がん(悪性度の高い印鑑細胞がん)で胃切除術を受けたが、がんは粘膜下層に浸潤したがんで、リンパ節転移を伴っていた。1年間、経口抗がん剤を服用したが、術後2年目、44歳のときに検診で多数の肺転移が見つかった。
気力・体力ともに低下していたため、漢方エキス剤の十全大補湯を処方された。年齢が若かったため、常用量の倍量の1日15グラムを朝・昼・晩の食前に湯飲み茶碗に入れ、お湯を注いで溶かして飲んだ。
十全大補湯を飲むたびに全身が熱くなり、その後にだるさがしばらく続いたが、2週間後、CT上で肺転移の縮小傾向を認めた。6週間後にはさらに縮小し、3カ月後には指摘が難しいほど縮小した。結局、Aさんは約4年間、十全大補湯を飲み続けた。その後の経過も順調で、肺転移してから8年目の現在も元気だという。
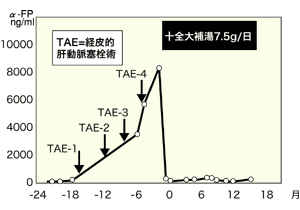
Bさんは、42歳のときC型慢性肝炎になり、肝硬変に移行した。さらに62歳のときに肝がんと診断されて、肝動脈塞栓術(TAE)を4回受けた。64歳で4回目の入院をしたときに多発性の肺転移が見つかり、抗がん剤のミフロール(一般名カルモフール)が投与されたが、食欲不振の副作用のため数回で服用を中止した。抗がん剤を中止してから1カ月後、食欲不振と全身倦怠感に見舞われて、気力・体力ともに落ちていたため、十全大補湯を処方された。服用を始めて2カ月後、肝臓がんの腫瘍マーカー(αフェトプロテイン)が急激に低下し、その後も低い状態で推移した(図1参照)。残念ながら服用を始めて18カ月後、腹水がたまり、死亡したが、解剖の結果、肺と肝臓にがんは見つからなかった。
「十全大補湯などの漢方補剤の処方によって、さまざまな症状が改善されます。食欲が出てきて、精神状態もよくなり、その結果として免疫力も高まります。腫瘍マーカーが低下してくる患者さんも少なくありません。その中にはAさんやBさんのように、症状の緩和だけでなく、がんそのものが縮小するケースもあります」と星野さん。
治療法が無くなった患者こそ漢方薬治療を
現在、星野さんは、抗がん剤治療や放射線治療を受けていて、再発・進行がんなどで西洋医学の標準治療では治療法の見つからない場合に、漢方薬による治療を行っている。「抗がん剤や放射線の治療によって骨髄の造血機能が低下し、白血球数や血小板数の減少などの副作用がよく現れます。そのような場合に漢方補剤を用いると、骨髄抑制が軽減されるため、抗がん剤や放射線の治療を最後まで受けることが可能になります」(星野さん)
転移・再発をきたした進行がんの治療現場では、手術・抗がん剤・放射線の3つの治療法の効果が得られなくなったとき、「もう治療法はない」と医療スタッフ側は早く治療をあきらめてしまうことが多い。一方、がん患者や家族はあきらめ切れず、「ほかに何か治療法はないか」と健康食品などの代替療法を必死に探し求めて、利用を始める。中には100万円以上の費用をかけて新興宗教的な治療に走る患者もいる。
「漢方補剤を用いた治療は、手術・抗がん剤・放射線の3つの治療法が奏効しなくなったら開始すべきです。しかし、理想的には、がんと診断されたときから漢方補剤によるがん患者さんの全身管理が必要なのです。うつ状態で生気のない状態で治療を受けてもよい結果は得られません。がんが引き起こすさまざまな心身の症状に漢方補剤は有効です。スタンダードながん治療の効果を高める役割も期待できます」と、星野さんは強調する。
日本東洋医学会・EBM委員会が推奨しているように、漢方補剤には化学療法や放射線治療の副作用を防止し、延命効果があるらしいこともわかりつつある。しかし、現在がん治療の現場では漢方補剤はあまり評価されておらず、出番が少ないようだ。漢方補剤だけでがんを治すことは難しいかも知れないが、手術・化学療法・放射線治療というがん治療の3つの柱に漢方補剤を併用することで、これまでにない治療効果が生まれる可能性は大いにある。
同じカテゴリーの最新記事
- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること
- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が
- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療
- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効
- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を
- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!
- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮
- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減
- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる


