- ホーム >
- 検査・治療法 >
- 代替医療・統合医療 >
- サプリメント・健康食品
サプリメント選びのポイントは臨床試験を行っているかどうか サプリメントはがん治療に役立つか? 最新徹底検証
1カ月以内に効果が実感できるか確認する
大野さんは、臨床試験を行っていないサプリメントは有効か無効かの判定がついていないだけで、「効果がないと誤解してはいけない」と強調する。ただし、「効果が実証されていない以上、使用には慎重になるべきだ」とも力説する。
「今のところ、がんの3大療法に取って替わる“ 代替医療” はありません。サプリメントの役割はあくまで“ 補完医療” に過ぎないのです。くれぐれも3大療法を拒否して、サプリメントに頼ることはしないでください」
その前提でサプリメントを使いたい場合、どうすればいいのだろうか。
「まず、使う前に、そのサプリメントが本当に自分にとって必要かどうか、よく調べ、考えること。売り手のセールストークに惑わされてはいけません。どんなに理論がすばらしくても、実際に効果があるのかどうかは臨床試験を行わなければわかりません。
また、情報収集をするとき、サプリメントの有効性のほかに、副作用や他の薬との飲み合わせなどにも注意を払う必要があります」
サプリメントの有効性や安全性については、国立健康・栄養研究所のサイトなどで調べられる。気をつけたいのは、「学会発表で好評を博す」「医学博士が推薦」といったサプリメントの宣伝文を鵜呑みにしてしまうこと。
「重要なのは、第3者によって評価された学術論文に掲載されていることです。たとえば、世界的に知られる臨床系医学誌としては、『ランセット』『ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』『JAMA』(米国医師会誌)『JCO』(米国臨床腫瘍学会誌)などがあります。これらに掲載された論文の内容は一応信用してもよいのですが、論文の内容は専門的で、患者さんにとってはわかりにくいこともあるでしょう。その場合は医師に質問するようにしてください」
では、サプリメントを使う際に注意すべきことは何か。
「試すときは1種類ずつにしてください。使う期間についても1カ月程度にすること。サプリメントがもし有効なら、1カ月以内に何らかの実感が得られるでしょう。それが使い続けるかどうかを決める目安になると思います」
失望の大きかったセレンの臨床試験
2010年6月のASCO(米国臨床腫瘍学会)で、サプリメントの研究者たちを大いに落胆させる研究が発表された。
非小細胞肺がん約1500例を対象にした比較試験の結果、ミネラルの1種であるセレンには抗がん効果が認められなかった。無増悪生存期間(がんが悪化しなかった期間)も5年生存率(再発を除く)も、セレン摂取群よりプラセボ摂取群のほうが上回った。
「セレンは、臨床試験において抗がん効果が証明されると期待された最右翼のサプリメントでした。それが無残な結果に終わったのです。がんに対するビタミンA・C・Eの効果にも疑問符が付いています。食物繊維の大腸がん予防効果にも否定的な結果が出ました。皮肉にも臨床試験によって、がんを直接的に改善するというサプリメントの“ 抗がん効果” は次々と打ち消されています。もはや、エビデンスのある抗がんサプリメントは現れないかもしれません」
こう嘆息するのは、銀座東京クリニック院長の福田一典さん。現在、漢方薬を中心としたがんの補完代替医療に取り組み、サプリメントも積極的に治療に取り入れている。
期待されるメラトニンの研究
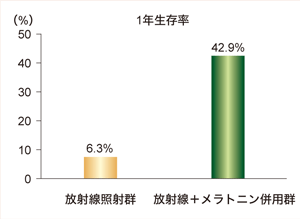
16例を放射線単独照射群、14例を放射線+メラトニン(1日20mg摂取)併用群に振り分けた
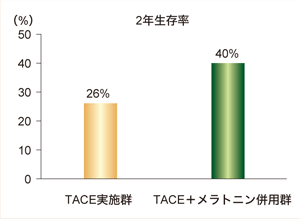
(Hepatobilliary Pancreat Dis Int,2002)
100例は手術不能だったため、TACE(肝動脈化学塞栓療法)を実施。50例をTACE単独実施群、50例をTACE+メラトニン(1日20mg摂取)併用群に振り分けた
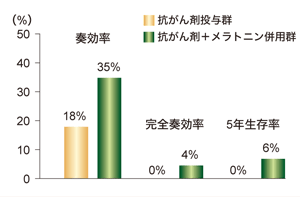
(J Pineal Res, 2003)
50例を抗がん剤単独投与群、50例を抗がん剤+メラトニン(1日20mg摂取)併用投与群に振り分けた
抗がん効果を狙ったサプリメントは旗色が悪い。しかし、その中で希望の星と目されているものの1つが「メラトニン」だ。
「メラトニンは、体内時計の調整を担う脳内ホルモンとして知られ、その合成剤が不眠や時差ボケを解消する薬として米国などで普及しました。ところが、メラトニンに抗がん作用や免疫強化作用などのあることがわかり、抗がんサプリメントとして一躍脚光を浴びたのです」
メラトニンは、サプリメントの中では臨床研究も進んでいる。国立健康・栄養研究所のサイトでも、複数の臨床試験があり、「固形がんへの有効性が示唆される」と示されている。たとえば、次のような報告もある。
転移性の進行非小細胞肺がん100例を対象とした比較試験では、抗がん剤単独投与群の奏効率(がんが縮小した割合)は18パーセント、5年生存率は0パーセントだったのに対し、メラトニン+抗がん剤併用投与群はそれぞれ35パーセント、6パーセントだった。
「メラトニンは、臨床試験を行っている研究機関が一部に偏っているのが玉に瑕です。ただし、さまざまな研究機関で臨床試験が行われ、確固たる評価を得られれば、抗がんサプリメントとして、世界中で認められる可能性もありますね」
また、メラトニンは、進行非小細胞肺がん70例を対象とした比較試験でも、悪液質の割合を有意に低下させた。
福田さんによれば、がん治療にメラトニンを活用する場合、1日20ミリグラムを服用するのが普通だと言う。
「メラトニンは価格が比較的安く、その点でもおすすめです。私のクリニックでもかなりの患者さんが使っています。しかし、日本ではサプリメントとして認められていないため、個人輸入などの手間がかかるのが難点ですね」
そのほかでも、抗がん効果に対するサプリメントの臨床研究が進められている。
「たとえば、最近では、ビタミンDとカルシウムを併用したところ、がんの発生率が半減したという比較試験の結果も出ています」
魚油と乳酸菌の研究も注目の的
- ●がん治療中の体重減少の抑制(J Nutr, 2010)
- 病期3期の非小細胞肺がん40例が対象のオランダの無作為化比較試験。治療中にサプリメント(たんぱく質とカロリーの補給のため)単独摂取群、サプリメント+魚油(1日DHA0.9g、EPA2.0g摂取)併用摂取群に分けて観察した。併用摂取群は単独摂取群に比べ、筋肉や体重の減少が有意に少なく、炎症性サイトカインの産生も少なかった
- ●がん性悪液質の改善(Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2010)
- 悪液質となったがん患者332例を対象としたイタリアの第3相無作為化比較試験。悪液質の改善について、EPA単独摂取群では、対照群(EPA非摂取)との有意差はなかったが、サリドマイドなどの薬剤とEPAを併用した群では、対照群と明らかに差があった
最近では、サプリメントによって患者さんのQOLを高め、間接的にがんを改善させようという試みも盛んに行われている。
「注目されているのが、魚油に含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)とEPA、それにプロバイオティクスの臨床研究です」
病期3期の非小細胞肺がん40例を対象とした比較試験によれば、DHA・EPA摂取群は、非摂取群に比べ、治療中の筋肉や体重の減少が明らかに少なかった。
プロバイオティクスでは、5-FU(一般名フルオロウラシル)を含む抗がん剤治療中の大腸がん150例を対象にした比較試験でグレード(重症度)3~4の副作用(下痢)の発生率は、非摂取群の37パーセントに対し、乳酸菌摂取群が22パーセントだった。さらに、乳酸菌が膵がんの術後感染症の発生率を有意に下げたという比較試験もある。
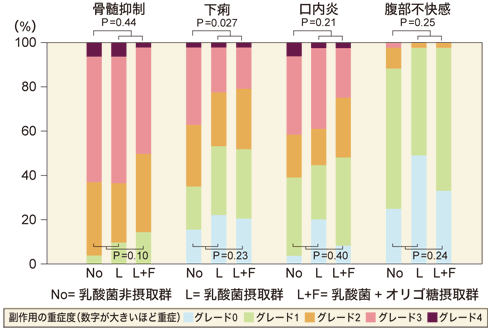
Br J Cancer 2007 October 22; 97(8); 1028-1034
「DHA・EPAや乳酸菌は、日常食品からも摂れるのが利点ですね。日常食品という点では、がん予防効果が報告されている大豆、ニンニクなども積極的に摂るといいでしょう」
福田さんは、エビデンスは重視すべきだが、臨床試験での有効性が示されていないサプリメントや食品でも、体に有害でないとわかっていれば、摂ってもかまわないと言う。
「漢方薬がよい例ですが、西洋医学のエビデンスがなくても臨床経験上、有効と考えられるものも中にはあります。患者さんの体調の改善に何らかの効果が期待できるのであれば、医師と相談の上、試してみてもいいのではないでしょうか」
サプリメントの問題の1つは、薬と違ってメーカーや商品によって品質がまちまちなこと。選ぶ際のポイントは何か。
「保障はできませんが、なるべく製薬メーカーや信用のある有名メーカーの商品を選ぶほうが外れは少ないでしょう」
福田さんは、笑顔でこう説明してくれた。
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる
- ガゴメ昆布「フコイダン」には有用性を裏付ける多くのエビデンスがある
- ガゴメ昆布「フコイダン」は腸管を直接刺激して免疫力を高める
- 免疫力を高めるガゴメ昆布「フコイダン」
- 好中球減少予防 代替療法にもエビデンスを追究する意義 乳がんの補助化学療法 AHCCに副作用軽減の可能性が?
- がんのサプリメントを選ぶ際の2つのポイント サプリメントの選び方の正しい基準
- サプリメント選びのポイントは臨床試験を行っているかどうか サプリメントはがん治療に役立つか? 最新徹底検証
- キノコ系食品「AHCC」に見るエビデンスのレベル 本当にがんに効果があるのか!? 健康食品のチカラ
- 健康食品には、進行抑制・改善、治癒、症状改善の効果があるか 健康食品を安易に使うことは勧められない


