- ホーム >
- 検査・治療法 >
- 代替医療・統合医療 >
- サプリメント・健康食品
キノコ系食品「AHCC」に見るエビデンスのレベル 本当にがんに効果があるのか!? 健康食品のチカラ
再発予防や生存延長する可能性
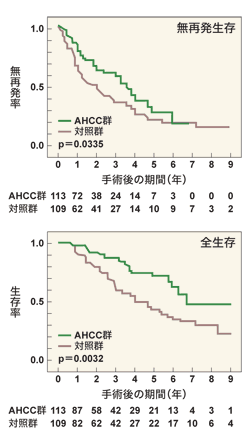
その結果、解析できたのは269人中222人。そのうちAHCCを摂取した群(113人)のほうが、摂取しなかった群(109人)に比べて、無再発期間が有意に長く、生存率が有意に上昇することを示す結果であった。
肝がんはよく再発をするがその再発率は、摂取しない群の72人(66.1パーセント)に対し、AHCC摂取群は39人(34.5パーセント)再発した。無再発率もAHCC群が有意に良好であった(再発しにくかった)ことを示していた。
死亡率は、摂取しない群の51人(46.8パーセント)に対し、AHCC摂取群は23人(20.4パーセント)で、これも有意に減少していた。
術後の観察期間は、摂取しない群の2~117カ月(平均30カ月)に対し、AHCC摂取群は2~108カ月(平均28カ月)の観察期間で全生存率も有意に良好であった。
さらに、術後5年間、肝機能に関する血清学的検査データの経時変化を10項目について追跡調査もしている。その結果、AST、γ-GTP、コリンエステラーゼにおいてAHCC摂取群で有意な改善が認められてもいる。
以上の調査結果により、肝細胞がん術後にAHCCを摂取することは、術後の再発を少なくしたり、生存を延長したり、肝炎を改善したりすることにつながる可能性が示唆された。
西洋医学と補完医療との関係

第16回AHCC研究会国際報告会における上山さんの講演風景
この調査を中心となって携わった関西医科大学第1外科教授(当時、現在は名誉教授)の上山泰男さんは、こう語る。
「AHCCは、肝細胞がん術後の再発を予防する補助療法としてよい効果のあることがわかりました。
補完代替医療は西洋医学の代わりをするものではありません。西洋医学を無視して代替医療に走るのは間違いです。あくまでも西洋医学にプラスαをもたらすものでなくてはいけません。その意味で、補完医療として大切なことは、生存率が短くならないことです。AHCCを、肝がん以外にも、胆管がん、乳がん、膵がん、胃がん、大腸がんなどの患者さんでも摂取されていますが、現時点ではAHCCを食べている群で生存率が下がるデータは出ていません。だから、この点はクリアできていると思います。
また、がんは長期的に闘う病気です。長期的に飲んで肝障害や腎障害などの副作用が強く出るのでは長期に闘えません。その点でも、AHCCには副作用がほとんどないので、長期に飲めるいい食品です。
第3に補完医療として大事なことは、簡便性です。肝細胞がんでは血漿交換などをしても再発予防の効果があると報告されています。しかし、血漿交換は大変ですしリスクもあります。その点、AHCCは飲むだけですから簡便ですし、補完医療の条件はすべてクリアしているといえます」
AHCC試験における今後の課題
ただ、これだけ良好な結果が出たこの報告にもまだまだ今後に課題が残されていることは間違いないようだ。たとえば、このコホート研究は、AHCCを飲んだか否かでその効果を調べているだけで、飲んだ期間や量は反映されていない。したがって、患者はどれくらいの期間、どれくらいの量を飲めばいいのかがわからない。
またこの研究は、最も信頼性の高い、二重盲験法でもなければ無作為化比較試験でもないという点だ。患者も医師もAHCCを摂取しているかどうかがわかっているので、厳密な意味でAHCCだけによる効果かどうか、確定できず、その分、データの信頼性は低くなる。また、摂取群と非摂取群とを無作為に分けてもいないので、ここにもバイアスが入る余地があり、信頼性が少し落ちるのだ。
もう1つ、なぜ、AHCCが患者の再発率や生存率に影響を与えたのかについて、この研究だけではわからないことだ。
ただ、この点は動物実験や臨床データなどである程度は類推できるようだ。
たとえば、AHCCと他のキノコ系健康食品との大きな違いは、キノコの菌糸体(根の部分)の培養が個体培養ではなく、液体培養であることだ。しかも、従来菌糸体の長期培養は難しいとされていたが、アミノアップ化学では独自の培養技術を培い、長期培養を可能にしている。そしてこれによって、食品の成分に影響を与えている。
通常、キノコ系食品の主成分はβ-グルカンと呼ばれる糖類だが、AHCCにはβ-グルカンはほとんど含まれていない。主成分はアセチル化されたα-グルカンと呼ばれる糖類だ。β-グルカンは巨大分子(分子量数万~数10万)なのに対して、α-グルカンは低分子(分子量約5000)である。そのため、AHCCは吸収されやすくなっていると考えられている。
もう1つは、ごく簡単に言うと、免疫機能を高めて、それによって間接的にがんを攻撃するのではないかと考えられている。
具体的には、最近の上山さんたちの臨床データでは、AHCCを摂取すると、体内で樹状細胞と呼ばれる免疫担当細胞の数が増加したり、樹状細胞のT細胞の活性化能が促進されていることが示されている(Nutrition and CANCER)。
樹状細胞は、がんを攻撃するリンパ球に「攻撃命令」を送る司令塔の役割をする免疫細胞である。AHCCは、こうして免疫機能を上げているのではないかというのだ。
このことから、上山さんは、手術や抗がん剤で敵(がん)を叩くことと、味方(自然治癒力)を強化する免疫療法を組み合わせる新しい医療の形、統合医療の重要性を力説している。
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる
- ガゴメ昆布「フコイダン」には有用性を裏付ける多くのエビデンスがある
- ガゴメ昆布「フコイダン」は腸管を直接刺激して免疫力を高める
- 免疫力を高めるガゴメ昆布「フコイダン」
- 好中球減少予防 代替療法にもエビデンスを追究する意義 乳がんの補助化学療法 AHCCに副作用軽減の可能性が?
- がんのサプリメントを選ぶ際の2つのポイント サプリメントの選び方の正しい基準
- サプリメント選びのポイントは臨床試験を行っているかどうか サプリメントはがん治療に役立つか? 最新徹底検証
- キノコ系食品「AHCC」に見るエビデンスのレベル 本当にがんに効果があるのか!? 健康食品のチカラ
- 健康食品には、進行抑制・改善、治癒、症状改善の効果があるか 健康食品を安易に使うことは勧められない


