- ホーム >
- 検査・治療法 >
- 代替医療・統合医療 >
- サプリメント・健康食品
健康食品には、進行抑制・改善、治癒、症状改善の効果があるか 健康食品を安易に使うことは勧められない
βカロテン(サプリメント)は効果なし
初期の研究でがんの予防に役立つと言われていた物質が、より信頼性の高い研究が行われるにつれて、効果なしとわかったり、かえって有害であることが明らかになったりすることもある。よく知られているのが、がんを予防すると言われていたβカロテンのサプリメント(野菜から取るβカロテンではなく、サプリメントの話)だ。
βカロテンは、細胞や遺伝子を傷つける活性酸素の働きを抑えることで、がんを予防する効果があると考えられていた。培養細胞レベルの実験や動物実験では、予防効果があることを示す結果が出ていたし、人間の集団を対象にした研究でも、がんの予防効果をうかがわせるデータが出ていた。そこで、食品からとるだけでなく、サプリメントとして多量に摂取したら、もっとはっきりした結果が出るだろうと考えられ、βカロテンのサプリメントを使った臨床試験が行われたのだ。
その結果、βカロテンをサプリメントで摂取しても、がんを予防する効果がないことが明らかになった。それどころか、喫煙者では肺がんの発生率が上昇するという結果さえ出てきたのだ。
「抗酸化作用を持つβカロテンやビタミンEなどのサプリメントは、がんや心臓病の予防に役立つということで、一時人気が高まったことがあります。臨床試験も盛んに行われたのですが、大規模な臨床試験が行われるようになると、効果を否定するデータが増えてきました。それどころか、サプリメントを利用していると、死亡率が高まるという研究結果も出てきたのです」
これは、デンマークの研究者グループが今年2月に発表したもの。抗酸化作用があるとされるβカロテン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、セレンのうち、少なくとも1つを使った68件の臨床試験(ランダム化比較試験)を対象に、総合的に分析したものである。68件の臨床試験に参加した人を合計すると、23万人にもなるという。
サプリメントを飲んだ人と、偽サプリメント(形などは似ているが成分を含まない)を飲んだ人で、総死亡率を比較すると、サプリメントを飲んでも飲まなくても、統計学的に意味のある差はないことがわかった。総死亡率とは、あらゆる死因を合わせた死亡率のことである。
サプリメントを飲んだら死亡率が上が���た
(飲まないグループの総死亡率を1とする)
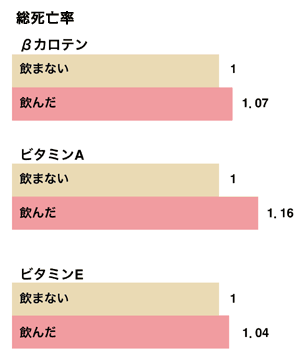
さらに研究方法などから、データの信頼性がより高いと考えられる47件の臨床試験に絞って分析を行うと、サプリメントを飲んだ人の総死亡率が高くなった。ビタミンCとセレンは「さらに研究が必要」とされたが、βカロテン、ビタミンA、ビタミンEのサプリメントは、総死亡率を上昇させると結論づけられたのである(図3)。
「βカロテンのサプリメントで総死亡率が7パーセント、ビタミンAで16パーセント、ビタミンEで4パーセント高くなっています。個々の病気ではなく全体の死亡率が増えるという結果ですから、これは非常に大きな影響といえます。このように、さまざまな研究が行われていたサプリメントでも、大規模な研究が行われることで、それまでの常識が逆転することがあります。がんの患者さんを対象にした研究ではありませんが、一般的な話として、このようなことも起きるということを、念頭に置いておくべきでしょう」
健康食品を利用するがん患者のなかには、どれほど治療効果があるかわからないが、とりあえず飲んでおいたほうが体によさそうだ、と考えている人がいるだろう。しかし、健康に役立つと言われながら、実はそうではなかったケースもあるのだから、健康食品を安易に利用することは決して勧められない。
健康食品に関する情報を正しく評価する方法
世の中には、健康に関する情報がたくさん出回っている。がんと健康食品に関してもたくさんの情報があり、その信頼性はさまざまだ。ある情報が信頼できるものかどうかを評価するために、坪野さんは「健康情報を評価するフローチャート」を利用することを勧めている。
ステップ1は、具体的な研究に基づいているかどうか。体験談だけの健康情報は、それ以上考慮する必要がないことになる。
ステップ2は、研究対象が人間かどうか。培養細胞による実験や動物実験で効果があっても、人間のがんに効果があるとは限らない。人間を対象にした研究で効果が検証されていなければ、興味深い仮説として話半分に受け止めておく程度でいいという。
ステップ3は、学会発表か論文報告か。学会発表というと、専門家たちに認められたのだから正しいのだろうと考えたくなる。しかし、学会発表のために提出した原稿が、拒否されることは一般に少ない(日本の学会はほとんど拒否しないが、海外の学会は拒否も多い)。その点、専門誌に論文を載せるためには厳しい審査が行われる。論文報告なら一定の信頼を置けるが、学会発表はそれだけでは判断できないので、評価を留保して聞いておくに止める。
ステップ4は、研究方法が「ランダム化比較試験」や「前向きコホート研究」かどうか(研究方法については 「疫学研究の方法」参照)。研究方法によって、得られたデータの信頼性は大きく異なる。最も信頼性が高いのはランダム化比較試験で、その次に信頼できるのが前向きコホート研究。これらの方法であれば、信頼性の高い研究として評価できる。それ以外の研究方法なら、参考程度と考える。
ステップ5は、複数の研究で支持されているかどうか。ランダム化比較試験でも、データが偏っていることがある。その点、複数の研究で一致した結果が出ていれば、それは信頼するに値する情報と考えていい。
この方法で評価すると、ステップ5までクリアする健康情報は、実はきわめて少ない。ほとんどの情報が、どこかの段階で消えてしまうはずだ。だから使用すべきではないとは言えないが、ある情報に基づいて健康食品を利用するのであれば、その情報の信頼性がどの程度なのかを、きちんと評価しておくことは必要だろう。
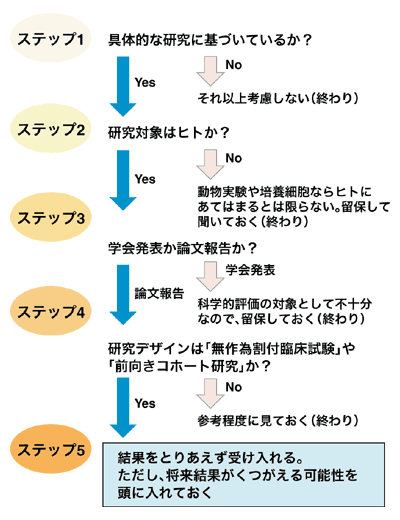
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる
- ガゴメ昆布「フコイダン」には有用性を裏付ける多くのエビデンスがある
- ガゴメ昆布「フコイダン」は腸管を直接刺激して免疫力を高める
- 免疫力を高めるガゴメ昆布「フコイダン」
- 好中球減少予防 代替療法にもエビデンスを追究する意義 乳がんの補助化学療法 AHCCに副作用軽減の可能性が?
- がんのサプリメントを選ぶ際の2つのポイント サプリメントの選び方の正しい基準
- サプリメント選びのポイントは臨床試験を行っているかどうか サプリメントはがん治療に役立つか? 最新徹底検証
- キノコ系食品「AHCC」に見るエビデンスのレベル 本当にがんに効果があるのか!? 健康食品のチカラ
- 健康食品には、進行抑制・改善、治癒、症状改善の効果があるか 健康食品を安易に使うことは勧められない


