どうやってがんを叩くのか。なぜ副作用が強いのか。抗がん剤の疑問にわかりやすく答える がんを知らない人でもすぐわかる!抗がん剤の基礎知識
複数の抗がん剤を一緒に使う
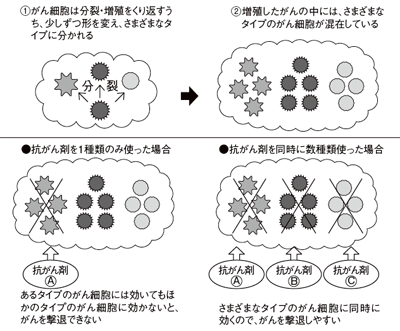
抗がん剤は1種類だけを使うより、2~3種類を一緒に使うことが多い。その理由はいくつかある。
抗がん剤治療には、特定の抗がん剤を使い続けるとがんが攻撃をかわす術を身につけ、薬が効かなくなるという問題がある。その対策の1つとして行われているのが、複数の抗がん剤を同時に使う投与方法(多剤併用)だ。こうすれば、がんは薬に対する抵抗力を獲得しにくくなる。
「1種類の薬だけでがんを叩くのが難しい理由としては、同じがんといっても、実はがん細胞の性格や性質が多様なこともあげられます。兄弟の顔つきが少しずつ違うように、分裂を繰り返すうち、がん細胞も姿を変えていくのです。そこで、複数の抗がん剤で、あるタイプのがんは空爆し、生き残ったがんは毒ガスで攻撃し、それでも死なないがんは兵糧攻めにするといった具合に、多様な攻撃の方法でがんを叩いたほうがいいというわけです」
多様化する抗がん剤の投与方法
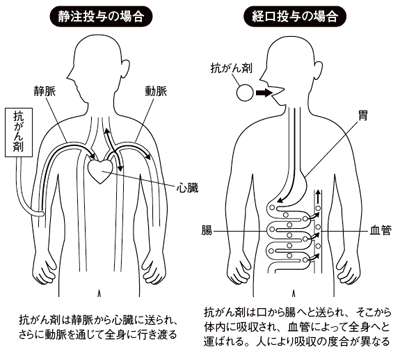
抗がん剤治療は腕などの静脈に針を刺し、点滴によって薬を注入する方法(静注)が一般的だ。静注は操作がしやすく、抗がん剤を確実に体内に入れられるからだ。一方で、抗がん剤にも口から飲む経口剤がある。
「患者さんにとって理想的なのは使いやすい経口剤でしょう。しかし、経口剤は腸から薬を吸収できる度合いが人によって違うため、一定の薬剤濃度にするための技術が難しく、また”飲み忘れ”の問題などで管理も簡単ではありません」
まだ一部のがんでしか使えないが、カテーテルという体に挿入する管を使い、がんに栄養を送る動脈から直接抗がん剤を注入する���法もある。
「一般の抗がん剤治療とは異なり、がん本体を狙う局所療法といえます。静注や経口投与の場合、抗がん剤は全身に広がるので、がんに到達する割合は投与量の数万分の1にすぎません。この方法なら、抗がん剤は高濃度のままがんに到達するため、がんを叩く効果が大きいと考えられ、行われてきました。しかし、実際に効果が上がるのは、一部のがんだけであることもわかってきました」
抗がん剤の投与量は臨床試験で決める
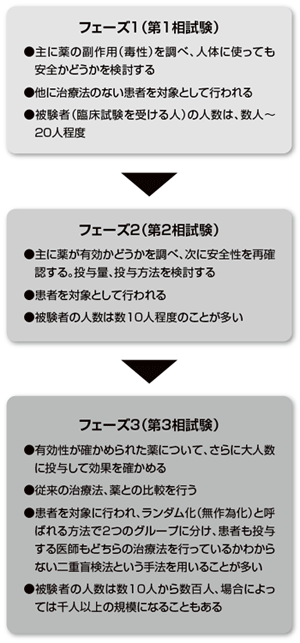
従来の抗がん剤は過剰に投与すれば、かえって命を縮めることになりかねない。抗がん剤の投与量はどのようにして決まるのか。
「臨床試験によって決められます。まずネズミの致死量(*)の数分の1の薬を人間に投与し、少しずつ投与量を増やしてどこまで耐えうるかを確かめます(フェーズ1という)。次に、人間にどのぐらい投与すれば効き目が出るかを調べます(フェーズ2という)。こうして安全性と効果を確認しながら、最適な投与量を見極めていくわけです」
*致死量=投与すれば確実に死ぬ薬の量
抗がん剤が効いてもがんは治らない?
一般に抗がん剤の効き目は、「がんが小さくなったかどうか」で判断される。よく「奏効率」という言葉が使われるが、これは「抗がん剤を投与した全患者のうち、がんの大きさが7割以下になり、その状態が1カ月以上続いた患者が何パーセントいたか」を示す数値だ。臨床試験では「奏効率20パーセント」が薬の承認の目安となる。
抗がん剤治療の成果を表すのに「寛解」という言葉もよく使われる。「完全寛解」とは「4週間以上、がんが画像診断では完全に見えなくなった状態」のこと。だが、完全寛解に持ち込むことができても、抗がん剤の投与をやめると微小ながんが勢いを取り戻すことがある。奏効率も完全寛解も、ある時点での治療効果を示しているだけなので、その状態が続かなければ意味はない。必ずしも「抗がん剤が効く」=「がんが治る」ではないのである。
「抗がん剤の効き目を示す数値には、全生存期間(最終的な生存期間)や無増悪生存期間(がんが進行しない期間)もあります。全生存期間の延長が望ましいのですが、まだまだ目ざましい成果の出た薬は少ない。そこで、無増悪生存期間が注目されています」
たとえがんを治せなくても、がんが悪化しない期間を延ばせれば、健康状態を維持し、命をつないでいけることになるので、治療効果の重要な指標といえるわけだ。
| 奏効率 | 抗がん剤投与を受けた患者のうち、下記の完全奏効、部分奏効が占める割合 ●完全奏効(CR) がんの消失が4週間続いた状態 ●部分奏効(PR) がんの大きさが30%以上縮小し、それが4週間続いた状態 ●不変(SD) PRとPDの間の状態 ●進行(PD) がんの大きさが20%以上増加 |
| 生存率 | 抗がん剤投与を受けた患者のうち、ある時点で生存している割合 |
| 5年生存率 | 5年後の生存率。多くのがん種で治療成功の目安にされる |
| 無増悪生存期間 | 抗がん剤投与を受けてから、がんが進行せずに生存した期間。進行がんで重視される (無増悪生存期間中央値とは患者全体のうち、中間の長さの無増悪生存期間。 無増悪生存期間平均値とは患者全体の平均期間) |
| 無再発生存期間 | がんがいったん消失した場合、抗がん剤投与を受けてから、がんが再発せずに生存した期間 |
| 全生存期間 | 抗がん剤投与を受けてから、患者が生存した期間 |
血液がんは抗がん剤が効きやすい
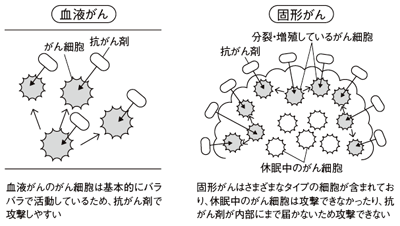
[抗がん剤が効きやすいがんと効きにくいがん]
| 抗がん剤がよく効くがん | 白血病・悪性リンパ腫・精巣腫瘍・絨毛がんなど |
| 抗がん剤が比較的効くがん | 小細胞肺がん・乳がん・卵巣がん・骨肉腫・膀胱がんなど |
| 抗がん剤が比較的効きにくいがん | 非小細胞肺がん・前立腺がんなど |
| 抗がん剤があまり効かないがん | 肝がん・胆のうがん・腎がん・甲状腺がん・脳腫瘍・悪性黒色腫など |
では、抗がん剤だけでがんを治すのは難しいのはなぜだろうか。
「第1に多くの抗がん剤は毒性も強く、がんを根絶できるだけの量を投与するのが難しいためです。第2に抗がん剤治療は再発・転移の場合が多いのですが、それまでのがん治療を生き延びた、よりしぶといがんが相手になるからです」
一方では抗がん剤だけで治せるがんもある。その代表が白血病や悪性リンパ腫などの血液がんだ。一般に固形がんは抗がん剤が効きにくいが、精巣腫瘍、絨毛がん(子宮がんの1種)のほか、乳がん、小細胞肺がんなどは、抗がん剤が比較的効きやすいことで知られている。半面、脳腫瘍や悪性黒色腫、肝がんのように、抗がん剤が効きにくいがんもある。
「血液がんはがん細胞が比較的似たような性格を持っていて、またどの細胞も増殖しているので、抗がん剤が効きやすい(がんを攻撃しやすい)のですが、大きくなった固形がんは一部のがん細胞しか分裂・増殖していないので、抗がん剤が効きにくい(増殖していないがんは攻撃しにくい)といえます。また、がん細胞は発生した臓器や組織が異なれば、それぞれ性質も異なります。そのため、試験をしてみると、同じ抗がん剤でも乳がんには効いて胃がんには効かない、ということがあるわけです。多剤併用でも同じで、どの薬の組み合わせがどのがんに効くかは試してみないとわかりません。さらに、患者さんによってがん細胞の個性も違うので、同じがんで同じ抗がん剤を使っても効き目が違います」
抗がん剤にはさまざまな長所と短所があるが、うまく活用すれば、がんの治療に大いに役立つことがおわかりいただけただろうか。抗がん剤に対する正しい知識を持ち、主治医と相談しながら自分に合った抗がん剤治療を見出すことが、がんの治療を成功させるために、患者さんにも求められているといえるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


