大型新薬の登場から1年。再発・難治の骨髄腫でも大幅改善した例が続出 大きく前進する多発性骨髄腫の薬物療法
QOLを保つのに適した薬
東京慈恵会医科大学付属柏病院ではたとえば、65歳を超える患者さんにはまずMP療法やデキサメタゾンを試し、「良好な部分奏効」(血中Mたんぱくが9割以上減少など)が維持できない場合は、ベルケイド、サレド、あるいはレブラミドに切り替えるという。その際、重要な選択基準となるのが副作用だ。
「治療効果があっても、副作用が重ければ、治療は続けられません。治療効果を維持するには副作用を悪化させないことが肝心なのです。たとえ軽度の副作用でも、患者さん自身が耐えられなければならないのです」
ベルケイドには、手足などがしびれたり、痛んだりする末梢神経障害という重大な副作用がある。半年~1年ほど使っていると、多くの患者さんがこの症状を訴えるといい、副作用が悪化して治療を止めざるを得ないケースが少なくないという。サレドにも眠気などの副作用がよく起こる。
「レブラミドにも血球減少、深部静脈血栓症(*)といった副作用があり、注意は必要ですが、比較的コントロールしやすいですね。当院の多発性骨髄腫の多くの患者さんが、投与量を調節することでレブラミドの治療を継続できています」
レブラミドは動物実験によって胎児への催奇形性が心配されている。そのため、胎児への影響を避ける目的で、「レブメイト」という適正管理手順が定められており、患者さんや医師はその手順を守ってレブラミドを使用しなければならない。
「レブメイトの手順を守るのはそれほど難しくありません。また、ベルケイドは注射薬ですが、レブラミドは経口薬なので、遠方から通院する患者さんの負担を軽くできます。さらに承認後1年が経ち、長期投与も可能になったので、QOLを保つのに適した薬といえるでしょう。しかし、腎機能の低下した人への使用はレブラミドの血液中の濃度が高くなり、副作用が出やすくなるため、投与量を減らすといった注意が必要です」
| 薬剤 ※デキサメタゾンを 併用する | 投与経路 | 深部静脈 血栓症 のリスク | 顕著な末梢 神経障害の リスク | 腎機能 障害患者 への使用 | 治療期間 の推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| レナリドミド | 経口投与 | あり | なし | 減量 | レナリドミドは 病勢進行まで継続 |
| ボルテゾミブ | 静脈内投与 | なし | あり | 減量不要 | 最大の奏効が得られたら 中断または減量 (維持療法) |
| サリドマイド | 経口投与 | あり | あり | 減量不要 | 最大の奏効が得られたら 中断または減量 (維持療法) |
[レナリドミドが効果を発揮した症例(慈恵医大柏病院)]
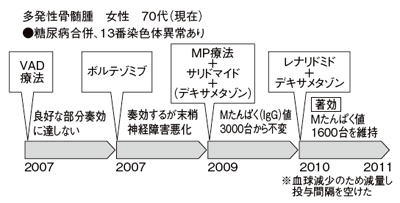
*深部静脈血栓症=体の深部の静脈内で血液が固まる病気。エコノミークラス症候群
予後不良の症例にも著効
| リスク分類 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 高リスク | 17番染色体欠失 14・16番染色体転座 14・20番染色体転座 | GEP(遺伝子発現予測) で高リスクとされている |
| 中間リスク (やや高リスク) | 4・14番染色体転座 13番染色体欠失 低2倍体 | PCLI(骨髄腫細胞 の増殖割合)≧3% |
| 標準リスク | その他の異常:高2倍体 11・14番染色体転座 6・14番染色体転座 |
東京慈恵会医科大学付属柏病院における多発性骨髄腫に対する治療症例をいくつか紹介しよう。
60代前半男性患者さん(IgD(*)型)は移植の前の大量化学療法でVAD療法を受けたが奏効 せず、ベルケイドを使ったが病気が進行した。そのため、レブラミドに切り替えたところ、3コース後にMたんぱくの値が770から30に減った。このままなら移植を実施できる見込みだという。
「最近では遺伝子診断技術の発達で、17番や13番染色体異常、4・14番染色体転座(*)の多発性骨髄腫患者さんは予後不良とわかっています。この患者さんは13番染色体異常、4・14番染色体転座、高2倍体(*)があり、ベルケイド抵抗性でしたが、レブラミドがよく効いたので驚きましたね」
70代の女性患者さん(IgG型)はVAD療法で十分な効果が得られず、ベルケイドに切り替えたが、末梢神経障害が出て中止に追い込まれた。その後、MP療法とサレド、デキサメタゾンを併用したものの、Mたんぱくの値が3000台で止まったため、レブラミドに切り替えたところ、値が1600に激減して、約1年間安定している。また、末期の患者さんがレブラミド使ったところ、Mたんぱくの値が1万から3000に減り、3カ月間自宅から通院できた例もある。
「レブラミドを1年間使ってみて、前評判に違わぬ効果を実感しています。レブラミドは早期に使えば、より効果が大きいという海外の研究報告もあるので、これから臨床試験が進み、初回治療でも幅広く使えるようになることを期待したいですね」
レブラミドは、3つの新薬の中でも期待されている薬剤のようだ。
*IgD=Mたんぱくの1種。多発性骨髄腫はMたんぱくの種類によって、主にIgA型、IgG型、IgD型、IgM型に分かれる
*染色体・転座=染色体は遺伝子の集合体で細胞核に含まれ、1番から22番まである(性染色体を除く)。転座とは染色体同士が入れ替わること
*高2倍体=染色体が通常(2倍体)より多いこと。反対に通常より少ないことを低2倍体という
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


