適切な治療を、適切な患者に、適切な時に行うことが重要 個別化が進む世界のがん医療
各種がん治療において新たなエビデンスも続々と登場
進行胆管がんに初の標準療法確立か!?
進行胆管がんは、発症頻度は低いものの治療は困難で、これまでに標準療法は確立されていない。マンチェスター大学のジュアン・ヴァレさんらは、進行胆管がんを対象とする英国における最大規模の第3相無作為化試験UKABC-02を実施し、ジェムザール単独投与群206例と比較して、ジェムザール+シスプラチン(商品名ランダまたはブリプラチン)併用群204例では、無増悪生存期間(6.5カ月対8.4カ月)および生存期間(8.3カ月対11.7カ月)がともに有意に延長し、忍容性も良好だったことを報告した(図6)。そしてこの治療法が、「進行胆管がんに対する初の標準療法になりうる」との見解を示した。副作用として多かったのは中等度の好中球減少症で、併用群22.6パーセント、ジェムザール単独群17.9パーセントに認めたが、多くは無症候だったという。
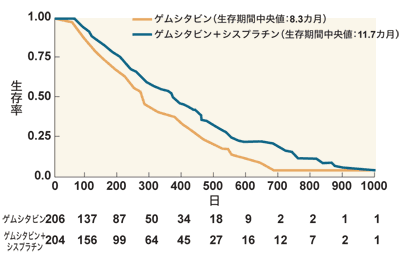
非小細胞肺がんは組織型によって薬を選ぶ時代へ
日本でも、悪性中皮腫に加えて「切除不能な進行・再発非小細胞肺がん」に対する適応が5月に認可されたばかりのアリムタ(一般名ペメトレキセド)が、特定の組織型(非扁平上皮がん)を有する非小細胞肺がんの維持療法として有用であることが明らかになった。ペンシルバニア州立ハーシーがん研究所のチャンドラ・P・ベラニさんによれば、プラチナ製剤を基本とする初期治療後に増悪を認めないステージ3B/4の非小細胞肺がん患者を対象とする第3相無作為化2重盲検試験で、適切な対症療法に加えてアリムタを投与した441例の無増悪生存期間は4.0カ月、全生存期間は13.4カ月で、対症療法+プラセボ投与222例(無増悪生存期間2.0カ月、全生存期間10.6カ月)と比較して、いずれも有意に延長した。組織型別に検討したところ、非扁平上皮がん481例での全生存期間はアリムタ群15.5カ月で、プラセボ群10.3カ月と比べて有意に延長していたが、扁平上皮がん182例では両群に差を認めなかった(図7)。ベラニさんは、「組織型によってより効果的な治療を選ぶ時代になった」と非小細胞肺がん���療のパラダイムシフトを強調した。
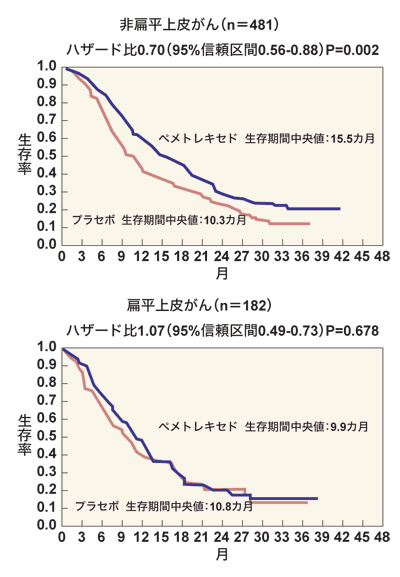
免疫療法で高リスクの神経芽細胞腫の生存率が上昇
神経芽細胞腫は、1歳未満では最も多いがんで、死亡率は約15パーセントである。なかでも40パーセントを占める高リスク患者では、化学療法、手術、幹細胞移植と治療を尽くしても多くが死に至る。カリフォルニア大学サンディエゴ校のアリス・ユゥさんによれば、小児神経芽細胞腫226例を対象とした試験で、化学療法後、手術、幹細胞移植をした後に、標準療法(13シスレチノイン酸)のみを行った患者の2年無病生存率は48パーセントだった。これに対して、抗GD2モノクローナル抗体を用いた免疫療法を加えた患者の2年無病生存率は66パーセントと約20パーセントも上昇した。痛み、脈管漏出、アレルギー反応などの有害事象は、いずれも対処可能だったという。両群の差が大きかったことから試験は早期に打ち切られ、現在、この治療法のFDA承認を目指してさらに安全性を検討中である。この免疫療法は、抗GD2モノクローナル抗体が、腫瘍細胞に発現している糖脂質GD2に特異的に結合し、それによって他の免疫細胞が誘発されて腫瘍細胞を攻撃するというもので、同じくGD2を発現する腫瘍であるメラノーマや小細胞肺がんなどにおいても有用である可能性が期待される。
QOLを高めてより効果的ながん医療を
予防的治療で激減 抗EGFR製剤の皮膚毒性
大腸がんにおいて、抗EGFR抗体製剤は高い治療効果を示すが、ベクチビックスでは90パーセント、アービタックスでは75パーセントの患者に、にきび様の皮疹が出現する。効果の指標になるともされるほどだが、美容上の問題に加えて、投与拒否や投与延期などによる治療効果軽減につながることが懸念されている。トーマスジェファーソン大学のエディス・ミッチェルさんは、切除不能の転移性大腸がんに対する2次治療で、皮膚治療レジメン(保湿剤/日焼け止め/局所ステロイド剤/経口抗菌剤)をベクチビックス投与前日から6週間投与することによって、皮疹出現後に同治療を開始した患者と比較して皮膚毒性が激減、治療延期頻度が低下し、治療効果も高くなることを報告した。
ミッチェルさんは、「外見上の悩みも減り、QOL(生活の質)を損なうことなく効果的な治療が可能となる。予防的治療は今後、抗EGFR製剤投与に際する標準療法として組み込まれる可能性がある」と話した。予防的治療薬はすべてジェネリック薬で賄うことができ、コストの点でも魅力的だという。
進行卵巣がんの再発予測CA125測定は必要ない?
初期治療終了後の進行卵巣がんの再発率は80パーセントにのぼり、多くの患者が再発と寛解(病気の症状が軽減し、臨床的にコントロールされた状態)を繰り返す。欧米では再発予測のための腫瘍マーカーとして、血中に微量に存在する糖タンパク質CA125の定期的な測定が行われている。
英国マウントバーノンがんセンターのゴードン・ラスティンさんは、MRCOV05/EORTIC55955試験において、プラチナ製剤による初期治療で完全寛解が得られた進行卵巣がん患者では、CA125上昇を指標として症状のないうちに治療を開始しても、骨盤痛、膨満などの症状発現後に治療を開始した患者と比べて生存期間は延長しなかったことを報告した。QOLも症状発現後に治療開始した患者のほうが良好だったという。この成績は、症状発現まで治療開始を先延ばしにしても生命予後が悪化しないことを、はじめて実証したものであり、今後、定期的なCA125測定を行うかどうかは、患者の意向を重視することになるだろう。副作用を伴う化学療法の期間を短縮できることもあってか、ラスティンさんの施設でも、多くの患者が定期的なCA125測定は行わず、症状発現後の治療を希望したという。
より質の高い個別化医療を目指して

分子標的治療をはじめとして、さまざまな患者のさまざまな腫瘍に対抗するための多くの武器を手にした今、がん研究においては、それらをいかに用いるべきかを明らかにすることが、より質の高い個別化医療を実現するための鍵となる。そのために、がんの生物学、個々の患者の「宿主」としての生物学や「人間」としてのさまざまな背景や環境と、これらの関係を明らかにしていく過程は、新たな薬剤や治療法の開発にもつながるものである。また臨床の現場では、多様化する医療を適切に個別化していくために、これまでにも増して、患者と医師とのコミュニケーションが重要になっていくだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


