抗がん剤の使用方法に関する基本的な考え方 抗がん剤の投与量、投与間隔をきちんと守る
がん細胞の再増殖する間隔を短くすることが重要
がん細胞の増殖には、増殖しているがん細胞の割合、がん細胞が分裂する周期の長さ、さらにはがん細胞自身が死んでいく程度など、いくつかの要素が関係しています。そこで、抗がん剤治療の分野では、このようながん細胞の増殖をどのようにすれば効率的に抑えられるかについて、いくつかの理論が考えられ、それに基づく研究が行われてきました。
がん細胞が増殖する速度については、当初がん細胞の大きさに関係なく常に直線的で一定であるという考え方がありましたが、その後、その考えは否定されています。
つまり、がんが小さいときには増殖が速いのですが、がんが大きくなるとがんが増殖するために必要な栄養分を運ぶ血液や酸素が相対的に不足するため、増殖速度はむしろ遅くなるという考えに改められたのです。
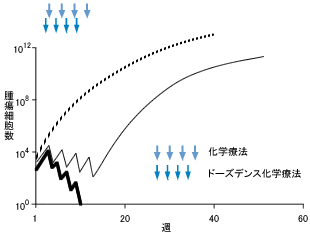
この考え方によると、抗がん剤治療が効果を発揮し、ある程度、がんが小さくなってくると、その反動として、残っているがん細胞の増殖速度が逆に速くなることが考えられます。
したがってこの考え方からは、抗がん剤投与の間隔をできるだけ短くして、がんの再増殖を抑えようとする仮説が立てられました(サイモン・ノートン理論)(図4)。
この仮説に基づいて、臨床においても、抗がん剤の用量を変えずに、投与する間隔を縮めることによって、抗がん剤とがん細胞の接触する頻度を高め、がん細胞の再増殖を最小限に抑えようとするドーズデンス化学療法と呼ばれる治療方法が考えられ、今日では、抗がん剤治療の主流の1つになりつつあります。事実、いくつかの臨床試験でもその効果が証明されつつあります。
投与間隔短縮療法の有効性
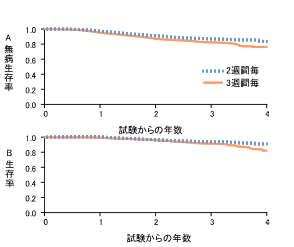
たとえば、乳がんの患者さんを対象とした試験(Cancer and Leukemia Group B 9741と呼ばれる)で、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、エンドキサン(一般名シクロフォスファミド)、およびタキソール(一般名パクリタキセル)のドーズデンス化学療法(2週間毎に反復使用)は、同じ組み合わせで標準的な治療方法である3週間毎の使用より、優れた効果があることが確かめられています(図5)。この治療には好中球減少症回避のためにG-CSFが予防的に使用されています。
また、中~高悪性度リンパ腫についても、とくに高齢患者さんにおいて、ドーズデンス*CHOP療法が、標準的なCHOP療法よりも優れていることが海外の大規模な臨床試験で確かめられています。
*CHOP=エンドキサン(シクロフォスファミド)、アドリアシン(ドキソルビシン)、オンコビン(ビンクリスチン)、プレドニゾロンの4剤併用療法
まとめ
このように見てみると、がん、とりわけ乳がんの術後補助療法と悪性リンパ腫の抗がん剤治療の基本は、なんと言っても決められた用法・用量どおりにきちんと抗がん剤を使用することかと思われます。それは、縮小したがんが再増殖するときに、抗がん剤とがん細胞の接触する機会をできるだけ多くするドーズデンス化学療法が、治療効果を高めることで証明されつつあります。
ですが、ドーズデンス療法はまだまだエビデンスとして確立されてはおらず、実験的医療の域を超えていないのが実情です。
ただし、少なくとも決められた用法・用量どおりにきちんと抗がん剤を使用することが重要である事実は変わりません。そのためにも、G-CSF製剤や、制吐剤をうまく使用することも必要になってきます。とりわけG-CSF製剤は、単に好中球減少症の予防だけではなく、好中球減少症を発症しても、それを重症化させない(重度の好中球減少症、発熱性好中球減少症の予防)ためにも積極的に使うことが望まれます。
このような理論に基づいた抗がん剤治療を受けるためには、経験豊かながん専門医(オンコロジスト)が常時勤務し、がんのチーム医療が確立されている病院を受診することが望まれます。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


