仕事と治療を両立させる外来化学療法 医療技術や薬剤の進歩により入院治療から外来・在宅治療へ
種々の副作用のコントロールも可能!
外来化学療法では抗がん剤の副作用を軽減し、患者が楽に化学療法を継続できるためのさまざまな工夫がなされている。たとえば、抗がん剤の新たな投与方法もその1つだ。
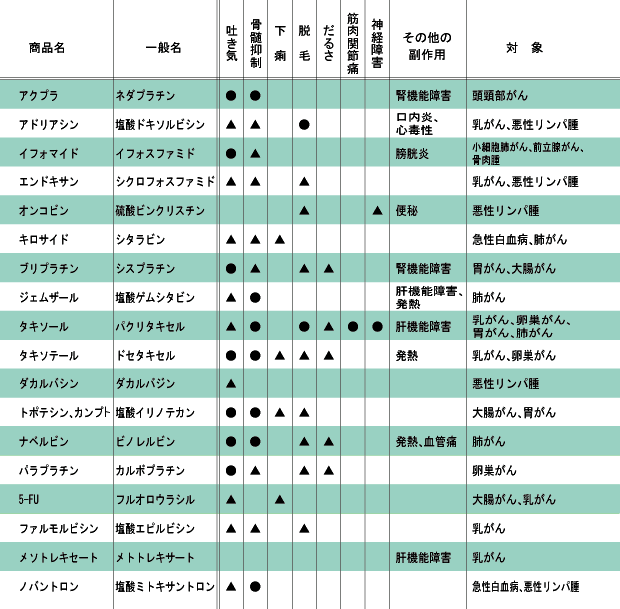
:とくに多く現れる副作用 ▲:多く現れる副作用
「タキサン系抗がん剤のタキソールは、3週間に1回点滴投与するのが一般的方法です。しかし、白血球の減少や末梢神経障害等の副作用が強く現れるため、それを軽減する週1回のウィークリー投与が確立されました。外来化学療法では患者さんにより安全に、より楽に受けてもらうため、タキソールは週1回のウィークリー投与が普及しています」(徳田さん)
一方、抗がん剤の副作用を抑え、それをコントロールする支持療法もしっかりと行われている。
乳がんの化学療法で使用される抗がん剤の中で、もっとも強い吐き気や嘔吐を起こすのはアントラサイクリン系抗がん剤だ。なにも支持療法を行わないと、投与後、数時間してから気持ちが悪くなり、それが2~4日間続く。
「しかし、吐き気などを抑えるためのカイトリル(一般名グラニセトロン)等の抗セロトニン剤や、デカドロン(一般名リン酸デキサメタゾンナトリウム)等のステロイド剤などを事前に投与しておくと、こうした急性期の吐き気や嘔吐などはほとんど抑えこむことができます。実際、ほとんどの患者さんは吐くことはありません」(徳田さん)
ただし、投与を受けてから4日目以降に生じる晩期の吐き気や嘔吐などを覚える患者がわずかにいるが、それはコントロールしにくいというのが難点である。
タキサン系抗がん剤の特徴的な副作用として、手や足の痺れを招く末梢神経障害があげられる。週1回のウィークリー投与の確立で末梢神経障害を避けられる患者も増えてきたが、中には投与を繰り返すと痺れが徐々に増強していく患者もいる。
「いま���ところタキサン系抗がん剤の痺れを防ぐ確実な手立てはないので、それが増強する患者さんは投与を一旦中止し、他の抗がん剤に切り替えて外来化学療法を継続してもらいます」(徳田さん)
抗がん剤は投与1~2週間後に白血球の減少を招くことが少なくない。白血球が減少すると細菌やウイルスに感染しやすくなり、高熱や肺炎などを起こすこともある。
実際、発熱が生じた場合は抗生物質の内服を始め、それでも熱が収まらなければただちに主治医に連絡する必要がある。抗生物質の点滴や、白血球の増殖を促すG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)の注射を受けなければならないからだ。
QOL向上のためにも望まれる普及

化学療法室では、リクライニングシートかベッドかを選択することができるが、
ほとんどの患者がベッドを希望するという
東海大学病院の外来化学療法は、まず患者は各科の外来で主治医の診察を受ける。主治医は薬剤課に抗がん剤等の薬剤名とその量などの指示を出し、薬剤課はそれを受けて外来化学療法室へ抗がん剤を届ける。外来化学療法室では個々の患者ごとに主治医の出した指示書と薬剤が合致しているか否かを厳密にチェックしたうえで、その日の担当医から患者に抗がん剤が投与されるシステムとなっている。
「CAF療法やCEF療法等の抗がん剤やハーセプチンの投与は約1時間で終了します。タキサン系抗がん剤の投与はアレルギー等を防止するため、ステロイドや抗ヒスタミン剤等の事前投与があるので2~3時間かかります。その間、患者さんはベッドかリクライニングシートに体を横たえ、リラックスして投与を受けています」(徳田さん)
がんの化学療法は患者と医師が二人三脚で進めていかねばならない。患者は体調の変化や症状の動静などをきちんと医師に報告すると同時に、医師はそのつど、より適切な処置を行っていく必要がある。副作用の少ない新規抗がん剤の開発や支持療法の発達、そして長年の経験によって、あらかじめ個々の患者ごとに症状の推移が見通せるようになり、より安全な化学療法が遂行できるようになってきた。
アメリカではすでに化学療法を受けているがん患者の8~9割が、通院外来で抗がん剤の投与を受けている。しかも透析クリニック(腎不全の患者が人工透析を受けられるクリニック)のように居住地や職場の近辺に化学療法専門のクリニックが開業しているため、普通の生活を営みながら化学療法が受けられる。抗がん剤によって治癒をはじめ、症状の改善、QOLの維持・向上をはかり、がん患者にとっては、なくてはならないシステムとなっている。
日本の外来化学療法はようやく端緒についたばかりだが、その普及はがん患者とその家族にとって大きな福音となるにちがいない。なによりも患者が家族とともに生活できることに加え、先の吉田さんのように仕事を継続しながら治療を受けられる。さらに入院にかかる費用は不要となり、その分、患者側の治療費の負担も軽くなる。 いわば、外来化学療法はがん患者の生活を支えるテコであり、早急な普及が待ち望まれている。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


