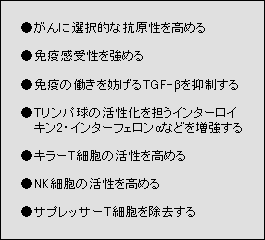わずかな副作用で延命効果を得る極少量抗がん剤療法
QOLを維持しながら長生きするための治療法
梅澤さんは約10年間、町田市民病院外科に勤務し、乳がんを中心に数多くの標準的な抗がん剤治療に取り組んできた。しかし、次第に標準的な抗がん剤治療に疑問を抱くようになった。
「標準的な抗がん剤治療を行えば、確かに奏効率は得られます。がん病巣はおもしろいように縮小します。しかし、長生きしないのです。数カ月の延命のために副作用で苦しんでいる患者さんもいます。本当に患者さんは満足しているのだろうかと考えるようになりました」(梅澤さん)
次第に免疫療法に興味を抱き、免疫療法で知られるオリエント三鷹クリニック(八木田旭邦元近畿大学教授)に1年半ほど勤務した。しかし、この免疫療法にも失望し、抗がん剤治療と免疫療法の両方の長所を取り入れた治療法を追究し始めた。
「がんと闘うにはたくさんの武器が必要です。抗がん剤と免疫療法は相反する治療と思われがちですが、がんと闘うには両方の長所を生かすことが大切です。私は再発・進行がんの患者さんが少しでも長生きができるように努力しています」と梅澤さん。
梅澤さんが取り組んでいる「極少量抗がん剤を組み合わせた治療」「がん免疫化学療法」のメカニズムは残念ながら解明されていない。しかし、この治療法によって長生きを実現している再発進行がんの患者がいることだけは確かである。
極少量抗がん剤療法の効果を裏付ける研究
| [図1:ラットがんに対する低用量化学療法の効果] 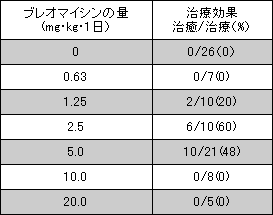 細田さんらはラットにがん細胞を移植し、移植後8~12日 の5日間、抗がん剤ブレオマイシンを投与した [図2:がん化学療法の主な免疫学的効果] 梅澤さんが実践している「少量の抗がん剤と免疫療法を組み合わせた治療法」は、実は動物実験レベルではその有効性が証明されている。北海道医療大学看護福祉学部教授の細川真澄男さん(元北海道大学教授)は、71年から98年まで10数回、動物実験でさまざまな免疫療法に化学療法を併用した「がん免疫化学療法」を試み、良好な治療成績を得ている。また、動物実験で「抗がん剤をたくさん使用した場合よりも少量使った場合のほうが治療効果は高く、治療成績で優れている」ことを明らかにし、発表している(図1参照)。 がん細胞は生体の免疫反応から逃れながら、免疫による攻撃をうまくすり抜けながら増殖していく力を持っている。この「免疫逃避機構」と呼ばれる力は、進行がんでは強くなるという。そのため、進行がんの治療では、がん細胞の免疫逃避機構をどうやって打ち破るかがポイントになる。多くの抗がん剤にはがん細胞の抗原性を増強したり、免疫感受性を増強したりする作用がある(図2参照)。つまり、抗がん剤にはがん細胞を傷つけて「これが、がん細胞だよ」と生体の免疫に示す働きがある。その結果、それまで免疫反応から逃れていたがん細胞をターゲットに、生体の免疫が有効な攻撃を行うことができる。少量の抗がん剤を用いたがん免疫化学療法では、そんな反応が生体内で起きるようだ。 細川さんは、次のように述べている。「進行がん患者に成立している免疫逃避機構をそのままにしていては、どんなに優れた免疫療法でも十分な効果を発揮することは期待できない。われわれの動物実験での研究成果は、低用量がん化学療法がさまざまなタイプの免疫逃避機構を打破し、宿主のがん細胞免疫応答性を回復させ得ることを示している」 (「癌と化学療法 」2000年6月 ) |
梅澤充さんは石岡市医師会病院外科(火・水・金曜日。茨城県石岡市)でも診療を行っている
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬