化学療法と栄養療法併用で予後改善にも期待 栄養改善で元気回復!膵がん化学療法継続の秘訣
経腸栄養剤により栄養状態が改善
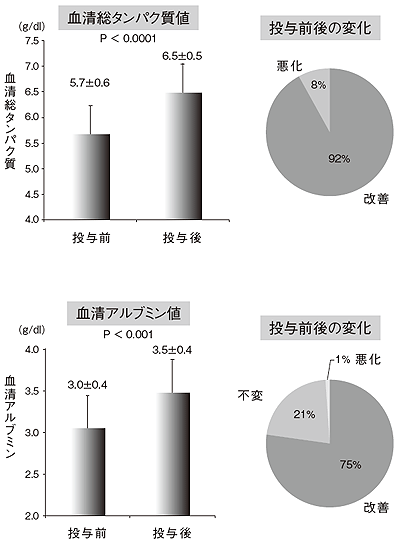
栄養療法のもう1つの柱は経腸栄養剤の服用だ。
経腸栄養剤とは消化吸収機能が低下し、十分な栄養が摂れない場合に栄養補給を目的として、飲むかチューブを用いて胃や腸に入れる栄養剤をさす。日本では医薬品と食品とに分類されており、製剤の吸収の形態によって、「成分栄養剤」「消化態栄養剤」「半消化態栄養剤」に分けられる。
国内で唯一、医薬品として医師が処方する成分栄養剤のエレンタールはタンパク質としてアミノ酸が配合されている。タンパク質は消化されてアミノ酸となり吸収されるが、アミノ酸の形で摂取することで消化の過程を経なくても吸収できるのだ。
また腸の運動を刺激する脂質は必要最小限に抑えられ、食物繊維が入っていないので便の量は少なく、硬くならない。
「タンパク質、糖質、脂質のほか、電解質、ミネラル、ビタミンが含まれ、栄養価が高いこと、消化を必要とせず吸収されるので胃腸に負担をかけず栄養状態が改善できることから利用しています。問題となるのは浸透圧の関係で起こる下痢くらいで、安全に使えます」
庄さんらは化学療法中の患者さんに行った、エレンタールを使った栄養サポートの結果をまとめた。
対象とした患者さんはTS-1またはジェムザールで治療中の、48歳~79歳までの膵がん患者さん24人(男性16名、女性8名)。血液検査で栄養状態が落ちていることがわかった時点でエレンタールの服用を開始し、投与前後で血清総タンパク質と血清アルブミンの値を比較した。
その結果、血清総タンパク質値は平均5.7から6.5に、血清アルブミン値も3.0から3.5に上昇。エレンタールの摂取により栄養状態が改善されることが明らかになったのだ(図4)。
飲みづらさを克服して継続させる
エレンタールは1包を水で溶かして300mlの溶液にし、直接飲むか、細いチューブを鼻から胃、または十二指腸あたりまで入れて、時間をかけてゆっくり流し込む。これで300キロカロリー摂取できるのだが、独特のにおいや味がついているため、飲みづらいと訴える患者さんが多い。
そこで飲みやすくするために青りんご、パイナップル、ヨーグルトなどのフレーバーを混ぜてにおいをやわらげたり、ゼリー状に固めて食べたり、とろみをつけるなどさまざまに工夫することができるので、医師や看護師さんに相談してみることをお勧めすると庄さんは言う。
「抗がん剤治療中はにおいや味に敏感で、味覚の変化が起こっている患者さんも多く、『これを飲むくらいなら、食事を頑張って食べます』と言う患者さんもいらっしゃるほど、長続きしないケースが目立ちます。改善策としての決定打はないのですが、乳酸菌飲料のようなさわやかなものに混ぜると飲みやすくなったとおっしゃる患者さんや、ゼリーだと飲めると言われる患者さんもおられました。味の好みは個人差が大きく、ご自身で少しでも飲みやすいものを見つけていただきたいと思います」
庄さんは患者さんに血液検査結果を示して改善していることを実感してもらい、栄養状態を良好に保つ必要性を根気よく説明するようにしている。
「実際に数値で見たり、むくみがとれたり、自覚できるものがあれば、継続する意欲となります」
また栄養療法を理解する看護師や管理栄養士からも患者さんに話しかけてもらったり、口腔外科医師と連携して口腔ケアによる味覚障害の軽減を試みるなど患者さんのサポート体制を整えている。
化学療法を続けるためにも栄養療法を
栄養療法は、現在、上部(食道・胃・十二指腸)消化管のがんや口腔がんなどで取り入れる施設も増えてきたが、普及しているとは言い難い。
「むくみが出るほど状態の悪い患者さんでも抗がん剤が効いたり、栄養状態が回復してきたら元気を取り戻します。だからあきらめないでほしいのです。化学療法の継続・完遂と患者さんのQOL(生活の質)の保持に栄養療法が大切であるということを理解して実行していただきたいと願います」
成分栄養剤に含まれるアミノ酸には腸管粘膜を保護したり、抗炎症作用などの効果があることがわかってきており、抗がん剤で傷んだ消化管の粘膜を改善させることができるのではと注目されている。単なる栄養補給だけでなく、粘膜障害という副作用予防への応用も期待される。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント
- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!
- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬


