患者ケア特集 薬剤の特徴や副作用、対処方法を知っておけば、外来化学療法は怖くない 外来化学療法の副作用対策はセルフチェックが何より大事
手軽な飲み薬でも副作用が強い場合も
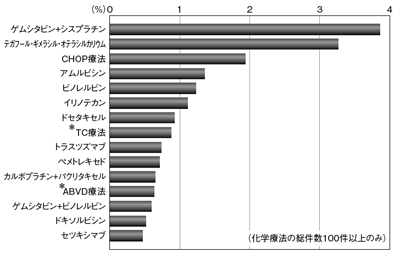
国立がん研究センター東病院における調査では、外来化学療法で重篤な有害事象の発生率が高い治療薬としては、進行胆道んに使われるジェムザール(*)+シスプラチン(一般名)、悪性リンパ腫に使うCHOP療法(*)、小細胞肺がんに投与するカルセド(*)、肺がんや転移性大腸がんに使われるカンプト/トポテシン(*)、乳がん、非小細胞肺ほかに使うタキソテール(*)、タキソール(*)、ナベルビン(*)などがあげられる。中でも、後藤さんが注意を呼びかけるのは、胃がん、膵臓がん、非小細胞肺がんなどに使われるTS-1(*)だ。
「飲み薬の抗がん剤は扱いも簡単で手軽ですから、患者さんにはありがたい薬。でも、意外にも副作用が強いので、注意してください。内服薬だから安全と、過信しないことが大事です」
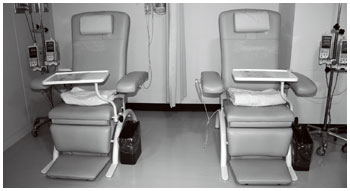
[患者さんに配布されている治療の記録表]
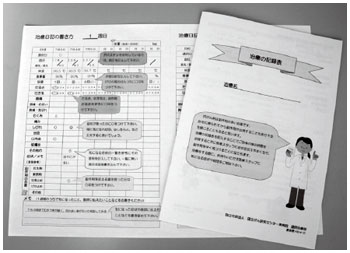
副作用で注意したいのは、患者さんが自分でわかる副作用と、自覚できない副作用があること。吐き気やおう吐、手足症候群(後出)などの皮膚症状は見逃されることはないが、先にあげた発熱性好中球減少のような血液毒性(骨髄抑制という)や間質性肺炎の初期は自覚症状が出にくく、症状が出たときには重症化していることが少なくない。基本的に医師の指示どおり、定期的に検査を受け、結果を必ずチェックしてもらうことだ。
*ジェムザール=一般名ゲムシタビン
*CHOP療法=エンドキサン(一般名シクロフォスファミド)+アドリアシン(一般名ドキソルビシン)+オンコビン(一般名ビンクリスチン)+プレドニン(一般名プレドニゾロン)
*カルセド=一般名アムルビシン
*カンプト/トポテシン=一般名イリノテカン
*タキソテール=一般名ドセタキセル
*タキソール=一般名パクリタキセル
*ナベルビン=一般名ビノレルビン
*TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
*レジメン=薬の組み合わせや投与方法
*TC療法=タキソテール+エンドキサン
*ABVD療法=アドリアシン+ブレオ(一般名ブレオマイシン)+エクザール(一般名ビンブラスチン)+ダカルバジン(一般名)
白血球減少や消化器症状。倦怠感や皮膚症状も
骨髄抑制・間質性肺炎
自覚症状は少ないが、熱やだるさなどの自覚症状を感じたら、とにかく医師に連絡をとること。
「薬を投与して24時間以内は、薬の副作用で熱が出る可能性があります。これに関しては、ある程度仕方がないのですが、その後、白血球が低下してくる時期に感染を併発すると、重篤な感染症を併発する可能性があります。下痢や食欲不振などで水分もとれないようなときは、一刻も早く受診することをお勧めします。
間質性肺炎は症状が出始めると、一気に悪化する可能性があります。咳や息苦しさなどには日ごろから気をつけてください」(市川さん)
吐き気・おう吐
今はよく効く吐き気止め(制吐剤)があるので、あらかじめそれを飲むことが最大の対策だ。
「吐き気が出る頻度が高い化学療法を行う場合には、カイトリル(*)などの5-HT3阻害薬、ステロイドとイメンドカプセル(*)という制吐剤をガイドラインどおりに使ってもらえれば、ほぼOKだと思います。それでも治まらないときは、ナウゼリン(*)やプリンペラン(*)など他の制吐剤や制吐効果のある向精神薬なども併せて処方してもらいましょう。そして、吐き気の治まった隙間を利用して、消化が良く、臭いの気にならない食事をとるようにします。アイスクリームや果実、お菓子などでもOKです。水分の摂取も心掛けてください」(後藤さん)
「吐き気は、体が抗がん剤を吐き出そうとして起こるもの。ですから、抗がん剤が体内からなくなってくれば、症状は軽快してきます。それを知っていると、症状はずいぶん改善するようです」(米村さん)
*カイトリル=一般名グランセトロン
*イメンドカプセル=一般名アプレピタント
*ナウゼリン=一般名ドンペリドン
*プリンペラン=一般名メトクロプラミド
皮膚障害は軽く見ないで早め早めの対処が大切
食欲不振
薬ですっきり改善するのは難しいが、食事の内容や食べ方の工夫で食べられるようになることがある。そうした工夫を冊子にして出版している病院もあるので、参考にしよう。
「抗がん剤を投与して2~4日目は、とくに吐き気が強く出ます。そういうときは無理に食事をとらず、水分補給を十分に行います。看護師としては栄養士さんにも相談し、食事を作る奥さんなども交えて、どんな食事なら食べられそうか、一緒に考えるようにしています」(市川さん)
下痢・便秘
いずれも、早めに薬をもらい、症状を取り除くことが大事だ。
「便秘は出ない期間が長くなると硬くなり、さらに出にくくなります。下剤と緩下剤をうまく使い、規則正しく排便できるようにすることです。下痢で注意が必要なのは、軽いとき止痢剤(下痢止め)をむやみに使わないこと。止痢剤を使いすぎると、逆に便秘になり、重篤化すると腸閉そくになることがあります。むしろ、ビオフェルミンのような整腸剤を日常的に使うようにします」(後藤さん)
皮疹・手足症候群
肺がんのイレッサ(*)、タルセバ(*)、腎がんのネクサバール(*)などでは、ニキビ状の発疹が出たり(皮疹)、ツメの縁に炎症が起きたり(爪周囲炎)、手足の皮膚が腫れて痛んだりする(手足症候群)ことも。
「こうした皮膚症状は症状が出たら、早めにステロイド軟膏を使いながら積極的に治療をします。皮膚科と連携することも大事です。ステロイド剤は予防には使いませんが、皮膚症状が起きる可能性のある抗がん剤を使うときは、保湿剤などで乾燥対策をし、ビタミン剤を投与しながら、悪化させないようにしていきます。できるだけ長く飲み続けたい薬なので、重症化したときは休薬も検討し、症状をコントロールしましょう」(後藤さん)
*イレッサ=一般名ゲフィチニブ
*タルセバ=一般名エルロチニブ
*ネクサバール=一般名ソラフェニブ
治療法のない倦怠感、末梢神経障害も工夫で緩和
むくみ
むくみでよく知られているのは、タキサン系抗がん剤(タキソール、タキソテール)。
「ステロイドを予防的に投与すると効果があるとの報告がありますが、当院ではあまり使っていません。リンパ節を切除した乳がんの患者さんは、腕がひどくむくむことで知られていますが、抗がん剤のせいなのか、手術の後遺症なのかを見極めることが大切。後遺症の場合はステロイド剤を飲むより、むしろリンパ・マッサージのほうが有効ということもあります。専門家にも相談してください」(後藤さん)
末梢神経障害
指先がしびれたり、足の裏の感覚が鈍くなったりする末梢神経障害。今のところ、特効薬はないが、「生活にどんな影響が出るかを考え、2次障害を防ぎます。たとえば、足の感覚がマヒして転倒しやすくなったり、指の感覚がなくて熱いものがわからなかったり、ということが起こります。ラッシュ時をできるだけ避けて外出する、足元に物を置かない、などを心がけるようにしましょう」(市川さん)
「車の運転も要注意です。足の裏がしびれていると、アクセル・ブレーキの踏み心地が変わります」(米村さん)
倦怠感
倦怠感はがんが進行すると必ず出てくる症状であり、副作用とは必ずしも言い切れない。そのため、対処が難しい。
「『ステロイド剤を使うと楽になることがあります』と申し上げるのが精いっぱいですが、がんの進行に伴うほかの症状を取り除くと、同時に倦怠感も和らぐことがあるので、まず、医師にご相談ください。化学療法中は、ある程度付き合っていく覚悟も必要になります」(後藤さん)
「決定的な解決法はありませんが、治療のどのタイミングで倦怠感が出るのか検証し、1番つらいときに十分に休息が取れるように生活上の工夫をします」
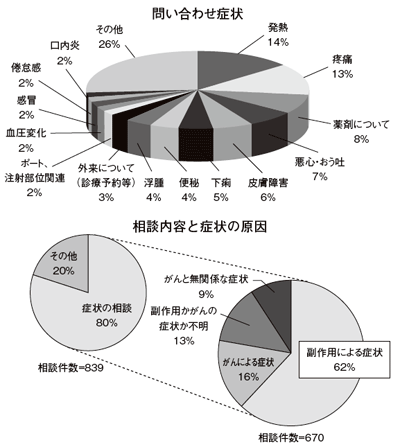
異常を感じたら遠慮せずに医療者に相談
いずれにしても、患者さんは自分の治療に伴う副作用をあらかじめチェックし、症状が出ても落ち着いて対処できるようにすることだ。一方、副作用は人によって出方が違うので、「おや?」と思う異常を感じたら、遠慮せずに医師や看護師、薬剤師に連絡をとることも大事だ。
そしてもう1つ。
外来化学療法は在宅でがん治療が受けられるありがたい方法だが、不安を感じたり、むしろ入院のほうが安心するという人は、そのことを医師や看護師、薬剤師さんに伝えよう。
無理をしない。個人個人に合った化学療法の方法があるので、できるだけ楽な道を探す。これが何よりの副作用対策といえるだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


