無理をせず、できる範囲のセルフケアを心がけて、治療を続けていこう つらい血液がん化学療法の副作用は治療とセルフケアで上手に付き合う
白血球数が下がっている間は生ものは避けるべき
骨髄抑制がある時期の食生活では、生ものを避けるべきです。その理由は、感染症になる可能性があるためです。とくに、骨髄抑制によって抵抗力が低下していると、ひどい下痢になったり、おう吐をしたり、場合によっては重篤な状態に陥ることがあります。
「患者さんに食べたいものを聞くと、多くの方がお寿司、焼肉、おそば、たまごサンド、サラダなどを挙げます。しかし、白血球が低下している時期に食べてもいいのは、このなかでは焼肉だけです」
お寿司は生ものなので、もちろんですが、たまごは殻にサルモネラ菌が付着していることがあり、調理形態によってはそれが残っているため危ない、と清弘さんは説明します。
「おそばは温かいものなら大丈夫ですが、ざるそばなどは要注意です。水が清潔かどうかが問題なのです。ミネラルウォーターでおそばを洗うなど、水が清潔ならば問題ないのですが、外食や市販のものの場合は、調理形態がわからないので要注意。お豆腐なども同様の理由で避けたほうがいいかもしれません」(清弘さん)
サラダを食べてはいけないのは、生野菜なのでやはり水に問題があるのと、土が付着していると、そこに菌が混入している可能性があるためです。
結論として、骨髄抑制がある時期には、火を通しているものを食べるのが安全ということです。焼肉でもレアは×、ウェルダンが○。もちろんユッケは×です。ただし、白血球の数値が上がってくれば、その限りではありません。
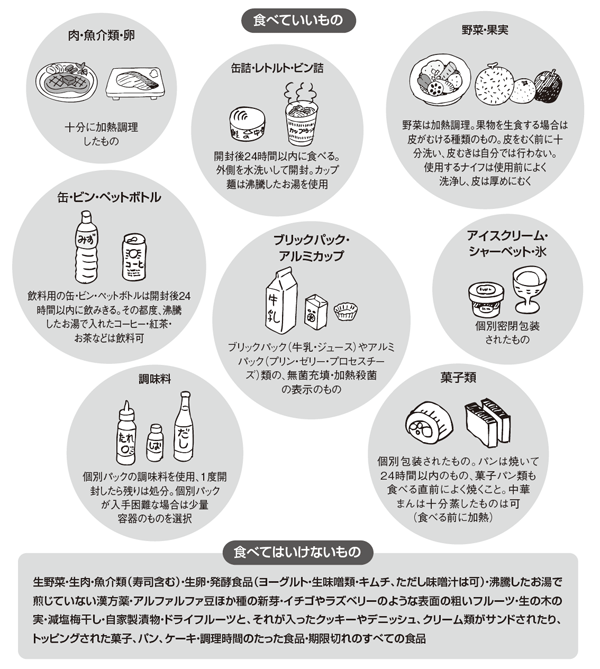
症状に過敏にならず無理をせずに過ごす
骨髄抑制などに伴って、化学療法の1~3週目ぐらいに現れるのが倦怠感です。白血球が減少すると極端にだるくなり、トイレだけはなんとか行って、あとは横になっていたいほどの状態になることもあるようです。テレビをよく見ていた人が見なくなったり、本好きな人も読まなくなります。起き上がったり、動いたり、考えることすら面倒になってしまい、声を発するのさえ嫌なこともあるのだとか。
しかし、白血球の数値が上がり始めると元気になるので、あまり過敏にならず、つらい数日間をいかにやり過ごすかが大切だといいます。
「なかにはけっこう元気な方もいますし、だるさとうまく付き合える人や、副作用を治療の効果として受け入れる人もいます。痛みと同じで、人それぞれの許容範囲があり、倦怠感も低い人と高い人がいるようで、個々人のとらえ方といえます。白血球の数値が良好でも肉体的には不調という人、数値とともに着実に元気になる人、あるいは数値が低くても元気な人もいます。
現在、倦怠感を和らげる薬はとくにありませんが、あまり数値などには過敏にならずに、無理をせず、できる範囲のことだけをなさればいいでしょう。白血球が上がれば必ず元気になると希望を持って過ごせば、落ち込まずに済むと思います」(清弘さん)
周囲の人々の理解も大切です。看護においては、検温や食事の時間も、その人の体調に合わせてずらすなどの対応をしているそうです。
「血液がんの患者さんは、胃がんなどの固形がんの患者さんと違って、手術で大きく切られたりしていないので、見た目は元気なんです。ステロイドの副作用でふっくらしたり、食欲が出たりして元気に見えてしまいます。『太ったじゃない』とか『元気ね』とお見舞いにきた友人などから言われ、ショックを受けている患者さんは多いです。
実は、患者さんは治療の繰り返しによって確実に体力・気力ともに萎えていることを周囲の人は理解してあげることが大切です。自宅に戻られても、患者さんがだるそうにしているのを、家族や周囲の人は、わがままだとは思わないでください」(小林さん)
食べたいものを探して食べるという努力も大切
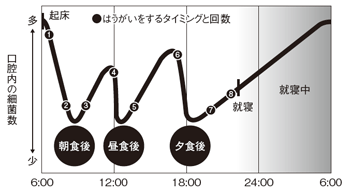
吐き気・おう吐の症状があるときはもちろん、化学療法の期間は、食べる意欲をなくすケースが往々にしてあります。
「食欲不振のときは、”食べたいと思い浮かんだものを、食べたいときに、ほどほどに”が大切です。白血球数が下がっているときは生ものは禁止ですが、上がってくれば普通に食べてもかまわないですし、血液がんにおいて、これを食べてはいけないというものはとくにありません。自分のおなかの調子と相談してもらえばいいと思います」(清弘さん)
食べたくないときには無理に食べる必要はないそうですが、患者さんのなかには、食べること=元気になることと考えて食べる人や、口内炎で痛みが出ていたり、吐き気・おう吐があったりしても食べるほど、食べることを楽しみにしている人もいるそうです。
食べられるものは何かしらあると思いますので、大事なことは、食べられるものを自分で探すということです」(清弘さん)
水分だけでもとって胃腸を動かしておく
たとえば、食欲不振のときに、思い浮かぶ食べやすいものの代表は、プリンやゼリー、フルーツジュースなど甘いものばかりなのだとか。甘いものが嫌いな人は、自分でテリーヌや煮こごりのようなムースやゼリー状のもの、自分の好きな味のスープなど食べやすいものを見つけることが大切です。インスタントのカップ麺などを好んで食べられる方は多く、味の濃いものは食べやすいようです。
2週間ぐらいなら食べなくても、栄養は点滴でとれますが、できれば経口摂取をするべきだといいます。胃腸を多少でも動かしておかないと、後々、体力回復が難しくなるのです。
「水分だけでもいいので、とってほしいと思います。コーラなど炭酸飲料は、スッとして気持ちがいいようです」(清弘さん)
病院ではグレープフルーツ系は薬との相互作用があるため、全部抜いてありますが、少々味を添加してあるぐらいのものなら問題はないそうです。
患者さんのなかには、入院中は欠かさずグルメ番組を見て、食べたいものを探して、退院後の楽しみにしている人もいるとか。がん患者さんが自ら作った料理のホームページやブログなどで調理方法をチェックして、食べられるもののレパートリーを増やす努力をしている人もいるといいます。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


