抗がん剤の副作用「皮膚障害」にどう対処する? 早期発見・早期治療で重症化を防ごう!
抗がん剤が漏れたらどうする?
早期発見がポイント。重症化しやすい「漏出性皮膚炎」を防ごう!
漏出性皮膚炎
もっとも注意しなければならないのは、抗がん剤が血管外に漏れたときに起こる“漏出性皮膚炎”です。
「点滴の針がうまく血管に入っていなかったり投与中に抜けたりして、血管や皮膚、皮下組織が抗がん剤の薬液に直接さらされるために、痛みや腫れ、しびれなどが起こるものです。血管自体が抗がん剤の作用で傷んでいて漏れるケースも少なくありません。薬剤によっては皮膚が潰瘍化して治りにくくなり、最悪の場合は壊死することもあります。予防と早期発見、早期治療によって重症化を防ぐことができるので、患者さんも、漏れに気づいたらすぐ医療者に伝えていただくのが最大の対策です」
抗がん剤は、皮膚等の組織に与える影響や危険度により3つのグループに分類されています。少量の漏れでも強い痛みや炎症、難治性の潰瘍を起こしやすく、もっとも注意を要する薬剤はビシカント・ドラッグ(起壊死性薬剤)、大量に漏れたときに炎症を起こす薬剤はイリタント・ドラッグ(炎症性薬剤)、漏れても炎症を起こしにくいものはノンビシカント・ドラッグ(起炎症性薬剤)と呼ばれています。下の表を参考に、投与中または予定されている薬剤がどれにあたるかを覚えておくとよいでしょう。
なお、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)など、薬剤によっては漏れに関係なく、投与後に血管痛を起こすものもありますが、治療終了後は治ります。
| 種類 | 商品名(一般名、略語) |
|---|---|
| 少量でも炎症を起こす ビシカント・ドラッグ | |
| 抗がん性抗生物質 | アドリアシン(ドキソルビシン、DER) ファルモルビシン(エピルビシン、EPI) マイトマイシン(マイトマイシンC、MMC) |
| 植物アルカロイド | オンコビン(ビンクリスチン、VCR) フィルデシン(ビンデシン、VDS) エクザール(ビンプラスチン、VLT) タキソール(パクリタキセル、PTL) |
| 多量に漏れると炎症に イリタント・ドラッグ | |
| アルキル化剤 | パラプラチン(カルボプラチン、CBDCA) ランダ、ブリプラチン(シスプラチン、CDDP) エンドキサン(シクロホスファミド、CPA) アクプラ(ネダプラチン、254-S) |
| 代謝拮抗剤 | 5-FU(フルオロウラシル) |
| 植物アルカロイド | タキソテール(ドセタキセル、TXT) トポテシン、カンプト(イリノテカン、CPT-11) ラステット(エトポシド、VP-16) ジェムザール(ゲムシタビン、GEM) |
| 漏れても炎症を起こしにくい ノンビシカント・ドラッグ | |
| 抗がん性抗生物質 | TS-1など(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム、TGF) メソトレキセート(メトトレキサート・MTX) キロサイド(シタラビン、Ara-C) |
「漏出性皮膚炎」の予防法
(1)針が抜けないように注意
医師や看護師さんは、点滴の針が抜けないように、なるべく関節から離れていて動きにくく、平らにキープできる場所を選んで針をさし、針先に力がかかりにくいループ状にしてとめます(下イラスト参照)が、患者さんも注意が必要です。
「抗がん剤の投与中に読書をしたり、点滴スタンドを押してトイレに行くのはかまいませんが、管(ルート)を過度に動かしたり、引っ張ったり、体の下に敷いたりしないようにしましょう」
(2)移動時は管を衣類にとめて
長時間の点滴や入院中で、トイレなどへの移動回数が多いときは、管の1部にテープを貼り、安全ピンをつけて衣類にとめておくと、管が引っかかるのを防げます。
飯野さんより一言
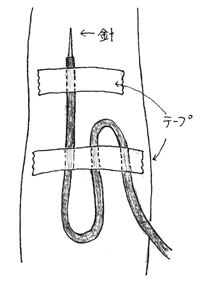
点滴針のとめ方にご注目!
点滴の針は、透明ドレッシング剤と呼ばれるテープで、針先がよく見えるようにしてとめるのが普通です。針に続く管(ルート)をS字状に曲げてとめるのは、管に力がかかっても針先に直接影響しないようにするためです。
早期発見のコツ
(1)痛みや腫れがあったらSOS
点滴の針をさした後、針周辺の痛みやツベルクリンの陽性反応のときのような赤みや腫れ、違和感、灼熱感、しびれなどの症状が起こったら、漏れている可能性がありますから、薬剤の種類によらず、すぐに医師か看護師さんを呼び、漏れの有無をチェックしてもらいましょう。また、点滴が染み出してテープが濡れているのも漏れのサインです。
「看護師さんも定期的に巡回・点検していますが、患者さんも30分に1回くらい、点滴の落ち方や針の周囲を見て、漏れがないか確認するといいですね」
(2)輸液ポンプによる投与なら
最近では、抗がん剤や制吐剤が最大の効果を発揮するように、点滴スピードや量を設定して、決められた時間内に自動的に注入する輸液ポンプと呼ばれる機械を使うケースが多くなっています。
点滴の針が血管に正しく入っているかどうかを血液の流れで確かめることがありますが、ポンプ使用時に血液が逆流するときは、何らかのトラブルがあると考えられます。
「ポンプの場合、さまざまな異常を察知しアラームが鳴ります。たとえば、点滴のチューブが折れ曲がったり、血管内から皮下の組織に薬液が漏出するなどして滴下時に抵抗を感じる場合です。しかし、針が抜けたり接続部分がはずれたりした場合は、漏れていても抵抗がないためにポンプは何のサインも感知せず、どんどん抗がん剤が落ちてしまいます。アラームに頼りすぎず、患者さんも針の周辺に薬液が漏れていないか、赤みや腫れなどが出ていないか、ときどき確認しておきましょう」
(3)帰宅後の異常も見逃さないで
高齢者の場合や、針をさした場所によっては、抗がん剤の漏れがあってもあまり痛みを感じないことがあります。また、帰宅後、腫れ等の異常に気づいてもそのまま放置して症状を悪化させてしまうケースがままみられます。
「翌日から数日後に症状が現れることもありますから、しばらく観察するといいですね」
漏れたときの対処法
(1)まず、医療者に連絡する
なんらかの異常や漏れの兆候に気づいたときは、病院でも帰宅後でも我慢せずに、すぐ医療者に連絡をとり、指示を受けましょう。「早期に見つけて連絡し、すばやく対処してもらえば大事に至らずにすむことが多いものです」
(2)自己判断で処置しない
痛みや発赤があるとき、もんだりおさえたりするのは厳禁です。
「一般的な医療処置として、抗がん剤の拡散防止と消炎のために冷やすことが多いのですが、オンコビンなどビン化アルカロイド系やエトポシドなど、冷却しないほうがよい場合もあります。また、温めると、普通は薬剤の吸収を促進させてしまうので、素人判断で冷やしたり温めたりせず、医療者の指示どおりにしましょう」
(3)医療的処置は
「薬剤によって、リバノール湿布か生理的食塩水などの湿布をするほか、ステロイド剤の注射などの処置がされます」
「イレッサ疹」は角化治療薬で改善する!
肺がん治療の新薬として注目される一方で、間質性肺炎などの副作用が問題となっている「イレッサ」。実は、この薬剤の副作用としてもっとも高い頻度でみられるのは「発疹」です。「使い始めてすぐにニキビ様のイレッサ疹が顔や体に出てくる患者さんが多いですね」と、飯野さん。 第2相国際共同臨床試験の副作用評価では、日本人51例中、発疹は62.7パーセント、そう痒症49パーセント、皮膚乾燥33.3パーセントと報告されています。 「発疹ができても、かゆくて生活できないというほどではありませんが、化膿しないように皮膚を清潔に保ち、気になるときは薬剤を処方してもらいましょう。現在のところ、角化治療薬のウレパール(商品名)がイレッサ疹に効果的だといわれています」
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


