不安やストレスを軽減する心のサポートの重要性 正しく理解することから始まる、症状緩和のセルフケア
家族が相談し合い、家族全員で情報を共有しよう
従来、日本のがん医療では患者本人に病名を隠して治療を行うのが普通でした。その結果、患者さんを孤立させ、抗がん剤の正しい情報も本人に伝わらず、ことさら副作用のために苦しませていた面があります。現在では患者本人への告知が普通に行われるようになり、家族で情報を共有できる環境が整ってきました。
がん専門病院で、患者や家族を対象に、がんの告知に関する調査を行ったことがあります。「(患者にがんを)告知してよかったですか?」という質問について、「よかった」という答えは、患者本人より家族のほうが割合が高いことがわかりました。がんが告知されていれば、家族は患者さん本人に気兼ねなく病気のことを相談できます。たとえ家族が治療について判断するにしても、最終的には「本人はどう考えるのか?」と相談できるわけですから、「告知してもらってよかった」ということになるわけです。
ところがそうではなくて、医師から家族への告知が先に行われて、医師が「ご本人への告知はどうしますか?」と相談するのがあとになるとしましょう。家族は「伝えたほうがいいのだろうか」と最後まで悩みます。そうすると、家族にだけシビアな症状が次々に伝えられることになるわけです。
こうなると、家族のストレスが非常に高くなってしまいます。がんで不安を覚えるのは患者さんだけではなく家族も同様です。患者さん本人に病気が告知されていないということになれば、家族にだけ非常にシビアな病状が伝えられることになります。
逆に、家族がともに相談し合うことができれば、患者さんの不安も緩和されることになります。治療についての正しい情報も届くので、患者さんはたとえ抗がん剤の副作用が出てもそれほど不安を感じなくてすむわけです。
ただし、医療者側にとって難しいのは、病院を訪れる人のどの範囲までを「家族」と考えるかということです。たとえば「病院へよく来るのは患者の息子の妻であり、治療の選択などの意志決定者は息子で、もう1人、意志決定をする重要な立場にあるのが遠方にいる娘である」というケースもあるでしょう。すると、医療者が患者の病気について、この3人に別々にそれぞれ同じ内容の話をしても、理解していることがバラバラということになりがちです。
このように患者を支える人の間で認識のズレがあることがわかると、患者本人の不安は高まってしまうかもしれません。
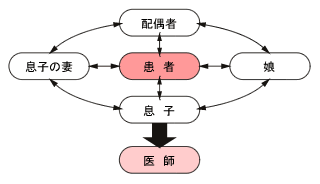
患者の大事な時期の方向性を決める家族は、情報を共有することが必要です。患者を支えていく範囲にいるメンバーは、医療者から患者さんの話を聞くとき、普段は遠方にいる人も含めて、なるべく一堂に会するようにすることをお勧めします。
また、治療が長くなるにつれ、抗がん剤への反応が悪くなるなど方向転換の時期を迎えることもあります。患者さんが「もう治療をやめたい」と主張したり、病院を変えようという話が出てくるかもしれません。そういうケースで、患者さんも家族も意志統一をするためには、情報を共有しておくことが重要です。
抗がん剤の入院治療が多かった時代は、患者さんや家族に病気や薬の副作用などの情報はあまり伝わりませんでした。しかし、通院治療が増えるとともに、たとえば「そろそろ白血球が下がる」といった情報は家族も知って、日常生活に配慮しなければならないという点が出てきました。
また、主婦の患者さんなどは抗がん剤治療が始まっても、「家のことが心配で寝ていられない」と家事労働を続けようとする面があります。しかし、健康なときと同じように働くことは無理と考えるべきです。周囲の家族ができることは進んでサポートし、家事の負担を少なくしてあげなければなりません。
また、よく使われている抗がん剤のタキソール(一般名パクリタキセル)などは、しびれという副作用があり、家事をこなすのに支障が出ますが、そうした薬の特性なども周囲の家族はわかってあげて、適正な援助をすることが必要です。
一方、抗がん剤の効果により回復する過程では、一見元気に見えてしまうこともあります。しかし、じつは治療中は体力を消耗するし、見た目ほど回復していないことも周囲は理解してあげることが必要です。いたずらに「がんばれ」と励ましたり、「もっとたくさん食べられるよ」と食事を押し付けたりしてはいけません。家族できちんと情報が共有されていれば、そんなことはないはずです。
副作用の現れ方を記録し、次回の症状を予測する
抗がん剤治療の不安やストレスを和らげるためには、患者さんの自助努力も大切です。
たとえば抗がん剤治療は、長期にわたって同じメニューを何クールかを繰り返すのが普通ですが、1クール目で経験したことを2クール目、3クール目の治療を受けるときの参考として活かすことができます。1クール目の1日目で副作用はどうだった、2日目はどのように出たというようにノートに記録しておくと、2クール目では「今日はちょっと副作用がきついけれど、あと1、2日で楽になっていくはずだ」と、予測を立てることができるわけです。
これは医療者などから教えられるよりは、ずっと自分を納得させられるのではないかと思います。すなわち、「患者として成長」することができるのです。
患者さんの状態は、治療を受ける中で日々状態が変わるし、個人差もあります。症状は「なんとなく不快」とか、「なんとなくだるい」というように、必ずしも数値で表せないこともあるし、その人独自の症状があります。だからこそ、患者さん本人の記録が役立つのです。
患者さんがこうした『自分ノート』を医療者に見せて情報を共有し合うことができれば、「この症状は前回も何日目に出たのでしたね」というふうに、相互の理解もいっそう進み、もっと前向きに抗がん剤治療を受けられるようになるでしょう。
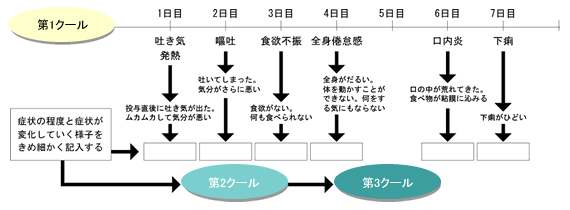
がんの患者さんは、病気にも治療にも大なり小なり不安やストレスを感じるものです。がんと告知されれば、多くの人が気分の落ち込み(抑うつという)を覚えるともいわれます。
さらに重い落ち込みが2~3カ月以上続き、「うつ病」や「適応障害」などの精神疾患を併発する人も少なくありません。同じがんの患者さんでも、うつ病がみられると、治療の予後に悪影響するという報告もあります。こうした心の問題とがんの関係を研究する「精神腫瘍学」という分野が注目されるようになりました。
また、患者さんの様々な苦痛を緩和するためには身体的な支援とともに、精神科医や精神科領域のナースなども積極的にかかわりつつあります。
抗がん剤治療を受けていく過程で、自分で解決できない不安やストレスに直面したら、担当の医師や看護師とともに、このような心のケアを専門的に行っている担当者や部門がないか確認し、可能であればこうしたサービスを積極的に活用してください。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


