副作用はもう恐れることはない 正しく理解することから始まる、症状緩和のセルフケア
体を清潔に、歯磨きを励行し、怪我をしないこと
抗がん剤治療の副作用を予防するためには、医療者から出された指示を守ることが重要なポイントです。中でも骨髄機能抑制により様々な感染症にかかりやすくなることから、例えば口内炎の予防のために口に氷をくわえること、うがい薬でうがいをすること、ヒビテン(一般名塩酸クロルヘキシジン)などを用いて痔の治療を行うことなどが指示されるでしょう。
また、抗がん剤が皮下漏出すると、潰瘍など重篤な副作用が起こるので、点滴中に手(腕)を動かさないように注意を促されます。
もちろん外来で抗がん剤治療を受ける患者さんは、自発的に生活の工夫をすることが大切です。よくお風呂に入って体を清潔にしたり、歯磨きを励行して口内をきれいにします。
女性の場合は、局所分泌物を清潔に処理してもらう配慮が必要です。さらに血小板が下がったときは、転んで怪我をしたりしないようにし、歯ブラシは歯茎を傷つけない柔らかいものを用いるなど、患者さん自身がセルフケアを果たしていくことがとても重要になるのです。
抗がん剤治療の副作用が現われても、初期の徴候をとらえることができ、早目に手を打つことができれば苦痛を小さくすることができます。
医療者から「何かあったら言ってくださいね」と言われているはずです。たとえば血管痛があるとか、風邪を引いたといった場合など、早めに連絡するようにします。
もちろん医療者から指示されたことを適宜実施することは欠かせません。口内炎に軟膏が処方されれば確実に塗り、白血球が低い時期はうがいを励行します。制吐剤にしても、最初は所要量を守り、症状にあわせて医療者に相談しながら、「こう使うのが効果的」というふうに、しっかり自分に合う対処方法を体得していきましょう。
症状を的確にキャッチし、的確な対策をたてる
- 嘔吐
- 悪心(吐き気)
- 脱毛
- 口内炎
- クリニックへの通院時間
- 注射をすること
- 呼吸困難
- 倦怠感
- 不眠
- 家族の不安、仕事のできないことによる焦燥感
治療が進むにつれて経験も蓄積されるので、患者さんの側で自分の状況を判断しながら、主体的に生活のペースを作っていく工夫をします。
血液データが理解できていれば、「1クール目のとき、2週間前後で白血球がここまで下がった」ということがわかるので、「今度は白血球が2000を切るくらいになったらちょっと注意しよう」ということになるわけです。
あるいは前回の治療で何日目に吐き気を覚えて食欲がなくなったということがわかっていれば、今度は治療が始まる前に前回食べることができた食品を買いだめしておくというふうに工夫します。
がん闘病中は何かと余計な心配をしたり、物事を悪いほうにとったりしがちです。しかし、症状の意味を理解していれば必要以上に苦しむ必要はなくなります。
脱毛のように避けて通れない予防困難な症状が現われた場合も、きちんと情報を得ていれば「仕方がない」「心配ない症状だ」というふうに理解できます。もともと抗がん剤は、細胞分裂の激しいがん細胞をターゲットにした薬なので、毛母細胞のように細胞分裂の激しいところに症状が現われがちなのです。
髪の毛の成長サイクルは成長期→退行期→休止期とあります。通常、髪の毛を抜いたとき、根本が丸く膨らんでいますが、これは毛母細胞が働いている成長期にある髪です。一方、部屋の中にパラパラ落ちている根本の膨らんでいない毛は、毛母細胞が休止して起こった脱毛です。髪の毛は本来1本1本がバラバラの成長周期の中にあります。
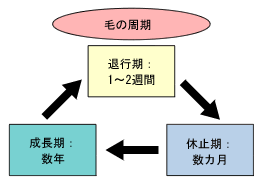
ところが、抗がん剤を使用すると、毛母に働いて、細胞分裂が抑制されます。まるで動物の毛の生え変わり時期のように、頭髪は一気に休止期に進み、数日間で脱毛が終わります。
ただし、さいわいすぐに髪の毛は生え変わってきます。休止期に入っても毛母細胞への影響は一時的なので、まもなく細胞分裂が始まります。髪は新しいサイクル成長期に向かい、3~6カ月のうちに再発毛が生えてきます。もっとも再発毛は、脱毛以前とは性質が異なり、細い産毛状になったりしがちですから、このあたりも知っておいてください。
抗がん剤の副作用を軽く済ませられるように、正しい知識、適切な準備を整えて闘病を乗り切りましょう。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント


