受ける臨床試験の目的、意味を理解することが重要 だれでもわかる臨床試験データの見方・読み方
何例以上なら信用できるか?
「ただし、今、述べたことは、よく効いたかどうかどうかであり、治療の片側を見ていることになります。一方で毒性、有害事象をチェックしないといけません。つまり、いくらよく効いても患者さんが亡くなってしまったのでは何にもなりません。1回目の治療で効果があっても、薬が強すぎて2回目がとてもやれないぐらいになってしまったのではいけない。したがって、副作用のチェックが必要になってきます」
副作用の評価としては、血液学的有害事象と、非血液学的有害事象が問題となる。血液学的有害事象とは、白血球が減ったり血小板が減ったりした場合で、輸血が必要になったり、副作用を抑える薬の投与が必要になるので、試験を続けていくことができなくなってしまう。また、非血液学的有害事象とは、神経のしびれやだるさ、吐き気などがあげられ、これも投与の中止につながる。
副作用は前述したようにゼロから5までのグレードでチェックする。5は死亡で、ゼロなら何もなし。1~2はとくに処置を要さないもの、3~4は点滴をしたりの処置が必要。どのパーセンテージが多いかで、強い治療か、軽い治療かを判定する。
| 無イベント生存 | events free survival | EFS | 再発、増悪、合併症などがなく生存 |
|---|---|---|---|
| 無病生存 | disease free survival | DFS | ほかの病気が発生することなく生存 |
| 無増悪進行生存 | progression free survival | PFS | 病気が進行することなく生存 |
| 全生存 | overall survival | OS | すべてを含めた生存 |
| 無再発生存 | relapse free survival | RFS | 病気が再発しないで生存している |
| 治療奏効維持生存 | failure free survival | FFS | 治療効果が持続している期間 |
| 無進行期間 | time to progression | TTP | 進行するまでの期間 |
「中央値」と「平均値」
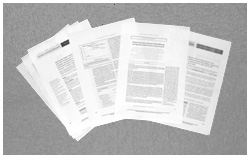
最新の臨床試験データは論文で示される
生存曲線にも注目だ。観察開始から死亡���まりエンドポイントまでの期間を調べて、累積生存率を計算することでその効果を解析する方法だ。生存期間を横軸に、生存している人の割合を縦軸にあらわすことが多い。
生存期間を評価するときは中央値で示されることが多い。中央値とは平均値とは違い、全体の中の真ん中の数値のこと。仮に100人の患者がいたとき、50人目の患者が亡くなるまでの期間、つまり生存率が50パーセントになるまでの期間が中央値だ。
これに対して平均値とは、統計データの総和をそれらのデータの個数で割った値をいう。たとえば、生存期間を横軸に、生存している人の割合を横軸にした図を描いた場合、対象となる患者の生存期間の総和を患者数で割れば平均値が得られる。
平均値は一般によく用いられる統計用語で、サンプルが正規分布しているようなときは中央値とも一致し、わかりやすいが、極端に大きい・少ない値がある場合などは偏った結果を導きやすい。生存期間は多くは非対称の分布をするため、平均値を求めるのでは不適切となる場合が多い。そこで、分布の要として、50パーセント点である中央値を示すのだ。
臨床試験の結果を示されたときは、「中央値なのか」「平均値なのか」を確かめたい。
生存曲線では、目標としている治療が古い治療より上側にあるかどうかで、いいか悪いかを見る。たとえば、新しい治療は5年生存率が58パーセントで、古い治療は45パーセントだったという場合、13パーセントの上乗せ効果があることになり、統計学的に有意であることを示している。一般に、P値(偶然差が出る確率)が0・05未満であれば統計学的に有意であり、その数値が小さければ小さいほどよいスタディであるということになる。
ただし、全体としてよくても、ある群ではその差が縮まったりすることがある。そこで、年齢や性別、リンパ節の数、さらにステージで分類して解析することをサブセットアナリシス(サブセット解析)といい、これを行うことも多い。
危険性を表すハザード比
「あとはハザード比(HR)という言葉がよく出てきます。たとえば、ハーセプチンを投与したかしなかったかで、再発がどれくらい免れたかを検証した試験があったとします。片方の群の再発が100だったとして、ハーセプチンを投与した群はたとえば0・52だったとしたら、再発の危険は48パーセント少なくなった、ということになります。つまり、ある治療を行った群で事象が起こる危険性を100なり1なりとして、もう一方の治療でどのくらいの危険性になるかを数字で見たものがハザード比で、最近の論文によく使われています」
また、「信頼区間」という用語が出てきますが、これは全体の数値のばらつきを示したもので、たとえば、すべての値がこの区間内にある確率が90パーセントの場合、「90パーセント信頼区間」とあらわされます。
畠さんは最近、こんな経験をしている。05年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で、乳がん治療で従来から行われているACT療法にハーセプチンを加えた治療で再発率が約50パーセント下がったという臨床試験の報告があった。すると2日後に「その治療をぜひ私にやってほしい」という問い合わせがあり、あまりの素早さに驚いたという。
臨床試験を吟味するなんて難しいと諦めるのでなく、わからなければ統計学や生物学に多少明るい人の助言を得たり、医師にも積極的に質問して、論文などに挑戦してみてはどうだろうか。
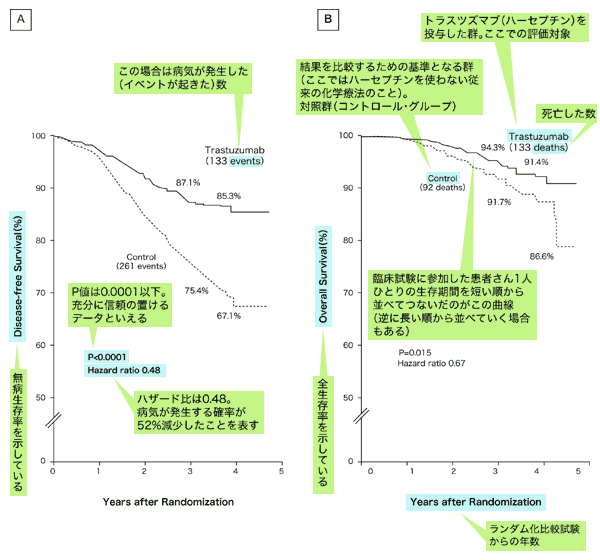
同じカテゴリーの最新記事
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 国立がん研究センター東病院が取得したCAP認定とは? 国際的な臨床試験が日本でもっと行われるために
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性
- 日本初!免疫チェックポイント阻害薬の臓器横断的適応 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)大腸がんにもキイトルーダ承認
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


