安心して臨床試験を受けるための基礎知識 3.抗がん剤の臨床試験は一般薬と違うの?
がん種を限定して行う第2相試験
腫瘍の縮小効果で薬剤を評価
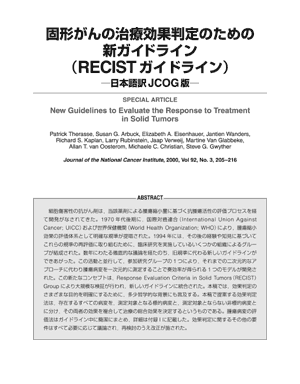
第2相試験からは、多施設共同試験といって、1つの病院あたり5人くらいの患者さんが被験者となり、がんの化学療法の専門家がいる病院が協力して行う。
第2相試験は通常前期試験(第2a)と後期試験(第2b)に分けられ、前期ではどのような種類のがんに有効かということを検討する試験を行う。第1相試験の結果、少しでも効果が出れば、「このがんに有用かもしれない」という見当がつけられるので、そのがん種を対象にすることになるわけだ。また、すでにあるがん種の抗がん剤として承認されている薬剤を、別のがんにも適応するかどうかを見つけるための検討も第2相試験から始める。
第2相後期試験は、「肺がん」とか「乳がん」というように疾患を限定して、より多くの患者さんを対象に実施する。
第2相試験では腫瘍縮小効果(奏効率)が検討される。その効果判定のためには、RECIST(レシスト)と呼ばれる国際規準が用いられるようになった。この基準では、標的となる病変の最長径の長さを測定して、その和を算出して、腫瘍縮小効果をみることになっている。どの程度の効果が得られたかは、次のような4段階で評価される。
・完全奏効(complete response;CR):すべての標的病変の消失。
・部分奏効(partial response;PR):ベースライン長径和と比較して標的病変の最長径の和が30パーセント以上減少。
・進行(progressive
disease;PD):治療開始以降に記録された最小の最長径の和と比較して標的病変の最長径の和が20パーセント以上増加。
・安定(stable disease; SD):PRとするには腫瘍の縮小が不十分で、かつPDとするには治療開始以降の最小の最長径の和に比して腫瘍の増大が不十分。
抗がん剤の有効性(腫瘍縮小効果)は、抗がん剤を投与したことにより、完全寛解(CR)と部分寛解(PR)を示した患者さんが全体の何パーセントを占めるかで判定する。例えばある抗がん剤を50人の患者さんに注射したとき、CRとPRを示した患者さんが20人いたとすればその抗がん剤の「腫瘍縮小効果は40パーセントである」という言い方をする。
「20パーセントから25パーセントの腫瘍縮小率が得られたら、一般に『まあまあ有効な薬剤』とみられています。しかし、この数値はちょっと1人歩きしていると考えなければなりません。例えばそれまでさんざん治療が行われてきた状態で治療を行う場合は、20パーセントにも達しないことがあります。これに対してどんながんでも初回治療はわりと奏効率が高く、60パーセントといった成績を示すこともあるのです。さらに腫瘍縮小効果が優れているからといって、必ずしもそれが最終的な患者さんの利益に結びつくとは限りません」
第2相試験で示される腫瘍縮小効果は「代替指標」であることを知っておく必要がある。抗がん剤の本当の利益とは、生存期間、無増悪生存期間、あるいは症状のコントロールなどによる「生活の質(QOL)」の向上などだ。それらを評価するために長期間のフォローアップが必要になる。
が、抗がん剤の場合、第2相試験の段階で長い時間をかけているわけにはいかず、まず代替指標により効果を判定するわけだ。そして真の利益の証明には、第3相試験での十分な症例数を持ったランダム化比較試験による最終的な検証が欠かせない。
患者さんが不便な思いをする検査も
第1相、第2相では薬物動態の検討も行われる。例えば同じように100ミリグラムという量の抗がん剤を投与しても、ある患者さんではきわめて有効である一方、ある患者さんでは非常に副作用が出て、また別の患者さんでは有効性も副作用も示されないということがある。これはお酒が強い人と弱い人がいるのと同じように、同じ分量の薬が体に入っても、処理されるしくみが大きく異なっているという場合があるからだ。
そこで、ある薬を投与したとき、それが体内でどういう挙動するかを探索することが必要になる。点滴したときに血中濃度がどういうふうに変わるか、どのくらいの量で推移して、どういう効果や副作用あるいは効果が出るか、また皮下脂肪にどのくらい浸透してどのくらい体の中に残るかといったことが検討される。さらに体内でどのように分布するか、あるいは肝臓で分解されるか、腎臓で排出されるか、というふうに分布、代謝、排泄といった薬理学的検討が図られる。こうしたことから、正しい、安全な薬の使い方がわかってくるのである。
「そこでそうしたことを探るため、治験に協力してくれた患者さんは、夜中に叩き起こされたり、1日に5回も10回も採血をする必要が出てきたり、点滴の管を留置したままのこともあります。そのことは事前に医師または治験コーディネーターから説明されるはずですが、いずれにしても治験に参加した患者さんには、検査が比較的多いなどで不便もお願いしなければならないこともあるわけです」
これまで抗がん剤の治験では他の薬剤の治験と大きく異なっていて、この第2相試験が終了した時点で、そのデータをもとに薬剤の製造、または輸入の承認を得るために申請が行われてきた。新薬の恩恵が得られることを首を長くして待っている患者さんの治療に役立てようという考え方が大きかったのだ。
同じカテゴリーの最新記事
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 国立がん研究センター東病院が取得したCAP認定とは? 国際的な臨床試験が日本でもっと行われるために
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性
- 日本初!免疫チェックポイント阻害薬の臓器横断的適応 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)大腸がんにもキイトルーダ承認
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


