安心して臨床試験を受けるための基礎知識 3.抗がん剤の臨床試験は一般薬と違うの?
必須になってきた第3相臨床試験
「患者さんをどれだけ幸福にできるか」という視点
これまでがん治療薬に関して、厚生労働省は第2相臨床試験まで済ませただけで輸入製造承認した場合もあった。ところが、この度臨床試験のガイドラインが変わって、第3相試験が義務付けられることになったのである。第3相試験が義務付けられたのは、乳がん・胃がん・大腸がん・非小細胞肺がんの4つだ。
「4つのがんはコモン・ディジーズ(よくある疾患)です。例えばAという新しい薬剤が開発されて胃がんに対して有望であるという場合、従来用いられてきたシスプラチン+5-FUに対してシスプラチン+5-FU+Aという組み合わせで、どちらの腫瘍縮小効果が長続きするか、生存期間がどのくらいあるかという検討が行われるようになっています」
しかし、第3相試験というと通常は数百名のあるいは数千名という患者さんが対象になってくる場合もある。最近では数千名という規模の試験となるとグローバル・トライアル(国際的な臨床試験)が行われる。その中で、世界で同時に始められるような試験では、日本で世界の1~2割といった患者さんが登録されるグローバル・トライアルが進められるようになった。これまでは海外で進められていた治療を日本に導入するというあり方だったわけだが、世界中で同時に開発が進められそれに日本も参加するという時代になってきているのである。
第3相試験は患者さん自らが治療を体験する中で、総合的な治療効果をみる試験でもある。それは症状の緩和効果といったQOL(生活の質)など質的な問題を評価する試験でもあるのだ。
「第1相、第2相の臨床試験では、量
的な問題、薬剤を単一の武器としての性能をだけをみていたのですが、第3相試験では、『患者さんをどれだけ幸福にできるか』といった新しい武器を戦術に組み込んだ場合の総合的力量を評価することになるわけです。第3相臨床試験まで必須ということになると、なおさらたくさんの患者さんの協力を得ないと難しいことになってきます」
有用性を科学的に証明するランダム化比較試験
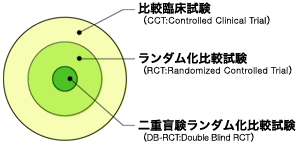
第3相臨床試験ではランダム化比較試験という要素がある。これは今までの標準的に行われてきた治療と、その新しい治療を厳密に比較するために、被験者にくじ引��でどちらかの治療法を割り当てる方法だ。「従来の治療法よりいい可能性がある」といっても、実際に比較してみなければわからないことから、この方法が考え出された。
例えば従来ABという標準治療があって、そこにXという薬が新しく登場したとすると、ABとXを比較するために「AB対X」、あるいは「AB対AB+X」、さらに「AB+ZY対AB+X」というふうに比較試験が行われることがある。試験の方法にはいろいろなパターンがあるが、共通しているのは従来のABに比較してXにそれを超える有用性があるかどうかということである。
[リンパ節拡大郭清]
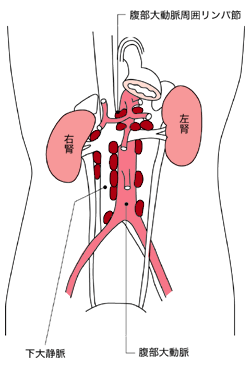
たとえ治療効果が同じだったとしても、XがABより副作用が軽ければ、従来の治療法より有用だということになる。あるいは、副作用が同じ程度出る場合でも、Xが従来のABよりも治療効果が優れているなら、有用性が高いとなるわけだ。
かつて胃がん手術に携わる外科医は、誰もが手術ではリンパ節 をごっそり郭清する拡大手術を常識としていた。そうしたなかで、一部から「リンパ節郭清をしても仕方がない」とか「リンパ節を残しても長生きしている」という声が現れるようになり、そのようなレベルの低いエビデンスが傍証として積み重なってきたのである。
国立がん研究センター中央病院医師の笹子三津留さんは、早期胃がんの 治療において、D2と呼ばれる縮小手術とD4と呼ばれる拡大手術のランダム化比較試験を実施した。その結果、D2とD4では治療成績に差がないことが明らかになったのである。
「こうしてそれまでみんなが拡大手術という間違いを起こしていたことが明らかになりました。それまではまだ期が熟していないためにランダム化比較試験ができなかったわけです。素人が考えるとランダム化比較試験はすごく不合理な気がするかもしれないけれど、きっちり考えるといちばん合理的、倫理的な考え方です」
「クリニカル・イクイポイーズ」で科学的・倫理的に
ランダム化比較試験は新薬の治験だけではなく、それ以外の治療法、例えば[手術]対[抗がん剤+放射線]というふうにまったく違った治療法を比較する場合もある。すなわち、ランダム化比較試験は薬だけではなく、がん治療全体の体系を評価するという意味で行われることがあるのだ。
食道がんの治療を例にとれば、いまや抗がん剤治療と放射線照射を組み合わせた化学放射線治療が標準的になってきた。従来標準的に行われてきた手術単独の治療よりも、化学放射線治療が有用であると考えられるようになった結果である。
もちろん放射線治療が有用なのか、化学放射線治療が有用なのかは、比較しない限りいえないことだった。こうした比較を行う上で重要な要素として、「クリニカル・イクイポイーズ(臨床的同等性)」という考え方が導入されている。
以前は食道がんの治療は、化学放射線治療でも、手術でも結果は同じようなものと考えられていた。食道がん治療の専門家が集まって議論を戦わせても、「手術がいい」「化学放射線治療がいい」と意見が二分してどちらも相譲らないという状態だったのである。
このように、その時点の医学知識ではどちらが優れているかどうか専
門家でもわからない状態をクリニカル・イコイーズという。こうした意見が相半ばする状態に対してはランダム化比較試験で検討して、どちらが有用かを判断するしかない。
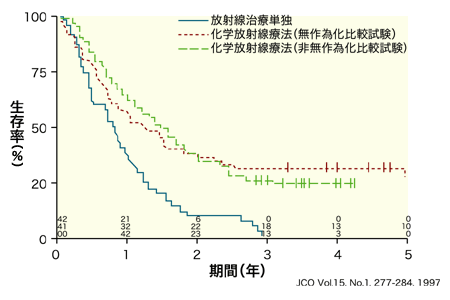
同じカテゴリーの最新記事
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 国立がん研究センター東病院が取得したCAP認定とは? 国際的な臨床試験が日本でもっと行われるために
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性
- 日本初!免疫チェックポイント阻害薬の臓器横断的適応 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)大腸がんにもキイトルーダ承認
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


