安心して臨床試験を受けるための基礎知識 3.抗がん剤の臨床試験は一般薬と違うの?
自分の思いこみや経験を優先して行う治療
クリニカル・イクイポイーズが成り立たない例の1つとして、小細胞肺がんの治療法を挙げることができる。この分野では、「化学放射線治療が有用か手術が有用か」ということになると、99パーセントの専門家は「化学放射線治療が有用」と判断する。そんなところで手術の有用性を検討しようと主張しても、専門家が見て明らかに手術を受ける患者さんに不利になるので、誰も登録しない。すなわちランダム化比較試験が成立しないのである。
もちろん食道がん治療にしても、化学放射線治療が登場した頃は、圧倒的に手術を支持する人が多く、クリニカル・イクイポイーズは成り立っていなかった。
これに対して徐々に化学放射線治療の第2相試験が行われて、データが蓄積された結果、「手術より優れているかもしれない」と考える化学放射線治療支持派が増えてきた。それが手術支持派に匹敵するほどになり、クリニカル・イクイポイーズの状態が成立し、ランダム化比較試験が行われたわけである。
その試験の結果、手術と化学放射線治療で効果はまったく同じであっても、手術より副作用が軽いという意味で化学放射線治療に軍配が上がることになった。
すなわち、一方の治療法が優れていると信じている専門家が多いと、クリニカル・イクイポイーズが成り立たず、ランダム化比較試験をしようということになってもその試験に登録しないことになる。一方、クリニカル・イクイポイーズが成り立っているということは、その結果は「神のみぞ知る」なのだから試験を行うことは倫理的ということになるのだ。
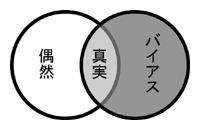
ところが、医療の世界では往々にしてこうしたランダム化比較試験の考え方が無視され、医師が自分の思い込みや限られた経験で治療が行われることがある。例えば研修医の時代に抗がん剤がとても効いたという体験があると、それを根拠に治療に結びつけるというケースが少なくない。このことを「思い出しバイアス(偏り)」という。
第2相試験までに示される化学放射線治療の有用性を示すデータは、化学放射線治療が効きやすい症例ばかり集めて試験をしているというバイアスが生み出したかもしれない。逆に手術の有用性を示すデータも、手術がしやすい症例を選択して手術のほうが成績がいいといっている可能性もある。
これに対して、どの治療法が有用であるかを科学的に推測するための手段はランダム化比較試験しかない。それは最も科学的で倫理的な方法といえるわけだ。第3相試験では、このランダム化比較試験を行うのである。
バイアスと偶然を極限まで排除したダブルブラインド
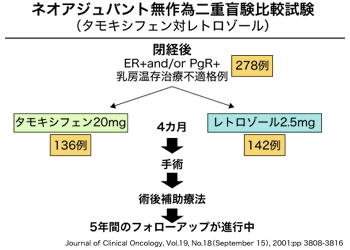
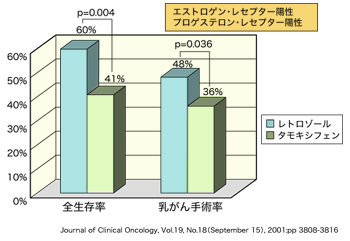
ランダム化比較試験の延長にはダブルブラインド(二重盲検)という試験がある。この試験もくじ引きでAという治療とBという治療が割り当てられて、その成績を比較検討するものだが、患者さん自身も、医師も、データ解析の担当者も、その人がAの治療を受けている群に入っているのか、B群なのかわからないようになっている。
この試験で顕著な副作用が出やすい抗がん剤や手術などを検討することはちょっと難しい。がんの治療薬ではホルモン剤などを検討するために採用されている。
その代表として、乳がんの治療薬であるレトロゾールとタモキシフェンを比較検討した例を挙げることができる。タモキシフェンの錠剤はちょっと大きめで白く、レトロゾールは小ぶりで黄色という姿である。
この比較試験に登録した患者さんたちはすべて白くて大き目の錠剤と黄色で小さ目の錠剤を飲んだ。タモキフェン群に当たった人はタモキシフェンの実薬とレトロゾールの偽薬を飲み、レトロゾール群はレトロゾールの実薬とタモキフェンの偽薬を飲んでいる。これをダブルブラインドでも上位にある「ダブルブラインド・ダブルダミー法」と呼ぶ。こうした方法によって、臨床試験の敵であるバイアスと偶然を科学的に極限まで排除できるわけだ。
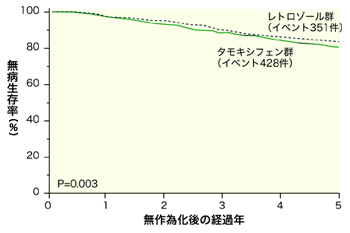
同じカテゴリーの最新記事
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証
- 国立がん研究センター東病院が取得したCAP認定とは? 国際的な臨床試験が日本でもっと行われるために
- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!
- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!
- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!
- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性
- 日本初!免疫チェックポイント阻害薬の臓器横断的適応 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)大腸がんにもキイトルーダ承認
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン


