患者も家族も早期の段階で救急症状に気づくことが大切 大きく遅れている。がんによる急変には、「がん救急医療」を
腫瘍の存在から起こる電解質のバランス異常
がん患者にはだるさ、倦怠感、吐き気、夜間の多尿など不特定の症状が現われることが少なくない。そうした場合には、第2の緊急事態、腫瘍随伴症候群が起こっていることも考えられる。 「もっとも多いのは、体内に生じたがんがさまざまな物質を放出することで生じる体液の電解質の乱れです。なかでも多いのが高カルシウム血症と低ナトリウム血症です。放置すると前者は腎機能障害につながるし、後者は意識障害や昏睡、全身けいれんにつながる危険があります。当然ながら迅速な処置が必要です」(新海さん)
とくに高カルシウム血症は乳がんや肺がんの扁平上皮がんに多く、全がん患者でみても10パーセントという頻度の高さで現われるから要注意だ。では、これらの症状に対してどんな処置が講じられるのか。
高カルシウム血症の場合には、水分摂取を増やしながらカルシトニン、ビスホスホネートなどのカルシウム抑制剤が投与される。この処置による効果は約9割。残る1割の患者は人工透析によるカルシウムの排除が行われる。もっとも多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、乳がんなどでこの症状が起こった場合には、ステロイドホルモンの投与で一時的に症状を改善させることもある。一方、低ナトリウム血症の場合は、逆に水分摂取間制限とナトリウムの補給が行われ、この処置で一部の重篤なケースを除きほとんどの患者で症状が解消されるという。
第3の治療の副作用として緊急事態が生じるケースは、抗がん剤が原因となっている場合が大半を占めている。なかでも多いのが、血液がんの初回の治療で生じる腫瘍崩壊症候群と呼ばれる症状だ。
「大量に投与した抗がん剤の影響で、がん細胞が一気に崩壊し、尿酸などの内容物が血中に放出されて、高カルシウム血症をはじめとするさまざまな異常が起こります。この場合には一旦治療を休み、そのうえで、薬物投与によって尿酸を抑える処置がとられます」(新海さん)
同じように抗がん剤の副作用として多発しているのが、骨髄がダメージを受けることによる白血球の減少だ。専門的には発熱性好中球減少と呼ばれる症状である。この場合の処置は白血球減少の程度によって異なる。
「血液1ミリリットル中の白血球が500個未満のもっとも危険な状態(グレード4)では、感染症予防のための抗生物質とともに白血球増殖因子のG-CSFを投与します。その前段階のグレード3では抗生物質を投与した上で、安静を保って体力の回復を待つ処置が基本になります」と、新海さんは語る。
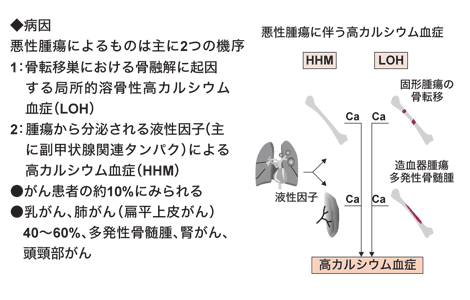
「おかしいな」と感じたら、初期症状として注意する
さらにもう1つ最近になって問題になりつつある事象に腸に穴が開く腸管穿孔がある。がんが進行した場合にも同じ症状が見られることがあり、最近では大腸がんの治療薬として脚光を浴びているアバスチン(一般名ベバシズマブ)の副作用としても問題視されている。この場合はどんな処置が講じられるのか。
「腸の内容物がお腹の中に放出されるときわめて危険な状態となり、さまざまな感染症が発生し、生命の危険にもつながります。その場合には、緊急手術に踏み切ります」(新海さん) このようにがんという病気にも、緊急処置が必要になる局面は決して少なくない。症状が重篤で治療が後手に回った場合には生命の危険も生じるし、また一命をとりとめても、後遺症やQОL(生活の質)の低下が生じることもある。
そうした事態を回避するために新海さんは、「初期症状のチェックの徹底」を提言する。
「だるさ、倦怠感、腹痛、下血など他の病気でも起こりがちな症状が、実は緊急事態の訪れを示唆していることが少なくありません。緊急を要する症状でも、それが初期の場合であれば、がん救急医療もスムーズに機能します。そのためにがん治療を手がけている医師は、患者さんとのコミュニケーションをよくするとともに、そうした症状に疑問を持つ、想像力を巡らす必要があるでしょう」
がんと同じように、がんに付随して起こる危険を回避するためにも、症状の早期発見と早期治療が切り札になるわけだ。
チームで対応するがん救急医療

がん救急医療に力を入れる四国がんセンター
さて、ここまで見てきたようにがんという病気にも救急医療が不可欠である。では、実際にそれはどう機能しているのだろうか。新海さんによると、がん治療の先進国、米国ではMDアンダーソン、メモリアル・スローン・ケタリング病院という2つのがん専門病院でがん救急専門医が常勤しているほか、全米25施設のがんセンターでも、周辺の大学病院との提携による、がん救急医療が実施できる体制が整えられているという。しかし、日本の場合はまったく状況は異なっている。
「日本の場合は同じ病院内でのチーム医療が基本です。たとえば私が所属している四国がんセンターでは、患者さんが脊髄に圧迫を受けている場合には、主治医であるがん専門医が実際の治療を担当することになる整形外科医や画像診断医とチームを組んで対応にあたるわけです」
もっとも現実には、こうしたチーム医療がうまく機能しているケースはそう多くはない。たとえば、がん救急医療がスムーズに機能するためには、何より主治医の緊急事態を察知する問題意識が不可欠の条件だが、その点でも今ひとつ、課題を残している。しかし希望がないわけではない。
「現在、日本では緊急時の対応も含めて、がん治療に特化したがん認定医が年間で3000人誕生しています。この認定医が3万人に達する頃には、かなり状況も変わっているのではないでしょうか」(新海さん)
さらには、在宅医療でも大規模ながん拠点病院とかかりつけの病院、さらに訪問看護ステーションとの連携が進みつつある。新海さんはこのことも、在宅で治療を続ける患者の緊急時への対応に大きなプラスになる可能性があるという。
もっともこうした救急医療の中心にいるのが他ならぬ患者自身であることも間違いない。思わぬ危機を回避するために、家族や患者自身も自らの状況変化をチェックする姿勢を身につけたい。
(構成/常蔭純一)


