肝転移への有効性は否定された。が、その技術レベルに問題との指摘も 血管内治療の現在―偽らざるその効果と限界
大腸がんの肝転移への肝動注の根拠は?
エビデンス・ベースド・メディスン(EBM=科学的根拠に基づく医療)が提唱されて久しいが、驚くべきことに血管内治療のエビデンスを明らかにした無作為化比較試験はこれまでほとんど行われていない。いわば、「有効ではないか」という医師の個人的経験や感触に基づいて行っているのが実情だが、そうした中で唯一、大腸がんの肝転移に対する肝動注については臨床試験が行われている。
大腸がんの肝転移は手術による切除が第1選択の治療法だ。手術で転移巣をすべて切除できれば、30~40パーセントの患者ががんが縮小するばかりか、治癒までするからだ。手術で切除できない場合、静脈から抗がん剤を投与する全身化学療法が次善の治療法となるが、転移巣の縮小効果や消失効果をより高めるために肝動注が行われることも少なくない。
大腸がんの肝転移に対する肝動注のエビデンスをさぐる無作為化比較試験は、海外において1980年代後半からいくつも行われており、その中で信頼性の高い無作為化比較試験は10本だ。いずれも肝臓以外への転移が認められず、手術で切除できない肝転移の患者が対象で、全身化学療法を受けるグループと、肝動注を受けるグループに患者さんを無作為に振り分け、その治療成績を比較したものである。
肝動注の有効性は否定された
「その結果はみな共通していました。すなわち、肝動注は全身化学療法よりもがんの縮小効果が高いこと。しかし、生存期間を比べると、肝動注と全身化学療法の間に有意差はなかったということです。従って、わざわざ肝動脈にカテーテルを挿入するなどの手間暇やリスクをかけてまで肝動注を行う必然性は認められなかったのです」(荒井さん)
この結果、国際的には、以上の無作為化比較試験の結果により、生存期間の延長が認められない肝動注は有効でないと判断された。

外来での化学療法の様子。
血管内治療と比較検討したデータはまだない
「肝動注は生存期間の延長に寄与しないばかりか、無駄な費用がかかる危険な治療法だ」 と言いきった論文もある。
エビデンスのレベルはレベル1~5までの5段階に分けられるが、無作為化比較試験によ��て立証された事実はもっとも信頼性の高いレベル1のエビデンスである。
「大腸がんの肝転移に対する肝動注は、レベル1のエビデンスによってその有効性が否定されたのです。加えて、肝動注は胃などの他臓器に、高濃度の抗がん剤が誤って流れるなどの副作用を伴ったりすることもあります。医療ではより安全で確実な治療法から試みるのが原則ですから、肝動注よりも全身化学療法を優先させるというのがエビデンス・ベースド・メディスンに適っており、これはワールド・コンセンサスといえるのです」(岩瀬さん)
飛躍的に向上している化学療法の効果
アメリカではこうしたエビデンスに基づき、肝動注はほとんど行われていない。ヨーロッパでは多少行われている程度で、肝動注が普及している日本は世界的に突出していると見られなくもない。まして大腸がんの肝転移に対する肝動注だけでなく、乳がんや胃がんなど他のがんの肝転移はもとより、肺や骨、骨盤、腹腔内への転移巣や、腎がんやメラノーマなどの原発がんまで、さまざまながん病巣に血管内治療と称して動脈塞栓療法や動注化学療法が広く行われているのは、日本だけなのである。
「しかも大腸がんの肝転移に対する肝動注以外、他の血管内治療はまったくエビデンスがありません。そうであるならば、きちんとエビデンスを出すために臨床試験として血管内治療を行うべきだと思いますが、現在、血管内治療を積極的に行っている一部の医師にそうした姿勢が見られないのは厳しく批判されてしかるべきだと思います」(岩瀬さん)
もっとも、血管内治療専門の医師がすべてそうではないことは断っておかなくてはいけないだろう。少ないかもしれないが、臨床試験の必要性を認識し取り組んでいる医師もいる。たとえば日本のJCOG(Japan Clinical Oncology Group)というグループでは、大腸がん肝転移に対する動注化学療法の臨床試験が進行しているのだ。
現在、新規抗がん剤や分子標的治療薬などの登場によって、全身化学療法の奏効率や延命効果などが著しく向上しつつある。もちろんがんの種類によっても異なるが、乳がんの場合、全身化学療法でも60~70パーセントの患者に奏効する。大腸がんもカンプト(一般名イリノテカン)やエルプラット(一般名オキサリプラチン)等の新薬の登場によって奏効率の向上がはかられている。
「全身化学療法によって肝転移や肺転移、骨転移などが縮小し、症状の改善や生存期間の延長をはかることが可能となってきています。少なくとも、血管内治療を考える前に、まず全身化学療法等の標準治療をきちんと行う可能性がないかを見定めることが重要だと思います」(荒井さん)
なによりも血管内治療は有効性が科学的に立証されていない治療法である。つまり、効くのか効かないのかまだ不明だし、副作用や障害もさまざまで、それらに対する対処の方法も明らかにされていない実験的治療法であることを把握しておかねばならないだろう。
血管内治療による症状改善、QOLの向上
一方、確かに血管内治療が全身化学療法より生存期間の延長をはかれることは科学的に立証されていないが、優れた腫瘍の縮小効果があり、それによる症状の改善やQOLの向上、生存期間の延長が得られることもある。全身化学療法で治療していたにもかかわらず、肝臓と胸骨への転移によって激しい痛みを招き、肝不全に陥るのも時間の問題といわれた乳がん患者が、血管内治療で肝転移巣を大きく縮小させ、1年以上経っても元気に過ごしている症例なども報告されている。
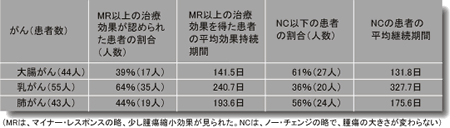
「もちろん、血管内治療を受けにくる患者さんに、まず全身化学療法等の標準治療を受けるよう勧めるのは当然です。標準治療が残されていると思われる患者さんには、大阪府立成人病センターや大阪市民病院などでそれを受けることをお勧めしています。しかし、標準治療の尽きた患者さんには、血管内治療が有効と判断した場合、積極的にそれを行っているのです」と血管内治療の専門クリニックであるゲートタワーIGTクリニック(大阪)院長の堀信一さんは語る。
腫瘍の縮小効果が高い血管内治療は、腫瘍の縮小によってなんらかの治療効果が得られる場合、優れた有効性を発揮する。先の肝転移から肝不全に陥る寸前まで進行した乳がんもそうだが、肺転移巣や骨転移巣の急速な増大によって呼吸困難や激しい痛みを招いた場合なども、血管内治療によって呼吸苦や痛みが和らいだり消失したりすることも報告されている。あるいは、心臓から血管が押し出されるときの圧力によって増強される骨転移の拍動性の痛みなどは、腫瘍血管を詰めることで速やかに解消すると同時に、転移巣の縮小や消失もはかられる。
「血管内治療を誹謗中傷する医師は、その優れた治療効果を知らないだけなのです。標準治療が尽きたらもう治療方法はないと告げ、がん患者さんを見捨ててしまう医師が少なくありません」と豪語する血管内治療の専門医もいる。
技術レベルが上がれば延命効果も
実は、血管内治療は腫瘍の縮小効果やQOLの向上だけでなく、延命効果もあるのではないかと考えている専門医も少なくない。というのは、血管内治療は、カテーテルを腫瘍栄養血管まで確実に到達させる技術など、専門医個々の技量に負うところが大きく、それによって治療成績もかなり変わってくるからだ。先述した大腸がんの肝転移に対する肝動注の有効性を調べた海外の無作為化比較試験は、いずれも開腹して肝動脈へカテーテルを挿入しているのだが、世界でもっとも技術的レベルが高いといわれる日本の血管内治療と比べると、そのレベルは確かに低いと言わざるを得ない。たとえば、2003年の「ランセット」という医学専門誌に発表されたイギリスの無作為化比較試験では、肝動注に振り分けられた患者の37パーセントが開腹手術による容態の悪化やカテーテルの挿入の失敗等で肝動注を実施できなかったという。日本ではあまりないことだ。
さらに、肝動注が開始された患者のうち当初の計画通り2週間ごとに6回の治療を繰り返せた患者は20数パーセントで、平均2回しか実施されていない。無作為化比較試験の内容をさらにもう1歩踏みこんで調べてみると、肝動注の技術面に大きな問題があることが浮かび上がってくる。
これでは肝動注と全身化学療法を比較して、生存期間に有意差がないとして出した結果はおかしいのではないか、という疑問も出てくる。加えて、実際の治療現場で腫瘍の縮小からめざましい効果が得られるという自信が重なり、きちんとした血管内治療を行えば、生存期間も延びるだろうという信念を持つ専門医は、日本のみならず欧米も含め少なくない。
いずれにせよ、血管内治療は、歴史が長く、普及しているとはいえ、その有効性についてはまだ科学的に立証されていないことは事実だ。
従って、血管内治療を受ける際には、これが実験的治療であることを念頭に置いて、まず患者さんが受けようとする治療法がきちんとした標準治療にのっとっているのか、他に標準治療がないのか、それらを主治医にきちんと相談したり、セカンドオピニオンで確認したりすることが大切だといえよう。
そしてまだ標準治療を受けていないのなら、まずはそちらを優先し、標準治療で効果がなくなった段階で、血管内治療を受けるかどうかの検討に入っても遅くはないだろう。血管内治療の専門医には、自分のがんにそれが有効と考えられる根拠や、副作用や障害の程度と対策などについて、事前にきちんと説明を受けておくべきこともまた重要である。


