高齢者でも可能になったミニ移植の成功のカギは?
リスクが高い感染症
基本的には、前処置としてフルダラとアルケランという抗がん剤を使い、臍帯血移植を行って、GVHD(移植片対宿主病)予防のために免疫を抑える薬を使う。鬼塚さんによると「再発を防ぐために、ミニ移植の前処置としては最強の抗がん剤を使っている」そうだ。
これで、ほぼ若い人と同じ治療成績をあげている。再発率も非常に少ないという。これまで60歳以上で骨髄移植を受けた骨髄異形成症候群の患者さんは19例。最高齢は71歳。うち死亡した患者さんは5名のみという。
原因は、GVHDが2例、再発が1例、感染症が2例。GVHDは、生着した幹細胞が白血球など免疫細胞を産生し、宿主である患者の体を攻撃する現象。その力でがん細胞も叩くが、健康な細胞まで攻撃する。これが、移植のやっかいなところだ。
2例は感染症が原因で死亡しているが「移植で1番リスクになるのは感染症です。感染の予防と管理が非常に重要なので、感染のリスクが高い人は今は対象になりません」と鬼塚さん。感染症によるリスクは、かなり事前に把握できるそうだ。今はそれだけ移植のリスクを低下させることが、可能になっているのである。
移植成功の鍵は周囲のサポート
しかし、鬼塚さんによると移植の適応になるかどうかは、高齢者の場合医学的な問題ばかりではないという。
「医学的には高齢者でも移植をすることは可能になってきました。しかし、むしろ重要なのは周囲にサポートしてくれる人がいるかどうかなのです」
移植の場合、移植がすめば終わりではない。感染症やGVHDなど、いかに早く見つけて対処するか、その後の管理が非常に重要になる。
「合併症が起きたときにサポートしてくれる人がいるか、すぐに病院に来てくださいと言ったときに、寝たままでもいいから病院につれてきてくれる人がいるかどうか。それが、結果を左右する」のだという。
移植後半年ぐらいは、週に1~2回は病院に通うことになる。遠くて通いきれないからと、近くの病院でみてもらっていた人がいたが、この人はいよいよ状態が悪くなって東海大学に来たときにはもう手遅れの状態だったという。移植を熟知していないと、管理は難しいのだ。また、肺炎を発症したのに家族に遠慮して我慢し、亡くなった女性もいる。GVHDが原因だった。
回復に半年から1���
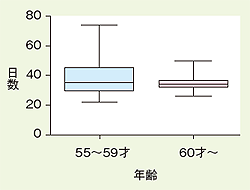
さらに、高齢者の場合は体力の回復にかなり時間がかかることも覚悟しなくてはならない。鬼塚さんによると元の体力に戻るには半年から1年はかかるという。若い人と同じように2~3カ月で職場復帰できると思っていて、それができずにうつ状態になった患者さんもいるそうだ。
「ミニ移植には死ぬほどの副作用はないのですが、問題は体力の低下。ものの味はわからなくなるし、食が細いのに食べられなくなって体力が低下、その結果感染を起こすという悪循環に陥りやすいのです」と語る。
入院が長くなるほど足腰が弱る。若い人はハイリスクでも可能性が高ければ骨髄移植を行うので100日も200日も入院することもある。しかし、幸い今は抗生物質や抗ウイルス剤が良くなったので軽症であれば外来でも感染症のコントロールができ、60歳以上の高齢者の場合入院期間は移植前2週間と移植後5週間程度だそうだ(図5)。
移植後の1年間をしっかり乗り越えることができれば、ゴルフや海外旅行、登山を楽しんでいる人もいる。老後をエンジョイすることができるのである。ただし、それには厳しい条件がある。
「骨髄移植がどんな治療法か、なかなか事前に理解することは難しいかもしれません。でも、1番大事なのは移植後のケア。半年は頻回に通えて周囲に食事から通院、日常生活までしっかりサポートしてくれる人がいることが、移植の条件です」と鬼塚さん。
これからの高齢者医療がどうあるべきなのか、どんな人を対象に行うべきなのか、医療技術が発達した今、新たな問題も浮上しているのである。


