下肢のリンパ浮腫を防げ!リンパ管温存するリンパ節切除術
拡大鏡で局所解剖を確認しリンパ節のみを切除

こうして2007年ごろから北さんたちは、リンパ管を温存する新しいリンパ節郭清法を開始した。
リンパ管は、脂肪組織にくるまれるようにして血管の周囲を走っている。どこにリンパ節があり、どうリンパ管が走っているかは、膜にくるまれていて特に肉眼(裸眼)では表面からはわからない。そこで、従来は血管を包む血管鞘や脂肪組織・毛細血管などと一緒にリンパ管やリンパ節を”リンパ節”としてまとめてとっていたのである。
「私たちも、リンパ節転移が疑われる場合には、従来の方法でリンパ節郭清を行いますが、郭清したあとは血管だけツルツルに露出した状態になってしまう」のだそうだ。
これに対して、北さんが行うリンパ管温存法では、手術用ルーペで拡大しながらリンパ節だけを摘出していく。リンパ管などをくるんでいる膜を少しずつ電気メスで開き、脂肪組織を分け入ってリンパ管の流れを追う。そこで、1つひとつリンパ節を見つけて切除していくわけだ。リンパ節を摘出すれば当然それにつながるリンパ管は切断されてしまうが、リンパ管は1本道ではなく網の目状になってバイパスを形成しているので、これらを温存すれば全体としてのリンパの流れはかなり温存できるという。
「最初は、高周波メスや超音波メスなど器具も大きく性能もあまり良くなかったのですが、今は改良が進み、細かい手術がずっとやりやすくなりました」と北さんは語る。
新しい術式で減少したリンパ浮腫
しかし、問題は安全性だ。
北さんは「切除する範囲が少なければ、副作用が少なくなるのは当たり前なのです。結局はそれが安全かどうかが、1番大事なところです」と語る。
そこで、リンパ節だけを郭清する群と、従来からのリンパ節郭清群とで比較検討を行った(リンパ節だけを郭清する群では、拡大鏡〔ルーペ〕のみでリンパ節を探す方法と、乳がんのセンチネルリンパ節生検でも使われるリンパ節を染めるためのICG〔インドシアニングリーン〕という色素を���った検査を併用してリンパ節をみつける方法とに分けて比較)。
検討したのは、リンパ節の取り残しがないか。リンパ管を残すことによって診断精度が低下しないか、再発につながらないか、という点だ。
「リンパ節生検はマイナスだったから、抗がん剤治療をしなかったが、万が一残したリンパ管にがん細胞が残っていて、そのために再発したということがあってはなりませんから」と北さんは言う。
| 浮腫の程度 | 従来法 | リンパ管温存法 | |||
| 拡大鏡 | ICG-PDE併用 | 合計 | |||
| 兆候なし | 50+*1 (75.8%) | 40+*1 (90.9%) | 14 (93.3%) | 54 (91.5%) | |
| 臥床で消失 | 6+*1 (9.1%) | 16 (24.2%) | 4 (9.1%) | 1 (6.7%) | 5 (8.5%) |
| 臥床で消失せず | 9+*4 (13.6%) | 0 | 0 | 0 | |
| 皮膚病変を伴う | 1+*1 (1.5%) | 0 | 0 | 0 | |
| Kruskal- Wallis体験 | コントロール | p=0.0292 | p=0.115 | p=0.0233 | |
しかし、結果は表のとおり。2007年から2009年までの間に、ルーペやICGを使ってリンパ管を温存した子宮がんや卵巣がんの患者さん65人と、同じ時期に従来のリンパ節郭清を行った患者さんで比較。その結果、摘出されたリンパ節の数は、骨盤内ではほぼ同じ、傍大動脈リンパ節ではむしろリンパ管温存群のほうが多いぐらいだった。
再発に関しては、「2009年の段階では、リンパ節転移陰性で術後治療をしなかった人は24人いたのですが、再発をした人は1人もいませんでした。ただ、これは平均観察期間が408日なので、さらに観察を続ける必要があると思っています」と北さん。
その一方、リンパ浮腫の発症率は、従来法が24.2%だったのに対し、温存法8.5%と3 分の1に減少していた。
つまり、リンパ節の取り残しや再発のリスクを高めることなく、下肢のリンパ浮腫の発生を3分の1に減少させるというのが、この時点での結果だったのである。
技術の習得に3年
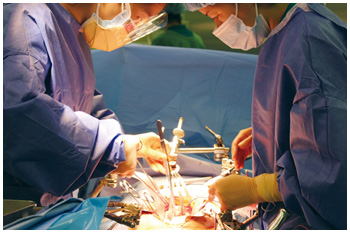
このデータでは、ルーペだけを使ってリンパ管を温存してもICGを併用してリンパ管を造影しても、治療成績に差はないことも明らかになったため、現在北さんはルーペだけを使って リンパ管温存術を行っている。
「まだ、以後のデータはまとめていないのですが、この方法で郭清をして中等度以上の浮腫が起きた人はいません。再発に関しては5年以上経過をみて比較しないといけませんが、私自身はとくに再発しやすいとも、合併症が起きやすいとも感じていません」というのが、北さんの印象だ。
技術的な難しさはどうなのだろうか。「ルーペをかけて手術する産婦人科医も少ないし、当科の若い医師もこのリンパ節郭清の習得には苦労しているようです。リンパの流れを見つけて、その流れにそって膜を切り開いていって一通りリンパ節を探せるようになるまでに3年ぐらいかかりますね。でも、最近は神経温存術などでも細かい局所解剖の重要性が認識されていますし、このような手術ができる若手の婦人科医師の育成に努めています」と北さん。
下肢のリンパ浮腫は、外見だけではなく靴がはけない、歩くのがつらいなど日常生活にさまざまな障害をもたらす。リンパ管温存術のデータをまとめて、その普及につとめるのが今後の課題だそうだ。


