厚い縦割りの壁を乗り越え、九州から意識変革の風 がんのチーム医療を未来へ託す
患者が望む医療者とのコミュニケーションとは
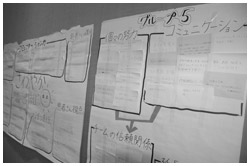
次のセッションは、相手の立場で話を聴く「コミュニケーションスキルトレーニング」だ。
「日頃から人の話を聴く姿勢を心がけ、さらに自分に余裕がないと人の話も聴けない」(九州がんセンター臨床心理士、白石恵子さん)とウォーミングアップから始まって、3人1組でお互いの話を聴きあい、ロールプレイ(役割演技)も体験。
セッション最後に九州がんセンターサイコオンコロジー科の大島彰さんが、がん患者と医師のコミュニケーションの最新事情を報告。
「人生の見通しが根底から悪く変わる経験をするがん患者とのいいコミュニケーションは、積極的にとろうとしてもむずかしいが、心がける医療者は少数です」(大島さん)
医療者とのコミュニケーションが悪いと、患者の精神的苦痛が増え、だんだん医療者に情報開示しなくなる。医療者も患者に信頼してもらえないとバーンアウト(燃えつき症候群)をおこしやすくなる。それでも「がん患者が望むコミュニケーション」は、まだ、その模索が始まったばかりだ。
2007年の国立がん研究センター東病院における患者調査では、医療者が作ってきたガイドラインと一部異なる結果が集まった。
たとえば、がんの告知には看護師が同席することが多いが、「他の医療従事者を同席させるのを望む」患者は2割に満たない。多くのガイドラインで望ましいとされる「悪い情報は段階的に伝える」ことを望むのは3割だけ。一方「余命を伝える」は、患者半数は望むが、3割は望まない。余命宣告の意向は、病状進行でも変わってくる。
がん患者の意向にそったコミュニケーションの実際をまとめた「実践に学ぶ悪い知らせの伝え方:疾患別シェアSHARE(*)」が、2009年10月に作られたところだ。
*SHARE=Supportive environment How to deliver the bad news Additional information Reassurance and Emotional support。悪い知らせを伝えられる際のわが国のがん患者の意向の構成要素をその頭文字で示したのがSHARE。がん医療において、悪い知らせを伝える際の効果的なコミュニケーションを実践するた���の態度や行動を示している
「患者の事情」を最優先に考える

2日目午前の授業は、EBM(科学的根拠に基づく治療)の基本を学ぶ「治療方針構築」。
(1)患者の問題を考える、(2)問題についての情報を集める、(3)批判的に吟味する、(4)患者に当てはめる、というEBMの4つの思考ステップは「毎日の生活でも行っている」と九州大学女性医療人きらめきプロジェクトの徳永えり子さん。
恋愛トラブルの例題をこの4ステップで考えた後、学生は、「45歳で初期の乳がん(腫瘍径1センチの浸潤性乳管がん、リンパ節への転移なし)が見つかった人への治療方針」を、ガイドラインを見ながら立てた。「患者と主治医は乳房温存を望むが、家族は再発を恐れて全摘を希望」という設定だ。
結果は、学生の全グループが「乳房温存法と術後放射線療法」を選択。しかし、質疑応答では、「放射線療法はいくらなのか」「患者が混乱しない再発率数値の伝え方は」「温存法の乳房はどの程度完全なのか、イメージと違うとデメリットにならないか」という具体的な質問が、次々出された。
温存法の乳房を患者がどう思うかは、会場にいたあけぼの福岡の深野さんが答えた。
「自分のときには全摘しか選べなかったので、乳房温存が最初の選択になった現在がうらやましい。術後の乳房も温存法の登場初期に比べ、現在はきれいです」(深野さん)
ただし温存法でも命の選択をするつらさは変わらないと深野さんは言う。温存法の選択後、最終の病理組織検査結果を待ちながら、パニックになる人もいる。だが術後は温存法を受けた人が「私は軽症」と服薬や定期検査を軽視する傾向もあるとのことだった。
立場の違う複数の眼がチーム医療の基本

あるグループのセミナー全体の感想だ。
「少人数で話し合うことで、受身の学校の授業と違い、意見を言うことでも学べた。患者さんは、それまでの人生や性格など、全体で考える必要があり、いろんな視点が必要になる。チーム医療はそのためにも必要だと思った。患者さんとのコミュニケーションはむずかしいのひとこと。言語でのコミュニケーションは10パーセント以下、言葉の前の沈黙が有効かもしれないなど、初めて聞くことが多かった。でも、どの職種でも専門性を高めて協力していけば、いい医療ができると希望を持つことができた」
望ましくない現実を知った者には責任がある

未来を託された医療従事者をめざす学生たち
プロジェクト発起人の大野さんに、なぜ学生向けセミナーを企画したかを聞いた。
「自分がチーム医療に取り組むなかで、組織の壁を越えるのは、社会人になってからではむずかしいと感じたからです。自分の周り、自分の科は、時間をかければいい方向に変えられる。でも他の科、病院全体はなかなか変えられない。これは、他の病院の仲間も同じことを言います」(大野さん)
「チーム医療」は、病院評価機能の項目になっているので、名目上はほとんどの病院ができることになっている。しかし現実は、行っている病院のほうが少ないのだ。
「現実の壁を乗り越えるのは若者です。学生に、チーム医療は『患者に必要なのだ』と伝えたい。将来、仲間を作って、周りから変えてもらいたいのです。毎年50人ずつ、10年で500人を世に出せば、10年後の医療は変わる。10年単位の夢です」(大野さん)
活動の動機には、乳がん患者の「ピンクリボン運動」への共感もあるという。
「ピンクリボン運動は、検診受診率が低いのを知った人たちが、高めるためにしているでしょう。僕も、チーム医療がほとんど行われないのを知った。知ってしまったら、行動に移さないといけない」(大野さん)
10年の夢を抱いた医師が、患者の活動にも刺激を受け、周囲の医療者や患者も巻きこんで、一緒に学生を育てていく。この事実1つをとっても、日本の医療は確かに変わりつつあるなと感じる。


