外科技術伝承の場の喪失は、医療界の財産の喪失を意味する
若手医師に強烈なインパクト与える
かつて国立がんセンターのレジデントとして、森谷さんの直腸がんの手術を何度か見学した現静岡県立がんセンター大腸外科部長の絹笠祐介さんは、ある雑誌のインタビューで当時のことを次のように振り返っている。
「森谷先生の手術は本当に強烈で、明らかに先生だから治った直腸がんと実感できる手術がいくつもありました」
その手術のインパクトは絹笠さんの医師としての進路をも変えた。本来、絹笠さんはダイナミックな肝臓外科か日本が世界トップレベルにある胃がんの専門医になることを夢見ていたのだが、森谷さんの手術に魅了されてしまった。
「森谷先生は危ないところを正確に逃げる。血も流さずにメスを入れる剥離ラインには絶対的な裏付けがあるはず」と絹笠さんは憑かれたように思案した。そして「安全に手術するには、膜と膜の間で手術すること」という答えに行き当たった。
そのことを検証するために一度臨床を離れ、解剖に明け暮れた。血管や神経の位置を確認しつつ、骨盤内の組織の切片を作っては顕微鏡で覗くという日々を続け、確信を得たのちに臨床に戻った。戻った先は大腸外科だ。今では直腸がん手術の名手としてその名を全国に轟かせている。
その記事のコピーを森谷さんに渡すと、さっと目を通し、一瞬だけ嬉しそうに笑った。だがすぐに冗談だが本気だがわからない話の転換の仕方で、「今、日本の医療界はとんでもない財産を失っている。こういうリスキーな手術を引き受ける外科医が極端に少なくなっている」と嘆いた。
雪崩打ってなびきがちな日本の医療人
聞くと上部下部の消化器外科を問わず、多くの診療科で外科の良き伝統が途切れようとしているのだという。
引き合いに出したのが腹腔鏡下手術の隆盛だ。近年、器具の改良や技術の進歩により、結腸はいうまでもなく直腸領域の手術においても導入する施設が増えている。技術的にはD3郭清も可能になりつつある。だが再発頻度などのデータもなく、適応も吟味されているとは言えず、コンセンサスが得られた手術とは言い難い。
「頭ごなしに否定しているわけじゃありません。もとより手術の侵襲が軽減することには大賛成で、腹腔鏡の長所もわかっているつもりです。でも右も左も雪崩打つようになびいていくのが情けない」
最たる例として挙げたのが某医大。そのホームページの消化管外科のスタッフ紹介欄には教授を筆頭に全員が内視鏡もしくは腹腔鏡の専門医として紹介されている。開腹手術の意義を理解している外科医は1人もいないのだ。
「内視鏡や腹腔鏡下手術で大腸がん手術の全部を施行できるわけではありません。それを主体にするにせよ、まず開腹による結腸切除術に習熟してからのことです」と苦言を呈する。
腹腔鏡下手術から開腹手術にチェンジしなければならない事態のことを森谷さんは言っているのかと���ったが、そうではない。開腹手術では執刀医と助手との間に一種の師弟関係が成立して、手術を通じて技術を伝承するチャンスが際限なくある。
しかし腹腔鏡下手術では助手の役割は格段に少なく、技術伝承の機会は多くない。このような場の喪失を森谷さんは「医療界の財産の喪失」と危惧しているのである。
低侵襲という合言葉を掲げ、腹腔鏡を使いさえすればすべてが低侵襲手術になるかのように報じるマスメディアも無責任だとなじる。腹腔鏡下手術による死亡事故が起こってもそれを改める気配はない。耳が痛いところだ。
医師も医療経済の問題に関心を
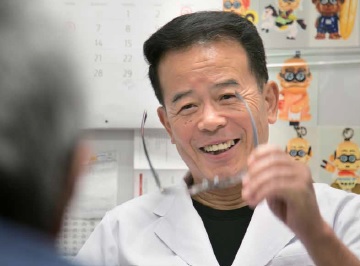
森谷さんの舌鋒は内部にも向かう。エビデンス(科学的根拠)の名のもとに外国の治療成績を分別なく受け入れてしまう医療界。下部直腸がんにおいても、欧米の直腸間膜内の全リンパ節郭清(TME:total mesorectal excision)の考え方が導入されて15年ほど経つが、ほぼ国内を席巻しつつある。学会の演題でこの名を冠するテーマは目白押しだ。
最近、補助療法として施行数を増やしている化学放射線療法についても、放射線の晩期障害の検証が十分でない、と森谷さんは心配する。
再発予防目的の治療としては、元来日本には転移の可能性のあるリンパ節をまとめて切除する側方郭清という手技があり、局所再発率はTMEと比べて劣らないとされている。だが科学的な証明が十分になされているとは言えない。もったいない話だ。
ではそれらを改善する処方箋はあるのか。とくに外科の失地挽回は気になるところだ。それに対し、森谷さんは「医療費の配分の見直し」を挙げた。例えば結腸がんの術後化学療法。手術費の何倍もの薬代がかかる例が多い。
「そのほとんどを外国のファーマ(製薬会社)が持っていっている。それを見逃してきた私たち医師の責任もある。これからはそういう医療経済の問題などについても、医師はマクロ的な観点から関心を持ち、積極的に発言をしていかなければなりません」と森谷さんは締めくくった。


