他科とスクラムを組み、最良の治療を届けるための努力を惜しまない
英国で臨床腫瘍学を体系づけて学ぶ
そんな緩和ケア志向の希望を満たすには、当時、放射線治療科に入るのが一番近道だったため、すぐに放射線科の門を叩いた。
当時の慶應義塾大学病院の放射線科は、日本の乳がん治療が乳房温存へ大きく舵を切るきっかけの1つを作ったことで有名な近藤誠医師がいた。
乳房温存の重要さを盛んに説き、院内で外科と患者を取り合って、物議を醸すことになる直前の頃だった。
「後に、近藤先生が本に書いているような一連の出来事は当時全く知りませんでした。でも、まさに時期的には、ちょうどその直前の頃、私は放射線科にいました。1年ほどの短い期間でしたが、近藤先生からは少なからぬ影響を受けました。このとき、後の上司である土器屋(卓志)先生とも出会っており、この2人は放射線治療におけるメンター(師匠)と言えます」
その後、萬さんは、放射線科医として様々な患者さんと出会い治療にあたるうちに、放射線治療をさらに深く、そして幅広く勉強しようと考えた。
そして、1999年から1年余り、英国マンチェスターへ留学した。そこで放射線治療のオーソドックスな部分から、小線源療法も含めた臨床腫瘍学を体系づけて学んだ。英国は、ホスピス発祥の地でもあった。
「英国では、放射線科医が臨床腫瘍医と呼ばれ、その地位を確立していました。日本ではがんは手術後も外科医が最期まで診ているのに対して、英国では放射線科医が化学療法や緩和医療も含め、がん治療全体を指揮しながら総合的に診療する存在でした」
萬さんは、留学以前より、英国のようなスタンスで放射線科医として診療にあたることを理想と考えていた。留学を通じて、さらにその思いを強くし、東京医療センターへ戻った。
黎明期の小線源療法治療に携わる
診療を再開した2001年頃、同センターでは、泌尿器科の斉藤史郎医師と放射線科の上司である土器屋卓志医師が中心となって前立腺がんに対する小線源療法を模索している時期であり、その後、2003年に治療が開始されたときから、萬さんが治療を指揮している。
その後、同センターの小線源療法は目覚しい躍進を遂げる。
国内の臨床試験をリードするのはもちろん、現在では、高リスク群の局所進行前立腺がんに対する治療についても全国一の症例を実施し、10年以上蓄積されたデータによる生存率においても好成績をあげている。
現在では、前立腺がんだけで、年間200例以上の小線源療法を実施し、同治療の日本における総本山的な病院となっている。
「治療が増えた分、以前のように患者さんとじっくり話す時間が減ってしまったことは、淋しい気がします。しかし〝切らない治療〟である放射線治療により、少しでも多くの患者さんに寄り添えるのであれば、こんなにうれしいことはありません」
放射線科の持つ緩和ケア的要素を理解してもらいたい
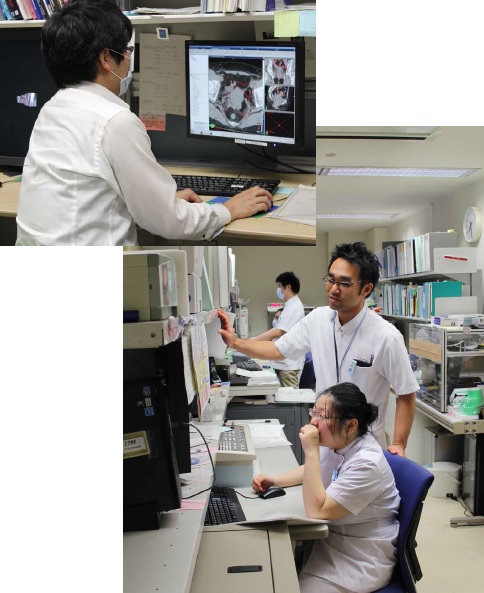
現在、放射線科の年間新患数は約700例。多いがん種は、前立腺がんが約250例、乳がんが約180例、肺がんが約100例、頭頸部がんが80例を数える。
その他にも婦人科がん、消化器がんほか、病院各科から訪れる患者さんに対して、3人のスタッフ医師で、1日約100人の患者さんを手分けして診療にあたる。
「現在、一番の問題点は、当科はもちろんのこと、全国的に放射線治療医や専門技術者が少ないことです。機器や治療技術が次々進化しているのに比して、専門家が極度に不足しているのが現状です」
陽子線、重粒子線などの粒子線治療、IMRT(強度変調放射線治療)、IGRT(画像誘導放射線治療)をはじめとする高精度放射線治療など、最先端の治療法やその機器について、マスコミでは盛んに取り沙汰されているにもかかわらず、放射線科や放射線科医に対する世の中のイメージは、まだまだ人口に膾炙していないと萬さんは感じている。
「放射線科というと、どこの病院でも地下にあって、暗くて冷たいというイメージを持っている人が多いようです。しかし、それには誤解があります。放射線科は、元々が緩和ケア的要素を強く持っていた治療科であることはお話ししてきたとおりですが、それ故に、とてもスローで温かいということを理解していただきたい。
各科での治療に疲れてたどり着いた患者さんの癒しの場になっていると強く感じます。コンピュータや機械中心のイメージがあるかもしれませんが、検査でも治療でも人が介在しないとできない、人の温かさがあっての治療なんです」
放射線技師がもつ優しさ
とくに放射線技師や看護師、事務員らスタッフの日常の仕事ぶりには頭が下がると萬さんは話す。
「他科での治療で弱って、つらい気持ちで訪れる患者さんに、技師さんたちは、放射線治療が終わるまで、30回も40回も会うわけですから、その接し方はとても優しいです。機械は冷たくても、そこへ優しく誘導して、優しく声をかけて、体をさすったり、息を整えたり、本来医者がするべき〝手当て〟をしっかりしています。治療計画なども、夜遅くまで残って、彼らと若手医師が行っています」
自分は放射線科のチームが円滑に動くためのコーディネーターに過ぎないと、萬さんは言う。そんなチームを率いて、他科、とくに連携が重要な、泌尿器科、耳鼻咽喉科、乳腺科、婦人科などとがっちりスクラムを組んで、最良の治療を届けるために日々の努力を惜しまない。
放射線治療医に大切な資質――血の通ったアプローチ
「放射線治療における今後のトピックスは、病巣をピンポイントに狙え、副作用も少ない外照射の高精度な治療がわが国でどこまで普及していけるかでしょう。小線源療法もまだ実施施設は限られていますが、同様にいかに優しい治療ができるかが模索されていくでしょう」
治せない治療から治せる治療へ変貌してきた放射線治療は、今後も目覚しい進歩を続けていくことが予想されるが、同時に血の通った、昔ながらのかかりつけ医的なアプローチができることも、放射線治療医には大切な資質だと萬さんは繰り返す。
「診療で多くの患者さんと接してきましたが、こっちが話を聞いてあげたというよりは、患者さんの話からあらゆることを教えてもらったというのが、私の心境です。皆さんの仕事や生活、そして歩んで来た人生のこと、家族のこと、日々の悩みなど、あらゆる話を聞くことを通じて、そのすべてが私にとって糧になっています。そういう意味では、患者さんが私のメンターだと言うこともできるかもしれませんね」
そう微笑む萬さんの柔和な笑顔は、医師として患者さんとのいい関係を築き続けてきたことを示す雰囲気にあふれていた。


